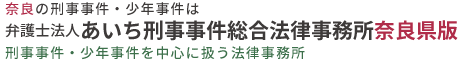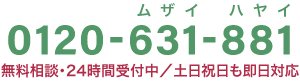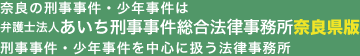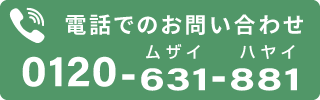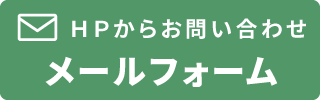Archive for the ‘財産犯’ Category
【事例紹介】コンビニで万引きし呼び止めた人を押し倒して事後強盗罪で逮捕された事例
【事例紹介】コンビニで万引きし呼び止めた人を押し倒して事後強盗罪で逮捕された事例

コンビニでパンなどを盗み、呼び止めた人に暴行を加えたとして事後強盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
4月8日早朝、奈良市内のコンビニエンスストアからパン等2点を盗み、さらに、これを発見した被害者に呼び止められた際、逮捕を免れるために被害者の体を押し倒す暴行を加えたとして、女(37歳)を事後強盗で現行犯逮捕しました。
(4月15日発表 奈良県警察WeeklyNews 「事後強盗で女を逮捕《奈良署》」より引用)
事後強盗罪
刑法第238条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
事後強盗罪は刑法第238条で規定されています。
簡単に説明すると、窃盗罪にあたる行為をした人が取り返されたり逮捕されないように、暴行や脅迫を行った場合には、事後強盗罪が成立します。
刑法第236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
刑法第236条1項では、強盗罪を規定しています。
事後強盗罪は強盗罪として扱われますので、有罪になると5年以上の有期懲役が科されます。
今回の事例では、奈良市内のコンビニでパンなど2点を盗んだ容疑者が逮捕を免れるために呼び止めた被害者の身体を押し倒す暴行を加えたとされています。
コンビニなどお店で料金を払わずに商品を盗む行為は窃盗罪が成立する可能性が高いですし、実際に容疑者がパンなどを盗んで逮捕を免れるために押し倒す暴行を加えたのであれば、事後強盗罪が成立する可能性があります。
万引きと事後強盗罪
万引きとは、お店で商品の代金を支払わずに盗む行為をいいます。
万引きでは多くの場合で窃盗罪が成立し、窃盗罪で有罪になった場合には、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます(刑法第235条)。
店員が万引きに気づいた場合、万引き犯を制止しようとするかもしれません。
制止してきた店員から逃げるために、暴行や脅迫を行うと、窃盗罪ではなく事後強盗罪が成立してしまうおそれがあります。
また、その際に店員にけがを負わせてしまうと、より刑罰の重い強盗致傷罪が成立してしまう可能性があります。
ちなみに、強盗致傷罪の法定刑は無期または6年以上の懲役(刑法第240条)ですので、強盗致傷罪で有罪になると、最悪の場合、無期懲役刑が科されてしまうおそれがあります。
万引きと聞くと罪が軽そうなイメージをもってしまいますが、窃盗罪は決して罪の軽い犯罪ではありません。
また、万引きの場合は盗んだ後の態様によっては事後強盗罪や強盗致傷罪など、窃盗罪よりも刑罰の重い罪に問われてしまう可能性があります。
窃盗罪では罰金刑が規定されていますが、事後強盗罪や強盗致傷罪には罰金刑の規定はありませんので、有罪になると必ず懲役刑が科されることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、刑の減刑や執行猶予付き判決の獲得など少しでも良い結果を得られる可能性がありますので、万引きなどの窃盗罪や事後強盗罪などでお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
【事例紹介】SNSで呼び出した相手に因縁をつけ、1万5千円脅し取った事例
【事例紹介】SNSで呼び出した相手に因縁をつけ、1万5千円脅し取った事例

因縁をつけた相手から現金を脅し取ったとして、恐喝罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
4月3日未明、共謀の上、奈良市内において、SNSで誘い出した被害者に対し「嫁にえらいことしてくれたな。誠意を見せろ。慰謝料30万円払え。」 等と因縁を付け、被害者から現金1万5千円を脅し取ったとして、男2人(いずれも22歳)、女(22歳)をそれぞれ恐喝で通常逮捕しました。
(4月5日発表 奈良県警察WeeklyNews 「恐喝で男女3人を逮捕《奈良署》」より引用)
恐喝罪
刑法第249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
恐喝罪とは簡単に説明すると、脅迫や暴行を用いて怖がらせ、相手からお金などを受け取ると成立する犯罪です。
脅迫や暴行が怖がらせる程度を超えて、抵抗が困難な程度に至っている場合には、恐喝罪ではなく、強盗罪が成立します。
今回の事例では、容疑者らがSNSで呼び出した被害者に「嫁にえらいことしてくれたな。誠意を見せろ。慰謝料30万円払え。」と言ったようです。
脅迫とは大まかに説明すると、身体などに危害を加えると知らせることをいいます。
直接的に危害を加えると言っていなくても、「誠意を見せろ」や「慰謝料30万円払え」と言われれば、慰謝料を払わなければ暴力を振るわれるのではないかと想像してしまうかと思います。
暴行を加えられることは身体への危害と言えますし、直接的に「暴力を振るうぞ」と言われなくても、暴力を振るわれるのではないかと想像してしまうような内容であれば、危害を加える告知をしたとして、脅迫にあたる可能性があります。
また、「誠意を見せろ」や「慰謝料30万円払え」と言われたとしても、その場から逃げたり、警察に通報できた可能性があります。
とはいえ、通常、成人男性から上記のような発言をされれば恐怖を感じるでしょう。
ですので、今回の事例の「嫁にえらいことしてくれたな。誠意を見せろ。慰謝料30万円払え。」という発言は恐喝罪が規定する脅迫にあたる可能性があります。
奈良県警察の発表によると、容疑者らは被害者から現金1万5千円を受け取っているようですので、実際に容疑者らが「嫁にえらいことしてくれたな。誠意を見せろ。慰謝料30万円払え。」と言って被害者からお金を脅し取ったのであれば、容疑者らに恐喝罪が成立するおそれがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
弁護士が示談交渉を行うことで、示談を締結できる場合があります。
被害者との間で示談を締結していることで、不起訴処分の獲得などに有利に働く可能性がありますので、恐喝罪で捜査を受けている方や、示談を考えている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
【事例紹介】奈良市内の側溝からグレーチングを盗んだ事例
【事例紹介】奈良市内の側溝からグレーチングを盗んだ事例

グレーチングを盗んだとして窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
1月9日昼過ぎ、奈良市内の側溝からグレーチング1枚(時価1万8,000円相当)を盗んだとして、3月25日、男(68歳)を窃盗で通常逮捕しました。
(3月29日配信 奈良県警察WeeklyNews 「窃盗で男を逮捕《奈良署》」より引用)
窃盗罪
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗罪とは簡単に説明すると、人の物をその人の許可なく自分の物や他人の物にすると成立する犯罪です。
今回の事例では、容疑者は奈良市内の側溝からグレーチング1枚を盗んだとされています。
このグレーチングははめられていた側溝が私有地にない限りは奈良県や奈良市の所有物だと考えられます。
ですので、所有者である奈良県や奈良市に許可を得ずに自分の物にしたのであれば、窃盗罪が成立する可能性があります。
また、私有地にあった場合であってもその私有地内にあるグレーチングは私有地の所有者の物でしょうから、自分の所有地以外の場所から所有者の許可なく自分の物にすると窃盗罪が成立すると考えられます。
ですので、実際に容疑者が側溝からグレーチングを盗んでおり、所有者の許可を得ていないのであれば窃盗罪が成立する可能性が高いでしょう。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
窃盗罪には罰金刑だけでなく懲役刑も規定されていますので、窃盗罪で有罪になると懲役刑が科されてしまう可能性があります。
グレーチングは金属でできていますので転売の餌食にもなりやすく、転売目的による窃盗なのではないかと疑われる可能性が高いと思われます。
転売目的による窃盗だと判断された場合、同じ被害額の窃盗事案と比べて転売目的の方が悪質性が高いと判断されより重い刑罰が科されてしまうおそれがあります。
また、転売目的だと疑われる場合には、余罪もあるのではないかと怪しまれることもあるかもしれません。
余罪がある場合とそうでない場合では、科される量刑が異なってくる可能性がありますので、注意が必要です。
転売目的でない場合や余罪がない場合には、取調べ段階で、転売目的や余罪をしっかりと否定することが大切です。
警察官や検察官は認めるように圧をかけてくることがあるかもしれませんが、良い結果を得るためには、違うことは違うとはっきりと否定し、意に反した供述調書の作成を防ぐことが非常に重要になってきます。
供述調書は処分の判断や裁判の証拠として使用されます。
もしも意に反した供述調書を作成されてしまった場合には、処分の判断に悪影響を及ぼしたり、裁判で窮地に立たされてしまう可能性があります。
そういった事態を避けるためにも、取調べ前に弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
窃盗罪でお困りの方は、捜査を受けている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
【事例紹介】駐車場から車を盗んだとして窃盗罪の容疑で逮捕された事例
【事例紹介】駐車場から車を盗んだとして窃盗罪の容疑で逮捕された事例

駐車場から車を盗んだとして窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
(前略)堺市西区内の駐車場から運転免許証等3点積載の普通乗用車1台(時価合計200万円相当)を盗んだとして、2月27日、男(32歳)を窃盗で通常逮捕しました。
(2月29日発表 奈良県警察WeeklyNews 「窃盗で男を逮捕《西和署、生駒署、捜査第一課》」より引用)
窃盗罪
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
簡単に説明すると、窃盗罪は、人の物をその人の許可なく、自分や他人の物にすると成立する犯罪です。
今回の事例では、駐車場から運転免許証などが積まれた車を1台盗んだとされています。
車の持ち主の許可なく自分の物にしたのであれば、容疑者に窃盗罪が成立する可能性があります。
自動車盗と量刑
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
窃盗罪は身近な犯罪のひとつだといえますし、身近な犯罪である分、軽視されがちですが、懲役刑が規定されている以上、有罪になった場合に懲役刑が科される可能性があります。
窃盗罪と聞くと、罰金刑で済むイメージを持たれている方や初犯では刑罰を受けることはないと思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、初犯であっても刑罰が科される可能性が高いですし、罰金刑で済まない場合も多々あります。
悪質性が高いと判断されたり、被害額が高額な場合には、初犯でも懲役刑が科されてしまう可能性があります。
自動車盗では、どうしても被害額が高額になってしまいますから、前科がなくても懲役刑が科されてしまう可能性があるといえます。
被害者に謝罪と賠償を行い、示談を締結することで執行猶予付き判決を得られる可能性があります。
容疑者と被害者が知り合いではない場合は、まず被害者の連絡先を手に入れることから始めなければなりません。
この場合には、警察官や検察官から被害者の連絡先を教えてもらうことになると思いますが、被害者保護の観点から教えてもらえない可能性があります。
また、容疑者が被害者の連絡先を手に入れられたとしても、容疑者が直接被害者と連絡を取ることで、証拠隠滅を疑われてしまう可能性があります。
弁護士が間に入ることで、円滑に示談を締結できる可能性がありますので、示談を考えている方は弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
窃盗罪でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
【事例紹介】奈良市内の飲食店で無銭飲食 詐欺罪で逮捕された事例
【事例紹介】奈良市内の飲食店で無銭飲食 詐欺罪で逮捕された事例

奈良市内にある飲食店で飲食代金を支払う意思や能力もないのに、飲食の提供を受けたとして、詐欺罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
1月17日夜、奈良市内の飲食店において、代金を支払う意思も能力もないのにあるように装って飲食を申し込み、飲食代金3,500円相当の飲食等の利便を受け、財産上不法の利益を得たとして、男(67歳)を詐欺で現行犯逮捕しました。
(1月22日発表 奈良県警察WeeklyNewsより引用)
詐欺罪
刑法第246条
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪は簡単に説明すると、人にうそをつき、そのうそを信じた相手からお金などの財物やサービスの提供などの財産上の利益を受け取ると成立する犯罪です。
このうそは、財物や利益を提供するうえで重要な事実に関するうそでなくてはなりません。
ですので、うそだと知っていても財物や利益を提供するような事実について、うそをついて財物や利益を受け取っても詐欺罪は成立しません。
今回の事例では、容疑者は奈良市内の飲食店で無銭飲食をしたとして、詐欺罪の容疑で逮捕されたようです。
無銭飲食をすると詐欺罪が成立するのでしょうか。
無銭飲食と詐欺罪
飲食店では、飲食の対価としてお金を払うのは当然ですから、わざわざ店員が支払う意思や能力があるのかどうかを客に確認することや客が注文の際に店員にお金を支払う意思や能力があることを伝えることはありません。
そういった事情から、客が注文をしたことで店員はお金を支払う意思や能力があると思うでしょう。
ですので、飲食店で注文をする行為は、対価としてお金を支払うと意思表示をしたことと同義だと考えられます。
無銭飲食では、支払う意思表示をしてサービスの提供を受けたのにお金を支払わないことになりますので、客が店員にうそをついてサービスの提供を受けたことになり、無銭飲食で詐欺罪が成立するおそれがあります。
今回の事例で、実際に容疑者が飲食代金を支払う意思や能力がないのに、あるように装って飲食をしたのであれば、詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺罪と不起訴処分
詐欺事件では、被害者と示談を締結することで不起訴処分を得られる場合があります。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですので、罰金刑の規定がないことから有罪になれば必ず懲役刑が科されることになります。
不起訴処分は起訴されない処分ですので、不起訴処分を獲得することができれば、前科は付きませんし、刑罰も科されることはありません。
不起訴処分は、嫌疑が不十分な場合や事件の悪質性が高くない場合、被害者が加害者の処罰を望んでいない場合などに付されます。
被害者と宥恕付きの示談を締結することで、検察官に被害者が処罰を望んでいないと判断してもらえる可能性があります。
被害者が処罰を望んでいない場合には、不起訴処分を獲得できる可能性が高まりますから、不起訴処分の獲得を目指す場合には宥恕付き示談の締結を目指すことが重要になります。
では被害者と宥恕付き示談を締結するにはどうしたらいいのでしょうか。
宥恕のありなしにかかわらず、示談を締結するためには、示談交渉を行う必要があります。
ですので、加害者本人が示談交渉を行う場合には、加害者自らが被害者の連絡先を手に入れ、示談交渉を行わなければなりません。
ただ、加害者自らが連絡を取る場合には、連絡先を知られたくない被害者が交渉自体を拒否する可能性や交渉できたとしても処罰感情を逆なでしてしまう可能性があります。
また、今回の事例のようにお店相手に示談をしなければならないような場合には、連絡先を手に入れることは容易でも、示談は受け付けてもらえない可能性が高いです。
そういった場合でも、弁護士であれば連絡先を教えてもらえる可能性や示談に応じてもらえる可能性があります。
一度、示談を断られてしまった場合でも、再度弁護士が示談交渉を行うことで示談を締結できる場合がありますから、示談交渉を行う際は弁護士を介して行うことが望ましいでしょう。
また、宥恕付き示談を締結する場合には、示談書に宥恕条項を加える必要があります。
どういった文言を示談書に記載すればいいのかわからない方も多いでしょうから、示談を考えている場合には、弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
示談交渉をはじめとした弁護活動によって、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
無銭飲食や詐欺罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
【事例紹介】共謀してコンビニで強盗を行い、現金約15万円を奪った事例

奈良県中部高市郡にあるコンビニで共謀して強盗を行い現金15万300円等を奪ったとして、強盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
共謀の上、3月20日未明、高取町内のコンビニエンスストアにおいて、店員に刃物を示して「金を出せ。殺すぞ。」などと脅迫し、現金約15万300円等を盗んだとして、12月5日、男2人(38歳、43歳)をそれぞれ強盗で通常逮捕しました。
(12月12日 奈良県警察WeeklyNewsより引用)
強盗罪
刑法第236条
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
強盗罪とは、簡単に説明すると、一般の人が抵抗できないような暴行や脅迫を用いてお金などを奪うと成立する犯罪です。
強盗罪は人を恐喝して金銭などを得た場合に成立する恐喝罪と類似しているように思われます。
もしも一般人が抵抗できない程度の暴行や脅迫に至っていない場合には、強盗罪ではなく恐喝罪が成立することになります。
今回の事例では強盗罪は成立するのでしょうか。
奈良県警の発表によると、容疑者らは店員に刃物を示して「金を出せ。殺すぞ。」などと脅迫して現金約15万300円等を盗んだとされています。
脅迫とは、一般の人が恐怖を感じるような害を与えると知らせる行為を指します。
突然、刃物を示されて「金を出せ。殺すぞ。」と言われれば、命や身体に危害を加えられるかもしれないと恐怖を感じるでしょうから、刃物を示して「金を出せ。殺すぞ。」と言う行為は脅迫にあたると考えられます。
また、たとえ一か所でも刃物で刺されれば死ぬ危険性がありますし、死に至らなくともけがをするわけですから、刃物を示されながら殺すと言われれば、抵抗は難しいでしょう。
ですので、今回の事例で容疑者らが実際にコンビニ店員に刃物を示して脅迫し、お金を奪ったのであれば、強盗罪が成立する可能性があります。
共犯事件と接見禁止決定
刑事事件では、逮捕後72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留が判断されるまでは家族であっても容疑者との面会ができません。
通常は、勾留が決定した後であれば、容疑者と面会ができるのですが、接見禁止決定がなされている場合には家族といえど面会をすることはおろか、手紙の差し入れさえできません。
接見禁止決定とはその名の通り、接見を禁止する決定のことです。
この接見禁止決定は外部の者と接触することで、証拠隠滅がなされることを防ぐためになされます。
容疑者が容疑を否認している否認事件や共犯者のいる事件などでは、口裏合わせなどを防ぐ観点から接見禁止決定がなされることがあります。
接見禁止が決定されてしまうと家族であっても面会できないわけですから、連日にわたる取調べでストレスを抱えるなか家族にも会えないことで、容疑者が精神的に追い詰められてしまうことがあります。
精神的に不調をきたすことで、判断力が鈍り取調べで警察官や検察官がいうがまま供述してしまったり、やってもいないことをやったと言ってしまう可能性があります。
取調べで作成される供述調書は、裁判の際の証拠として使用される重要なものであり、一度作成されてしまうと訂正をすることは容易ではありません。
取調べで不利な状況を作らないためにも、家族との面会などで少しでも心安らげる時間をもつことが重要となります。
また、勾留期間は最長で20日間に及ぶこともありますから、長期期間容疑者と会えないことで、体調に不調をきたしていないかなど容疑者本人だけでなくその家族も精神的に不安な状態に陥る可能性もあります。
弁護士は裁判所に対して、接見禁止を家族に限って解除するように求めることができます。
弁護士が、容疑者の家族は事件にかかわっておらず共犯者や被害者について何も知らないこと、容疑者に共犯者や被害者への伝言を頼まれても応じないこと、証拠隠滅につながるような行為は絶対にしないことを裁判所に訴えることで、接見禁止が一部解除される場合があります。
家族について接見禁止を解除してもらえれば、家族に限って容疑者との面会や手紙の差し入れを行うことができるようになりますので、ご家族様と面会したいのに接見禁止が決定されていて面会できないような場合には、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
また、弁護士は勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うことができます。
弁護士が裁判所に、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを訴えることで、勾留満期を待たずに釈放される可能性があります。
ですので、ご家族様が逮捕された場合には、一度弁護士に相談をしてみることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っております。
弁護士が接見を行うことで、少しでもご家族様への励みになるかもしれません。
また、弁護士による弁護活動で、接見禁止の一部解除や釈放を認めてもらえる可能性がありますので、ご家族様が逮捕された場合には、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120―631―881までご連絡くださいませ。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
【事例紹介】特殊詐欺事件で詐欺罪、窃盗罪の容疑で逮捕された事例
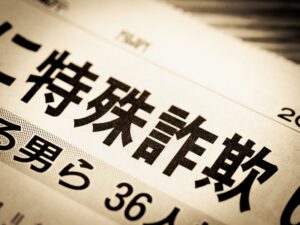
だまし取ったキャッシュカードで現金を引き出したとされている特殊詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
共謀の上、キャッシュカードをだまし取ろうと考え、9月19日、市役所職員等と名乗って被害者の自宅に電話をかけ、還付金を受け取るためにはキャッシュカードを交換しなければならず、自宅を訪れる金融機関職員にキャッシュカードを渡してほしい旨うそを言い、その後、被害者の自宅を訪問してキャッシュカード2枚をだまし取った上、そのカードを使用して橿原市内のATMから現金合計100万円を引き出して盗んだとして、11月14日、男(24歳)を詐欺、窃盗で通常逮捕しました。
(11月22日 奈良県警察発表より引用)
特殊詐欺と詐欺罪、窃盗罪
今回の事例では、容疑者が共謀して被害者からキャッシュカードをだまし取り、キャッシュカードを使用して現金100万円をATMから引き出したとして、詐欺罪、窃盗罪の容疑で逮捕されたようです。
今回の事例では、なぜ、詐欺罪と窃盗罪の2つの罪で逮捕されているのでしょうか。
詐欺罪
まずは、詐欺罪について解説していきます。
刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
詐欺罪は簡単に説明すると、人にうそをつくことで相手に財物を渡すように仕向け、そのうそを信じた相手から財物を受け取ると成立する犯罪です。
今回の事例では、容疑者は共謀して被害者に市役所職員等を名乗る電話をかけ、キャッシュカードを交換する必要があるとうそをつき、被害者からキャッシュカード2枚を受け取ったとされています。
容疑者らが被害者に交換が必要だとうそをつかなければ、被害者はキャッシュカードを渡していないでしょうから、実際に容疑者らがキャッシュカードの交換が必要だと被害者に言ったのであれば、容疑者らは被害者にキャッシュカードを渡すように仕向けるためにうそをついて財物であるキャッシュカードを受け取ったといえるでしょう。
ですので、今回の事例では詐欺罪が成立する可能性があります。
窃盗罪
次に、窃盗罪について解説していきます。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は簡単に説明すると、人の財物をその人の許可なく盗ると成立する犯罪です。
今回の事例では、容疑者はだまし取ったキャッシュカードを使用して橿原市内のATMから現金合計100万円を引き出したとされています。
引き出されたとされている現金100万円は橿原市内のATMに保管されていたものですから、この現金の所有者はこの橿原市内のATMを管理する銀行になります。
ですので、キャッシュカードの本来の持ち主ではない人がATMで現金を引き出すと窃盗罪が成立することになります。
よって、今回の事例の容疑者らがだまし取ったキャッシュカードで現金100万円を引き出したのであれば、詐欺罪だけでなく、窃盗罪が成立する可能性があります。
特殊詐欺事件と弁護活動
特殊詐欺事件では、詐欺罪だけでなく、窃盗罪も成立するおそれがあります。
詐欺罪や窃盗罪は有罪になると、懲役刑が科される可能性のある犯罪です。
また、詐欺罪に至っては、罰金刑の規定がありませんので、詐欺罪で有罪になると必ず懲役刑が科されることになります。
懲役刑が科されると刑務所に行くことになりますから、今までの生活をおくることはできなくなります。
実刑判決を回避するためには、不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得にむけた弁護活動が重要になります。
逮捕された場合、連日にわたって取調べが行われることになります。
取調べでは、容疑者から単に話を聞くだけでなく、供述調書が作成されます。
供述調書は裁判で証拠として扱われますし、検察官が起訴、不起訴の判断をするための判断材料にもなります。
ですので、不利な供述調書が作成された場合には、不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得が難しくなる可能性が高くなります。
不利な供述調書の作成を防ぐためにも、取調べ前に、供述すべき内容の整理を行っておく必要があります。
ですが、取調べではどのようなことを聞かれるのかわからない方や黙秘した方がいい内容と供述すべき内容がわからない方がほとんどだと思います。
弁護士に相談をして、取調べ前に対策を練っておくことで、後に不利な状況に陥ることを防げるかもしれません。
初犯では、実刑判決が下されないと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、特殊詐欺事件では、初犯でも実刑判決が下されることが少なくありません。
ですので、実刑判決を避けるためにも、できる限り早い段階で弁護士に相談をし、不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得に向けた弁護活動に着手することが重要になります。
実刑判決が下される可能性がある特殊詐欺事件では、不起訴処分の獲得を望めないように思われますが、被害者と示談を締結することで、不起訴処分を得られる可能性があります。
加害者が被害者と直接やり取りを行うことで、証拠隠滅を疑われたり、トラブルに発展するおそれがあります。
弁護士が加害者の代理人となって示談交渉を行うことで、円滑に示談を締結することができる場合がありますので、示談交渉は弁護士に委任することが望ましいといえます。
また、不起訴処分を得られなかった場合であっても、被害者との示談が執行猶予付き判決に獲得や罪の減刑など、有利な事情にはたらく可能性は非常に高いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
特殊詐欺事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
手術代が必要だとうそをつき、200万円をだまし取った事例

事例
Aさんは交際中のVさんとのデート中に、「健康診断で癌が見つかり、手術が必要だが手術費用が払えないため手術を受けられなくて悩んでいる」とVさんに吐露しました。
それを聞いたVさんはAさんの力になりたいと思い、現金200万円をAさんに渡しました。
その後、Vさんは、手術を受けるために病院に入院するというAさんからの連絡を最後に、Aさんとは連絡が取れなくなってしまいました。
Aさんの容体が気になっていたVさんは、何とかAさんの友人に連絡を取ることができ、Aさんの手術や経過についてその友人に尋ねました。
すると、Vさんはその友人から「Aさんが病気になったなんて話は聞いていないし、Aさんとは毎週のように会うけど、手術や入院なんて絶対にしてないし癌になったなんて嘘じゃないの?」と言われました。
なんと、癌になり手術費用が必要だというのは真っ赤な嘘で、VさんはAさんに騙されていたのです。
Vさんは最寄りの警察署である、奈良県長浜警察署に被害届を出し、Aさんは詐欺罪の容疑で奈良県長浜警察署の警察官に逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
詐欺罪とは
詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させると成立します。
もう少し簡単に説明すると、人にうそをついて、うそを信じた相手にお金などの財物を渡させると詐欺罪が成立します。
また、財物を交付させるうえで重要ではない要素についてのうそや、相手がうそだと知っている状態で財物を交付した場合には、詐欺罪は成立しません。
ですので、詐欺罪が成立するためには、①相手に対して重大な嘘をつくこと、②その嘘を信じた相手に財物を交付させることの2点が必要です。
加えて、詐欺罪で有罪になると10年以下の懲役が科される可能性があります。(刑法第246条第1項)
今回の事例では、AさんがVさんに手術が必要だとうそをついて、200万円をVさんから受け取っています。
Vさんは手術をするのにお金が必要だと言われなければ200万円を渡さなかったでしょうから、Aさんのうそは財物を交付するうえで、重大なうそだといえるでしょう。
重大なうそをついて財物を交付させているといえますので、今回の事例では、詐欺罪が成立する可能性が高そうです。
では、Aさんが騙すつもりはなかったと詐欺罪の容疑を否認している場合にはどうでしょうか。
詐欺罪で逮捕されたAさんは警察官からの取調べに対して、「手術が必要だとうそをついたのは本当だが、お金をほしいとは言っていない。お金を要求したわけではないのだから、詐欺罪にはあたらない。」と供述しています。
この場合、詐欺罪にはあたらないのでしょうか。
実際に事例をみてみると、AさんはVさんにお金がないから手術を受けられないと相談をしていますが、一言もお金が欲しいというような金銭の要求をしていません。
ですが、実際には手術の必要はない状態でお金が必要だとうそをつく行為は、そうすることでお金を得られると思ったからうそをついたのではないかと判断されても不思議ではありませんし、お金を得る目的でうそをついたのでなければ、200万円を渡されたときに受け取らないのが自然でしょう。
詐欺罪が成立するためには、財物を交付させる目的でうそをつく必要があります。
たとえ、自分から直接的にお金がほしいと言わなくても、お金を必要としていると思わせるようなうそをつくことで、うそによってお金を騙し取ろうとしていると判断できるような場合には詐欺罪が成立する可能性があります。
示談交渉の重要性
詐欺罪などの刑事事件では、示談交渉が非常に重要な役割を果たすことが多いです。
被害者との間で示談を締結することで、不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得できたり、科される量刑を少しでも減らすことができる可能性があります。
しかし、被害者の処罰感情が強い場合などには、加害者が直接示談交渉をすることはお勧めできません。
加害者が被害者に直接連絡を取ることで被害者をより怒らせてしまったり、そもそも連絡すら取れない場合も少なくありません。
ですので、示談交渉を行う際には、弁護士を介して行うことが望ましいでしょう。
また、当事者間で示談を締結する場合には、自分たちで示談書を作成することになります。
示談書の書式など、示談書にどういった内容を書けばいい のかわからない方がほとんどだと思います。
弁護士を入れて示談を締結する場合には、弁護士が代理人となって示談書を作成します。
そういった面でも、示談を行う場合には、弁護士を介して行うことが望ましいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
詐欺罪や示談締結でお困りの方は、詐欺事件などの刑事事件に精通した弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120―631―881までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
無断で傘を借りた場合に罪は成立するの? 窃盗罪と使用窃盗
無断で傘を借りた場合に罪は成立するのかどうかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
郵便物を投函しようと奈良県大和高田市にあるポストに向かっていたAさんは、ポストに向かう途中に通り雨に降られてしまいました。
通り雨といえど雨脚は強くすぐに止みそうにはありませんし、ポストまではまだ5分ほど歩かなければなりません。
ふと周りを見渡したAさんは、店先に傘が傘立てに置かれていることに気づきました。
悪いことだとは思いつつもAさんは傘を拝借し、10分後、傘を元にあった場所に戻しました。
この場合、Aさんは何か罪に問われるのでしょうか。
(事例はフィクションです。)
窃盗罪と使用窃盗
成立する可能性がある罪として、窃盗罪が挙げられます。
窃盗罪は刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
今回の事例では窃盗罪が成立するのでしょうか。
窃盗罪は財物を占有者の意思に反して、自分や第三者に占有を移転させると成立します。
もう少しわかりやすく説明すると、持ち主の意思に反して、持ち主が占有している物を自分や他の人へと占有を移すと窃盗罪が成立します。
占有とは何でしょう。
占有とは、財物の事実的な支配や管理を指します。
誰から見ても誰かの持ち物だとわかる状態であり、持ち主が自分のものだと認識している物には占有があるとみなされます。
店の傘立てに置かれていた傘はおそらく店の店主や従業員、お客さんの持ち物でしょう。
このように、誰から見ても持ち主がいることがわかる状態であり、持ち主が自分のものだと思っている物には占有があるとみなされます。
Aさんが傘を無断で借りてから返すまでの間の10分間は、Aさんが傘を使用していたわけですから、この10分間についてはAさんに占有が移っていたといえます。
そして、Aさんが傘を元の場所に戻した際に、傘の占有がAさんから元の持ち主の下に戻ったことになります。
一時的でも占有が移転したのであれば窃盗罪が成立しそうですが、窃盗罪は成立するのでしょうか。
結論から言うと、今回の事例では窃盗罪が成立しない可能性が高いといえます。
今回の事例では、Aさんは傘を拝借してから10分後に元の場所に戻しています。
傘の占有がAさんに移動したとはいえ、10分後には元の持ち主に占有が戻ったことになります。
占有の移転が一時的である場合には、被害者の損害が軽微であるとして、窃盗罪ではなく使用窃盗にあたるとして不可罰としています。
例えば、封筒を開けるのに他人のカッターを使用して、すぐに元の場所に戻した場合、カッターの持ち主にはほとんど損害が発生しないでしょう。
このように損害が発生しないような場合や発生したとしても軽微である場合には、窃盗罪は成立せず、使用窃盗として扱われます。
使用窃盗は不可罰ですので、懲役刑や罰金刑などの刑罰は科されません。
今回の事例でも、Aさんの下に傘の占有が移動していた時間は10分と短く、傘の所有者が被る損害はごくわずかでしょう。
ですので、今回の事例では窃盗罪ではなく使用窃盗にあたりそうです。
窃盗罪が疑わしい場合は弁護士に相談を
窃盗罪と使用窃盗の境界線は明確に規定されているわけではなく、曖昧です。
ですので、物の使用時間や拝借を繰り返した回数によっては、使用窃盗にはあたらずに窃盗罪が成立してしまうおそれがあります。
逆に言えば、窃盗罪で捜査を受けていても、場合によっては使用窃盗にあたる可能性もあります。
弁護士が主張することで、使用窃盗だと判断してもらえる可能性がありますので、窃盗罪で捜査を受けている方は一度弁護士に相談をしてみることをお勧めします。
窃盗罪は有罪になると懲役刑が科される可能性のある罪です。
窃盗罪は示談を締結することで不起訴処分を見込める場合があります
弁護士に相談をすることで示談を締結できる可能性がありますから、窃盗罪でお困りの方は弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
窃盗罪でお困りの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120―631―881までご連絡くださいませ。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
詐欺罪と弁護活動:架空請求の事例で理解する7つのポイント
詐欺罪は、日常生活からビジネスまで多くのシーンで起こり得る犯罪です。
この記事では、詐欺罪の定義から、弁護活動に至るまでを具体的な事例を交えて解説します。
1. 詐欺罪の基本的な定義
詐欺罪とは、他人を欺き財物を交付させることを指します。
具体的には、日本の刑法246条1項により定義されています。
2. 詐欺罪の基本的な成立要件
詐欺罪の成立要件には主に三つの要素があります。
第一に、欺罔行為(虚偽の事実を告げるなど)を用いることが必要です。
第二に、相手が錯誤に陥ること。
第三に、相手方から財物が交付されること。
以上の三つの要素が揃った場合に、詐欺罪が成立します。
刑法246条1項では、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」と規定されています。
以上が詐欺罪の基本的な成立要件になります。
次の項目では、欺罔行為の手法について具体的に解説していきます。
3. 欺罔の手法とは
詐欺罪の成立要件の一つである欺罔行為にはさまざまな形があります。
そもそも欺罔行為とは、相手にうそをつき欺く行為を指します。
具体的には、虚偽の事実を告げる、誇大な宣伝を行う、または情報を隠蔽するなどが該当します。
詐欺罪で重要なのは、欺罔行為が被害者を錯誤に陥らせるだけでなく、その錯誤を利用して財産の交付を引き起こさなければならない点です。
ですので、欺罔行為は人に対して行う必要があり、財物の交付を引き起こすようなものでなくてはなりません。
欺罔行為は基本的には言葉による操作が多いですが、行動や状況を利用する場合もあります。
例えば、壊れた商品を新品として売りつける行為も欺罔行為の一つです。
こうした欺罔行為が被害者の判断を誤らせ(錯誤に陥らせ)、財産を交付させる状況が生まれると、詐欺罪の成立要件が揃うことになります。
以上が欺罔行為の手法についての解説です。
次の項目では、被害者が財産を交付する過程について詳しく説明します。
4. 被害者による財産の交付
詐欺罪の成立要件の一つとして、被害者を欺罔行為によって錯誤に陥らせ、財産を交付させることが必要です。
財産の交付とは、被害者が財産を詐欺犯に譲渡する行為を指します。
この財産は、現金だけでなく、物品や不動産、サービスなども含まれます。
重要なのは、被害者が欺罔行為に基づいて自ら行動を起こす点です。
例えば、被害者が欺罔行為によって騙されて自分から振り込みを行った場合、この要件は成立します。
しかし、財産が盗まれた場合や、被害者が何もしなかった場合は、この要件は成立しません。
財産の交付の成立要件には、被害者が自らその行動を選択している必要があります。
つまり、被害者が欺罔行為により錯誤に陥り、その結果として財産を譲渡(交付)する選択をした場合に限り、詐欺罪の成立要件が揃います。
この財産の交付の要件は、詐欺罪が成立するための非常に重要な要素です。
詐欺事件が発生した際には、この財産の交付が明確に行われたかどうかが、事件解決においてキーとなります。
以上が被害者の財産の交付についての解説です。
5. 特殊詐欺の一例: 架空請求
特殊詐欺の中でも、特に知られている事例の一つが架空請求です。
この手法は、被害者に対して実際には発生していない料金や費用の支払いを求めるものです。
これも基本的な詐欺罪の成立要件、すなわち欺罔行為、錯誤、財産の交付が全て揃う場合に適用されます。
架空請求の多くは、インターネット上でのポップの表示、メールや電話、書面によって行われます。
例として、インターネット上の有料サービスに登録したと偽り、料金の支払いを求めるケースがあります。
被害者がこのような偽の請求に応じて支払いを行うと、詐欺罪が成立します。
もう少し詳しく見ていきましょう。
実際には支払う必要のない料金の支払いを求めていることから、加害者がうそをついていることになります。
人に対して、財物を交付するうえで重要なうそをついていることから、詐欺罪で規定する欺罔行為にあたると考えられます。
この加害者の欺罔行為により、被害者が支払う必要があると信じ(錯誤に陥り)、料金を加害者に支払えば、財物が交付されたことになりますので、詐欺罪が成立することになります。
以上が特殊詐欺の一例、架空請求についての解説です。
次の項目では、詐欺罪に対する刑罰について詳しく説明します。
6. 詐欺罪に対する刑罰
詐欺罪が成立した場合、その後に待ち受ける刑罰について解説します。
詐欺罪で有罪になると、10年以下の懲役が科されます。
特に大規模な詐欺事件や組織的な詐欺事件が確認された場合、より重い刑罰が科される可能性があります。
詐欺罪で有罪になると、前科が付くことになり、その後の社会生活に多大な影響を与える可能性があります。
例えば、就職活動や資格取得に障害が出ることも考えられます。
そのため、詐欺罪で有罪になると、単に刑罰を受けるだけでなく、その後の人生にも影響を及ぼす重大な問題となります。
7. 詐欺罪で捜査を受けた場合の初動対応
詐欺罪の疑いで捜査を受けた場合、その初動対応が非常に重要になってきます。
以下では、その具体的内容を解説します。
・すぐに弁護士に相談する
詐欺罪で捜査を受けた際にまずやるべきことは、専門家である弁護士に即座に相談することです。
弁護士は、事件の全体像を把握し、最適な対応策を提案してくれます。
事件によって必要となる弁護活動や処分の見通しは異なってきます。
不起訴処分や執行猶予付き判決の獲得など、より良い結果を得るためにも、早期に弁護士に相談をすることをおすすめします。
・自白や供述を避ける
取調べでは、警察官などの都合の良いように供述が誘導される可能性が高いです。
また、否認事件の場合は、自白を強要されることもあります。
取調べで供述した内容を基に、後の裁判で証拠として使用される供述調書が作成されます。
一度でもあなたの不利になるような供述調書を作成されてしまうと、内容を覆すことは難しく、裁判で不利な状況に陥ってしまう可能性があります。
ですので、どういった内容を供述すればいいのかわからない場合や取調べが不安な場合には、警察に任意で事情を説明することは避け、弁護士が到着するまで黙秘することが望ましいでしょう。
無料法律相談のご利用を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
詐欺事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得できるかもしれません。
ご家族が逮捕された方に向けて、初回接見サービスも行っておりますので、詐欺罪でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。