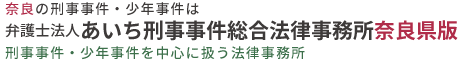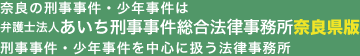| ※2025年6月1日より、改正刑法に基づき懲役刑および禁錮刑は「拘禁刑」に一本化されました。 当ページでは法改正に基づき「拘禁刑」と表記していますが、旧制度や過去の事件に関連する場合は「懲役」「禁錮」の表現も含まれます。 |
(1)少年事件の特色
少年法1条には、少年法の目的として、次のように定められています。
この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。
このような、過ちを犯した少年(20歳未満の者)に対しては、成人のように刑罰ではなく、健全な成長・発達を促す働きかけが必要であるという考え方のもと、少年事件においては、成人とは異なる手続が採られます(なお、捜査段階では、被疑者が少年の場合であっても基本的には刑事訴訟法が適用されます)。
また、少年の事件ついて捜査した結果、家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合には、全ての事件を家庭裁判所に送致することを義務付けています(全件送致主義)。この点でも、微罪処分・不起訴処分といったかたちで事件が終わる成人の手続と異なります。
(2)補導について
補導という言葉は少年事件に関する法律に限らず用いられていますが,警察官が少年に対して行うものは,少年警察活動規則に定められています。
補導として多く見られるのが街頭補導です(少年警察活動規則7条)。
街頭補導とは,道路その他の公共の場所、駅その他の多数の客の来集する施設又は風俗営業の営業所その他の少年の非行が行われやすい場所において、非行少年(少年法2条5号)などを発見したとき、必要に応じその場で、これら非行少年について、当該少年に係る事件の捜査又は調査のほか、その適切な処遇に資するため必要な範囲において、時機を失することなく、本人又はその保護者に対する助言、学校その他の関係機関への連絡をするなどの必要な措置をとるというものです。
(2の2)非行少年について
非行少年とは、少年法では、次の3種類の少年のことです。
ア 犯罪少年(少年法3条1項1号)
罪を犯した少年がこれに当たります。
イ 触法少年(少年法3条1項2号)
罪を犯した少年で、14歳未満のため刑事責任を問われない少年がこれに当たります。
ウ 虞犯少年(少年法3条1項3号)
直接刑罰法規に該当する行為はしていないが、家に寄り付かなくなったり,犯罪性のある人と交際するなど,その性格又は環境に照らして将来罪を犯したり刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年がこれに当たります。
犯罪少年は捜査機関の捜査の対象となります。
触法少年及び虞犯少年は,捜査ではなく調査を受けることになります。
少年警察活動規則上は,犯罪少年に対する捜査も触法少年及び虞犯少年への調査と同様に、少年警察部門に属する警察官に行わせるものとされています(少年警察活動規則12条1項本文)。事件の内容及び当該警察本部又は警察署の実情に鑑み、適切な捜査又は調査の実施のため必要と認められるときは、別の部門が対応します(少年警察活動規則12条1項但書)が、その場合においても,少年の特性に配慮した捜査が行われるよう、少年警察部門に属する警察官に捜査経過について常に把握させ、捜査を行う警察官に対する必要な支援を行わせるものとすることになっています(少年警察活動規則12条2項)。
(2の3)手続の流れ
ア 身柄事件
(ア)逮捕から勾留
少年事件であっても、逮捕され、勾留されます。その際の手続も成人事件と異なりません。
(イ)勾留に代わる観護措置
勾留については、検察官は、勾留請求に代えて観護措置を請求することができます。この請求に基づく観護措置を勾留に代わる観護措置と言い,少年事件特有の制度です。
この勾留に代わる観護措置が執られると、少年の身体拘束は留置場ではなく少年鑑別所で行われることとなります。
少年鑑別所は、罪を犯した少年がどのような理由から犯罪行為に至ったのかを医学や心理学、教育学といった視点から解明する場所で、留置場と異なり、少年の心身への影響にも配慮した施設です。そこで、どうしても身体拘束を免れない場合は、検察官や裁判官に対して、勾留に代わる観護措置をするよう働きかけを行うことが考えられます。
ただし、実際に勾留に代わる観護措置が執られることは非常に稀です。
イ 在宅事件
在宅事件の捜査は、少年事件と成人事件で大きく異なるところはありません。
ウ 家庭裁判所送致
身柄事件でも在宅事件でも、検察官は、必要な捜査が終わったら、事件の記録を家庭裁判所に送ります。
成人の刑事事件においては、検察官の裁量で不起訴処分とすることもありますが、少年事件ではそのような裁量は認められておらず、犯罪の嫌疑がある限り、全ての少年事件を家庭裁判所に送致することになっています(「全件送致主義」といいます)。
(3)鑑別所
事件の送致を受けた家庭裁判所は、審判を行うため必要があるときは、観護措置という措置を執ることができます。必要があるとき、とは、
ア 審判開始予定があること
イ 非行事実を疑うに足りる事情の存在
ウ 罪証隠滅・逃亡のおそれ
エ 心身鑑別の必要性があること
といった諸要素を総合考慮して判断されます。
観護措置には、家庭裁判所調査官の観護に付する(少年法17条1項1号)という措置もありますが、実際には、観護措置と言えば少年鑑別所への送致です(少年法17条1項2号)。
逮捕・勾留されていた場合、多くは家庭裁判所送致の際に、少年鑑別所に送致されます。
鑑別所では、家庭裁判所の決定のための資料を収集するため、少年の資質について科学的な調査と診断が行われます(心身鑑別)。具体的には、知能検査、心理テスト、日頃の行動観察などを行います。これらの鑑別の結果は、鑑別結果通知書として家庭裁判所に送られ、裁判官が少年の処遇を決定する際の重要な判断材料になります。
鑑別所への収容期間は2週間、基本的に特に継続の必要があるときは1回更新することができます(少年法17条3項・4項本文)。実際には、4週間収容されることがほとんどです。
この期間が終わるまでに、審判期日が設けられることになります。
なお、14歳以上で罪を犯した少年に係る死刑、拘禁刑に当たる罪の事件でその非行事実(犯行の動機、態様及び結果その他の当該犯罪に密接に関連する重要な事実を含みます)の認定に関し証人尋問、鑑定若しくは検証を行うことを決定した者又はこれを行った者について、少年を収容しなければ審判に著しい支障が生じるおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合には、その更新は、更に2回を限度として行うことができるとされています(少年法17条4項但書)。
(3の2)家庭裁判所調査官の調査
家庭裁判所の審判が開かれるまでに、家庭裁判所調査官が事件送致された少年やその保護者と面談し、事件の原因や少年が非行に至った動機、生育歴、生活環境等を調査します。
裁判官は、家庭裁判所調査官の意見を重視するため、この意見の如何が今後の少年の処分に大きく影響します。
(4)審判不開始・不処分
ア 審判不開始
家庭裁判所は、調査の結果、審判を開始するのが相当であると認めるときは、その旨の決定をしなければなりません(少年法21条)。
一方、審判に付することができず、又は審判に付するのが相当でないと認めるときは、審判を開始しない旨の決定をしなければなりません(少年法19条1項)。
イ 不処分
家庭裁判所は、審判をした結果、保護処分(少年法24条)に付することができず、又は保護処分に付する必要がないと認めるときは、その旨の決定をしなければなりません(少年法23条2項)。少年に対して訓戒を与えた上で、手続は終了します。
(4の2)少年審判
少年審判は、裁判官が、法的調査と社会調査の結果を踏まえ、少年に非行事実の有無及び要保護性があったかどうかを判断し、少年の抱えている問題点に応じた処分を選択するための手続きです。
要保護性とは、
ア 再非行の可能性(犯罪的危険性)
イ 矯正可能性(保護処分による矯正教育を施すことによってその犯罪的危険性を除去できる見込みないし可能性)
ウ 保護処分選択相当性(保護処分による保護が当該少年に対して最も有効適切な処遇であること)
をいいます。
少年審判は、原則として非公開で行われます。成人の刑事事件では公開が原則ですが、少年審判では、成長発達途中にある少年を保護し、社会復帰を円滑に進める必要があることと、審理の内容が少年やその家族のプライバシーに深く関わる点ことから、原則として非公開とされています。
(4の3)試験観察
試験観察とは、審判に付された少年の終局処分を決定する以前に、少年を相当期間、家庭裁判所の調査官に観察させるというものです。どのような保護処分を採るべきかの判断が困難であり、引き続き少年を観察した上で決定する必要がある場合に、試験観察に付されます。
(5)保護観察
家庭裁判所は,保護処分が必要であると判断したときは,保護観察,児童自立支援施設又は児童養護施設への送致,少年院送致の判断をします(少年法24条)。
保護観察とは、少年を家庭や職場等の環境に置いたまま、保護観察所の行う社会内処遇により、少年の改善更生を図ろうとする保護処分です(少年法24条1項1号)。1か月に一度ほど保護観察所の保護官や保護司の下に行き,指導を受けることになります。
ア 保護観察の期間
保護観察の期間は少年が20歳に達するまで,20歳に達するまでが2年に満たないときは2年間となります(更生保護法66条1項)。
ただし,処分時に18歳・19歳の少年(特定少年)については,6ヶ月間か2年間かのいずれかとなります(少年法64条1項)。
イ 保護観察の実施
保護観察は、保護観察対象者の改善更生を図ることを目的として、指導監督並びに補導援護を行うことにより実施します(更生保護法49条1項)。
(ア)指導監督
指導監督の方法は,面接その他の適当な方法により保護観察対象者と接触を保ち、その行状を把握すること(更生保護法49条1項1号),少年が遵守事項を遵守し、並びに生活行動指針に即して生活及び行動するよう、必要な指示等をすることなど(更生保護法49条1項2号),特定の犯罪的傾向を改善するための専門的処遇を実施すること(更生保護法49条1項3号),によって行います(更生保護法57条1項)。
(イ)補導援護
補導援護の方法は、少年が自立した生活を営むことができるようにするため、その自助の責任を踏まえつつ、適切な住居その他の宿泊場所を得ること及び当該宿泊場所に帰住することを助けること(更生保護法58条1号)などにより行います(更生保護法58条)。
ウ 一般遵守事項及び特別遵守事項
保護観察対象者は、再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること(更生保護法50条1項1号),保護観察官及び保護司による指導監督を誠実に受けること(更生保護法50条1項2号)などの一般遵守事項,犯罪性のある者との交際やいかがわしい場所への出入りなどをしないこと(更生保護法51条2項1号)などの特別遵守事項を遵守していくことになります。
エ 生活行動指針
保護観察所の長が、少年について、保護観察における指導監督を適切に行うため必要があると認めて、少年の改善更生に資する生活又は行動の指針すなわち生活行動指針を定めることができ,少年は、これに即して生活し、及び行動するよう努めなければなりません(更生保護法56条1項・3項)。
オ 保護者に対する措置
保護観察所の長は、必要があると認めるときは、保護観察に付されている少年の保護者に対し、その少年の監護に関する責任を自覚させ、その改善更生に資するため、指導、助言その他の適当な措置をとることができます(更生保護法59条)。
カ 被害者等の心情等の伝達
保護観察所の長は、少年について被害者やその遺族等から、被害に関する心情、被害者等の置かれている状況又は保護観察対象者の生活若しくは行動に関する意見の伝達の申出があったときは、この心情等を聴取し、少年に伝達する場合があります(更生保護法65条1項)。
(6)少年院送致
少年院送致は、少年法上の保護処分として最も強力な処分です。
少年院は、少年に矯正教育を授ける施設です。少年院は、児童自立支援施設または児童養護施設と異なり、少年の非行防止のため、基本的に外出が許されない非開放的な施設です。
短期処遇は原則6ヶ月以内、長期処遇は原則2年以内となります。
ただし,処分時に18歳・19歳の少年(特定少年)については,上限3年の範囲内で少年審判の際に決定されます(少年法64条3項)。
ア 少年院の種類
少年院は4種類に別れ,少年により入れられる場所が異なってきます。また,女子については女子少年院があります。
(ア)第一種
保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がないおおむね12歳以上23歳未満の者
(イ)第二種
保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がない犯罪的傾向が進んだおおむね16歳以上23歳未満の者
(ウ)第三種
保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害があるおおむね12歳以上26歳未満の者
(エ)第四種
少年院において刑の執行を受ける者
イ 処遇
少年院入所者の処遇は、その人権を尊重しつつ、明るく規則正しい環境の下で、その健全な心身の成長を図るとともに、その自覚に訴えて改善更生の意欲を喚起し、並びに自主、自律及び協同の精神を養うことに資するよう行うものとされています(少年院法15条1項)。また,医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識及び技術を活用するとともに、個々の在院者の性格、年齢、経歴、心身の状況及び発達の程度、非行の状況、家庭環境、交友関係その他の事情を踏まえ、その者の最善の利益を考慮して、その者に対する処遇がその特性に応じたものとなるようにしなければならないとされています(少年院法15条2項)。
少年には、その改善更生の状況に応じた矯正教育その他の処遇を行うためとして、成績の評価に応じ、①矯正教育の目標、内容及び実施方法,②社会支援の実施方法,③居室の指定、援助その他の在院者の生活及び行動に関する処遇の実施方法,といった処遇の段階が向上又は低下されて行われます(少年院法16条)。
ウ 矯正教育
矯正教育は、在院者の犯罪的傾向を矯正し、並びに在院者に対し、健全な心身を培わせ、社会生活に適応するのに必要な知識及び能力を習得させることを目的とし(少年院法23条1項),生活指導(少年院法24条),職業指導(少年院法25条),教科指導(少年院法26条),体育指導(少年院法28条),特別活動指導(少年院法29条)により実施されます。教科指導によりいずれかの学校の教育課程に準ずる教育の全部又は一部を修了した在院者は、その修了に係る教育の範囲に応じて当該教育課程の全部又は一部を修了したものとみなされます(少年院法27条1項)。また,社会復帰に向けての支援も行われます(少年院法44条)。
エ 外部交通
少年の保護者などは少年院にて少年と面会することができますが(少年院法92条1項1号),人数や場所時間などが制限され(少年院法95条1項),職員による立会又は面会の録音録画が行われます(少年院法93条1項)。
また,手紙など信書の発受(少年院法98条)も,検査を受ける(少年院法99条1項)などの制限があります。
(6の2)児童自立支援施設または児童養護施設送致
児童自立支援施設または児童養護施設送致は、児童福祉法上の支援を行うことを目的として、これらの施設に収容する保護処分です。これらの施設は、少年院と異なり解放された施設ですので、解放された環境の中で訓練や指導を受けることとなります。
(7)検察官送致
少年が20歳に達して少年法の適用対象から外れたり、事件が重大で少年の更生よりも処罰を優先するべきときは、通常の刑事手続によるべく、検察官送致されます。
ア 20歳になっていた場合の検察官への送致(少年法19条2項)
家庭裁判所は、調査の結果、本人が20歳以上であることが判明したときは、前項の規定にかかわらず、決定をもつて、事件を管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければなりません。
イ 逆送事件(少年法20条)
18歳未満の少年について,家庭裁判所は、死刑、拘禁刑に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき(パターン①)は、決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければなりません(少年法20条1項)。
また、18歳未満の少年について,家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るもの(パターン➁)については、管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致する決定をしなければなりません。ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、送致する決定をしないことができます(少年法20条2項)。
一方で,行為時に18歳・19歳の少年(特定少年)については,死刑、拘禁刑に当たる罪の事件に加えて,罰金等に当たる罪の事件であっても、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるとき(パターン①の拡大)は,決定をもって、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければなりません(少年法62条1項)。
さらに,行為時に18歳・19歳の少年(特定少年)については,家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であって、その罪を犯すとき16歳以上の少年に係るものだけではなく,死刑または無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる罪の事件についても(パターン➁の拡大)、管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致する決定をしなければなりません。ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、送致する決定をしないことができます(少年法20条2項)。
検察官送致されると、成人と同様の刑事手続が進みます。有罪判決が下されれば前科となります。
検察官送致を避けるためには、事件の経緯、実態について正しく裁判所に伝える他、示談を成立させるなどして被害を回復し、刑事手続による必要性をなくしていくことが重要となります。
(7の2)検察官関与(少年法22条の2)
家庭裁判所は、14歳以上で罪を犯した少年に係る事件であって、死刑又は無期若しくは長期3年を超える拘禁刑に当たる罪のものにおいて、その非行事実を認定するための審判の手続に検察官が関与する必要があると認めるときは、決定をもって、審判に検察官を出席させることができます(少年法22条の2第1項)。家庭裁判所は、この決定をするためには、検察官の申出がある場合を除き、あらかじめ検察官の意見を聴かなければなりません(少年法22条の2第2項)。
検察官関与の決定があつた事件において、検察官はその非行事実の認定に資するため必要な限度で、事件の記録及び証拠物を閲覧し及び謄写し、審判の手続(事件を終局させる決定の告知を含みます。)に立ち会い、少年及び証人その他の関係人に発問し、並びに意見を述べることができます(少年法22条の2第3項)。
少年の非行事実が認定されるよう主張する検察官が審判に同席して少年に質問をしたり意見を述べること自体、少年に悪影響を与えかねません。非行事実に争いがある場合であることが多いですが、非行事実がないことが明らかであること、あるいは逆に問題なく認定できること、検察官の関与による少年への悪影響などを主張して、検察官関与を回避する必要があります。
また、家庭裁判所は、調査の結果、児童福祉法の規定による都道府県知事又は児童相談所長に送致する場合であると認めれば、都道府県知事又は児童相談所長に送致する決定をします(少年法18条・23条1項)。
~弁護活動の例~
少年事件においては、手続の段階に応じて、種々の弁護活動を行います。
1 逮捕直後の段階
- 必要な事項を聴取の上、黙秘権等の権利・取調べに対する対応などを助言する。
- 供述調書録取に際してのアドバイスをする。
- 検察官に対して、勾留請求をしないでほしい旨働きかける。
- 勾留が避けられない場合、勾留に代わる観護措置をとるように働きかける。
2 勾留請求(又は勾留延長請求)がなされた段階
- 裁判官に対し、勾留(又は勾留延長)をしないように要請する。
- 検察官に対して、勾留延長請求しないように働きかける。
- 準抗告の申立てをする。
- 勾留取消請求、執行停止の申立てを行う
3 家庭裁判所に送致された段階
- 退学・解雇といったことにならないため、観護措置決定がとられないように活動する。
- 環境調整活動として、少年の保護者(家庭)、学校、職場等の関係者への働きかけ、少年自身の内省の促し及び少年自身の内省を踏まえた被害弁償、不良仲間との絶縁など交遊関係の改善、親子関係の修復等に向けた活動に着手(又は続行)する。
4 家庭裁判所による調査の段階
- 事件記録を謄写・閲覧し審判に向けて準備する。
- 少年が鑑別所いる場合は、面会して今後のことや法的な観点からのアドバイスをする。
- 観護措置取消しの申立てなどの不服申立て活動を行う。
- 環境調整活動を続行する。
- 家庭裁判所調査官と面談する。
5 審判の段階
- 少しでも軽い処分になるように活動する。
- 試験観察を採ることを提案し、最終的に軽い処分となるよう活動する。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を中心に扱う事務所として、刑事事件の経験が豊富な弁護士・スタッフが在籍しておりますので、少年事件で相談したいことがございましたら、弊所にご相談ください。