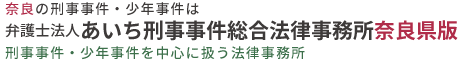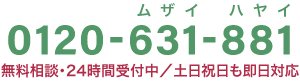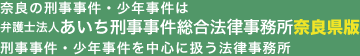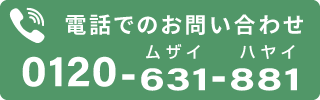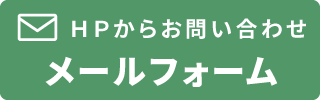Archive for the ‘財産犯’ Category
盗品等無償譲受罪で取調べ
盗品等無償譲受け罪で取調べ
盗品等無償譲受けについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県大和郡山市に住む大学生のA(19歳)は、無職の友人からブランド物の財布をプレゼントとしてもらいました。
実はこの財布は、友人が落ちていた財布をそのまま使っていたものであることが判明し、Aは盗品等無償譲受けの罪で、奈良県郡山警察署から呼び出しを受けることになってしまいました。
友人が拾った物だとは知らずに財布を譲り受けた事を主張するAは、取調べの前に両親と共に刑事事件に強い弁護士の無料法律相談を受けることにしました。
(この事例はフィクションです)
盗品等無償譲受け
盗品譲受等の罪については、刑法第256条に規定されており、盗品その他財物に対する罪に当たる行為によって領得された物に対する罪が規定されています。
第256条第1項に規定されている盗品等無償譲受け罪で起訴されて有罪が確定すると「3年以下の懲役」が科されることになります。
なお、第256条第2項には、盗品等を運搬、保管、有償譲受、有償の処分あっせんした者について「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」が規定されています。
盗品その他財物に対する罪に当たる行為とは、窃盗罪や今回の事例の横領罪は当然のこと、詐欺罪や恐喝罪も対象となります。
また、財産罪によって領得された財物が盗品等となるのですが、ここにいう犯罪行為は、構成要件に該当する違法行為であれば足りるとされ、必ずしも有責であることを必要としません。
つまり財産罪を犯した犯人が、刑事未成年者であったり、親族間の犯罪に関する特例の適用によって刑の免除を受けていたりしても、盗品等無償譲受けの罪は成立することになるのです。
財産罪の実行行為に加担していた者は、財産罪の共犯となるので、盗品等の罪の主体にはなり得ませんが、財産罪の教唆者や幇助者は、財産罪の実行行為を分担するのではないので、盗品等の罪の主体となり得ます。
そして、盗品等無償譲受け罪は故意犯となっています。
この罪が成立するには、行為者に盗品であることの認識がなければなりません。
この認識は、いかなる財産罪によって取得した物なのか、犯人や被害者が誰なのか等の詳細まで必要とされませんが、その財物が何らかの財産罪によって領得された物であることの認識は必要です。
そのため、今回のAのように盗品であることをまったく知らずに譲り受けたという主張が認められれば、盗品等無償譲受け罪は成立しない可能性があります。
少年事件の冤罪
少年事件は、逆送(家庭裁判所から検察庁に送致されて、成人と同じ刑事手続きが行われる)された事件を除いては、法律で定められた罰則規定にそって処分されることはありません。
少年事件では、家庭裁判所に送致後、一定の調査期間を経て審判が開かれ、そこで少年の保護処分が決定します。
審判では、成人事件での刑事裁判と同じく、裁判官によって処分が言い渡されます。
審判で、少年は、事件の内容についても主張する事ができます。
冤罪を主張する場合は、審判に検察官が参加し、その検察官と少年の意見を主張する付添人(弁護士)との争いになります。
その場合、通常なら1回で終わる審判が複数回に及ぶこともあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件を専門に扱う法律事務所です。
奈良県大和郡山市の盗品等無償譲受け事件でお困りの方、少年事件の冤罪を晴らす弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご家族が逮捕された場合に弁護士を派遣する初回接見、初回無料での対応となる法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
強盗罪で執行猶予判決②
強盗罪で執行猶予判決②
強盗罪で執行猶予となる場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
前回の続きです。
~事例~
奈良県生駒市に住むAは、あるとき道を歩いていた男性を刃物で脅して現金を奪い取るという強盗事件を起こしてしまいました。
しかし、家に帰ったAはとんでもないことをしてしまった怖くなり、その日のうちに奈良県生駒警察署に自首することにしました。
自首する前に、Aは刑事事件に強い弁護士の見解を聞こうと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
今回の事例で考えられる刑の減軽の種類
前回のコラムでは、刑の減軽がなされた場合にどのような方法で減軽されるかに着目しました。
今回は、強盗罪の上記事例において、どのような場面で刑の減軽がなされる可能性があるのかを見ていこうと思います。
まず、Aは自首しています。
自首
自首をすれば刑が軽くなる、ということはイメージしやすいかと思いますが、自首にも要件があり、成立しない場合もあります。
自首は刑法第42条に規定されています。
刑法第42条第1項
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽するころができる。」
自首は捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告しなければならず、取り調べ中や職務質問中の自白については自首とは言えません。
さらに、すでに犯罪の容疑をかけられているような場合には自首が成立しない可能性があり、捜査機関に発覚したあとに捜査機関に出向いて自らの犯罪を自白した場合には出頭とされます。
自首が成立した場合でも、「減軽することができる」とされているとおり、必ず刑が減軽されるというわけではなく、裁量的に減軽される可能性があるということになりますので、自首による刑の減軽を求める場合には、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することをおすすめします。
情状酌量の余地がある場合
次に、今回の事例で刑が減軽される場合として酌量減軽が挙げられます。
酌量減軽
刑法第66条
「犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。」
情状に酌量すべきものがあれば減軽される可能性があります。
具体的には、犯行態様が悪質でない場合や被害者との示談が成立した場合などが挙げられます。
特に被害者との示談成立は重要な情状となります。
また、もしも起訴されてしまう前に被害者との示談が成立していれば、不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
そのため、少しでも示談成立の可能性を高めたいという場合には、事件の早い段階で示談交渉に強い弁護士に相談した方がよいでしょう。
今回は強盗罪の事例で代表的な刑の減軽事由を検討しましたが、このほかにも、刑法第43条に規定されている未遂や刑法第39条2項心神耗弱などの刑の減軽事由があります。
具体的事例において、刑の減軽の可能性があるかどうかについては専門的な知識や経験が必要となってきます。
そのため、刑事事件でお困りの際には、刑事事件に強い弁護士にできるだけ早く依頼した方がよいでしょう。
刑事事件に強い弁護士であれば、刑の減軽事由がある場合に効果的に主張していき、執行猶予判決の獲得に近づくことはもちろん、情状酌量や不起訴を目指した示談交渉についても安心してお任せいただくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
刑事事件では、早めの対応が後悔のない事件解説へとつながっていきますので、お悩みの場合は一度お電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
強盗罪で執行猶予判決①
強盗罪で執行猶予判決①
強盗罪で執行猶予となる場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県生駒市に住むAは、あるとき道を歩いていた男性を刃物で脅して現金を奪い取るという強盗事件を起こしてしまいました。
しかし、家に帰ったAはとんでもないことをしてしまった怖くなり、その日のうちに奈良県生駒警察署に自首することにしました。
自首する前に、Aは刑事事件に強い弁護士の見解を聞こうと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
~強盗罪~
強盗罪は刑法第236条に規定されています。
第236条第1項
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」
強盗罪には、「5年以上の有期懲役」という非常に重い罰則が規定されています。
5年以上の有期懲役ということは、そのままでは執行猶予判決の可能性はないということになってしまいます。
執行猶予については、刑法第25条に「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言い渡しを受けたときに刑の全部の執行猶予の可能性があると規定されています。
では、今回の事例のように「5年以上の有期懲役」が法定されている強盗罪では、執行猶予判決となることはないのかというと、そうではありません。
刑の減軽がなされると、今回の強盗罪のように「5年以上の有期懲役」と法定されている場合でも執行猶予の可能性がある「3年以下の懲役」が言い渡されることもあるのです。
刑の減軽の方法
法律上の刑の減軽事由がある場合の減軽の方法については、刑法第68条に規定されています。
第68条
法律上刑を減軽すべき1個又は2個以上の事由があるときは、次の例による。
1.死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は10年以上の懲役若しくは禁錮とする。
2.無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、7年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
3.有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる。
4.罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の2分の1を減ずる。
5.拘留を減軽するときは、その長期の2分の1を減ずる。
6.科料を減軽するときは、その多額の2分の1を減ずる。
では、今回のAのように、強盗罪で裁判となってしまった場合に刑の減軽事由が一つあった場合についてあてはめてみましょう。
まず、強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」となっておりますので、刑法第68条3号の「有期の懲役」の場合となります。
そして、「その長期及び短期の2分の1を減ずる」とあります。
刑法第12条に有期懲役は「1月以上20年以下」とするとありますので、条文上に「5年以上の有期懲役」とある強盗罪の有期懲役刑の範囲は「5年以上20年以下の懲役」ということになります。
この長期及び短期の2分の1を減ずるとありますので、刑の減軽がなされた場合、その言い渡しは「2年6月以上10年以下」の範囲での懲役刑ということになります。
このように刑の減軽がなされると、「5年以上の有期懲役」が法定されている強盗罪でも、「3年以下の懲役」の言い渡しを受ける可能性があり、執行猶予の獲得は不可能ではないのです。
ただ、実際に刑の減軽がなされる場合は法律に規定されています。
次週は同じ事例で考えられる刑の減軽事由について見ていきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
逮捕されてもすぐには面会できない
逮捕されてもすぐには面会できない
逮捕された際の一般面会について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは、妻と大学生の息子(21歳)と3人で暮らしていました。
あるとき、奈良県奈良西警察署から電話があり、「息子さんを振り込め詐欺の疑いで逮捕しました。」と言われました。
Aは、すぐにでも息子から話を聞きたいと思いましたが、警察からは「捜査中なので面会はできない」と言われてしまいました。
そこで、Aは刑事事件人強い弁護士の初回接見サービスを利用し、息子の様子を知ろうと考えました。
(この事例はフィクションです。)
振り込め詐欺事件
振り込め詐欺関連の事件は、組織的に行われていることがほとんどです。
そのため、いわゆる受け子や出し子と呼ばれるような末端の役割には、アルバイト感覚で未成年者や今回の事例のような大学生が犯行に加担してしまうことがあります。
実際にSNS等で高額バイトや闇バイトなどで募集されていることもあります。
一般面会は逮捕後すぐにはできない
ご家族が逮捕されてしまった場合、残された家族は一刻も早く面会したいと考えるかと思います。
しかし、逮捕されてから勾留が決定するまでの最大72時間については、手続きに時間制限があることもあって、一般の方が面会できることはほとんどありません。
このようなときは、すぐに刑事事件に強い弁護士に接見を依頼するようにしましょう。
弁護士であればこの72時間のうちであっても接見することが可能なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスでは、お電話でお手続きいただき、最短即日に弁護士を派遣することが可能です。
そして、この初回接見サービスでは、ご依頼いただいた方の伝言をお届けすることができます。
刑事事件は、ほとんどの方が初めての経験となりますので、逮捕されている方は非常に不安を感じておられます。
そんなときに、ご家族等が派遣してくれた弁護士から励ましの伝言などをもらうことができれば、励みになることは間違いないでしょう。
接見等禁止
勾留が決定してからは、一般の方でも面会が可能となりますが、勾留決定時に接見等禁止決定がだされてしまうと、ご家族でも面会できなくなってしまいます。
今回の事例の振り込め詐欺のように組織的な犯罪で、共犯者がいるような場合は、接見等禁止決定がなされてしまう可能性が高くなります。
これは、共犯者が多数いると思われる組織的な犯罪では、共犯者同士の口裏合わせが行われてしまう可能性があるからです。
接見等禁止決定については刑事訴訟法第81条に規定があります。
第81条
「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。」
上記のように、勾留された際に「第39条第1項に規定する者=弁護人又は弁護人になろうとする者」以外との接見等を禁止されてしまうことがあります。
これが接見等禁止決定です。
この接見等禁止決定がなされてしまうと、たとえ家族であっても面会することができなくなってしまうのです。
弁護士はこの接見等禁止決定に対して一部解除を申し立てることでなんとかご家族と勾留されている本人が面会できるように活動することができます。
弁護士が、両親は事件には関係ないということをしっかりと主張し、事件の話をしないことや証拠隠滅をしないことをしっかりと約束することで接見等禁止決定の一部が解除され、ご家族だけでも面会が認められる可能性があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
業務上横領罪で自首
業務上横領罪で自首
業務上横領罪で自首をお考えの場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県香芝市の会社に勤めるAは、会社で経理を担当していました。
Aは数年前から帳簿を改ざんし、自身の懐に合計500万円を着服していました。
あるとき、同じ額の業務上横領罪で起訴された人が実刑判決を受けた例もあると知り、Aはこのままでは発覚すると刑務所に行くことになってしまうかもしれないと不安を抱くようになりました。
不安で眠れぬ夜を過ごしていたAは、いっそ自首しようかと考え、自首に対応している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
業務上横領罪
業務上横領罪は刑法253条に規定されており、業務上自己の占有する他人の物を横領することによって成立します。
刑法253条
「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」
業務上横領罪における「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う、委託を受けて他人の物を占有・保管することを内容とする事務であるとされています。
今回Aは、経理係という地位に基づいて会社のお金を管理保管する事務に就いているので、業務上横領罪における業務に該当するでしょう。
そして、「自己の占有する他人の物」である会社のお金について、帳簿を改ざんして着服したことは「横領」したといえるでしょう。
では、今回のAが検討している自首とは何なのか、自首をすればどうなるかをみてみましょう。
自首の要件
自首をすれば刑が軽くなる、ということはイメージしやすいかと思いますが、自首にも要件があり、成立しない場合もあります。
自首は刑法第42条に規定されています。
刑法第42条第1項
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽するころができる。」
自首は捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告しなければならず、取り調べ中や職務質問中の自白については自首とは言えません。
さらに、すでに犯罪の容疑をかけられているような場合には自首が成立しない可能性があり、捜査機関に発覚したあとに捜査機関に出向いて自らの犯罪を自白した場合には出頭とされます。
自首の効果
自首をした場合、必ず罪が軽くなるというわけではありません。
「減軽することができる」とされているとおり、任意的に減軽される可能性があります。
減軽される場合も刑法第68条に規定されており、例えば今回の事例の業務上横領罪であれば「10年以下の懲役」というところ「有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる」とされているので刑の減軽が認められれば、「5年以下の懲役」の範囲で処断されることとなります。
自首は自分の罪を申告すれば当然に成立するというわけではありません。
また、数年をかけての業務上横領罪では、すでに時効を迎えている部分がある可能性もあります。
そこでしっかりと刑事事件に強い弁護士に相談することが必要です。
特に、業務上横領罪で自首を検討する場合、会社側に報告するタイミングも相談が必要でしょう。
業務上横領事件では、会社側に報告し、被害金を弁償して示談することで、刑事事件化することなく事件を終了することができる可能性もあります。
もしも、捜査機関に発覚していない業務上横領罪やその他刑事事件で今後どうなってしまうのか不安だという場合や自首を検討しているという場合には、一度無料法律相談に来てみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約は0120-631-881で24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
ペットの持ち去りで窃盗罪
ペットの持ち去りで窃盗罪
ペットを持ち去った場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県大和高田市に住むAは、自宅近くの公園を散歩しているときに一匹の犬を見つけました。
その犬は、飼い主がトイレを利用するため、一時的に公園の柵にリードで括り付けられていました。
トイレを終えて出てきた飼い主が犬を探していると、公園の利用者が、Aが犬を持ち去るのを見たと言っていました。
犬が連れ去られたと聞いた飼い主は、奈良県高田警察署に通報しました。
捜査により、Aが犬を持ち去ったことが判明し、Aは奈良県高田警察署から呼び出しを受けることになりました。
取調べに対して不安になったAは、刑事事件に強い弁護士に相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
ペットの持ち去りは窃盗罪
ペットを持ち去った場合には、どのような罪になってしまうのでしょうか。
刑法上、動物は物として扱われ、傷つけた場合には器物損壊罪が成立します。(動物愛護法など特別法は除く。)
そのため、動物を持ち去ったという場合には、他人の物を持ち去ったということで、窃盗罪が成立することになるでしょう。
では、窃盗罪の条文をみてみましょう。
刑法第235条
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」
動物は、窃盗罪における財物にも含まれるとされているので、今回の事例のAにも窃盗罪が成立することになるでしょう。
今回の事例では、トイレに行くわずかな間だけでしたので、飼い主に占有があったと考えられます。
もしも、逃げ出したペットなどペットに対して飼い主の占有が及んでいなかったと判断されたとしても、持ち去ってしまった場合には、遺失物等横領罪が成立する可能性はありますので、注意が必要です。
なお、Aがペットを持ち去った後に、身代金要求のようなことをすれば、身代金目的誘拐罪などは成立せず、恐喝罪となる可能性が高いでしょう。
弁護活動
通常、窃盗罪の弁護活動としては、被害者に対して示談交渉を行い、被害弁償を行っていくことが考えられます。
しかし、今回の事例のようなペットの持ち去りによる窃盗事件では、ペットがきちんと被害者の下へ帰るかどうか、帰った後に被害を弁償するとしてその算出など、示談交渉をしていくにも通常の窃盗罪よりも複雑になることが予想されます。
また、ペットを持ち去られたということで、被害者の処罰感情も大きくなっていることが予想されます。
このように複雑で困難となってしまうことが予想される示談交渉には、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
示談交渉においては、まったく同じ状況ということはありえませんので、状況によって適切な交渉をしていくことが大切です。
そして、適切な示談交渉を行っていくためには、何よりも経験が大切になってきます。
被害者の存在する刑事事件では、示談交渉が最も重要な弁護活動となりますので、刑事事件に強い弁護士であれば示談交渉の経験が豊富にあります。
そのため、刑事事件に強い弁護士であれば、安心して示談交渉をお任せいただくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
今回の事例のように、警察に呼び出しを受けたという場合には、初回無料での対応となる法律相談にお越しください。
そして、ご家族が逮捕されたという場合には刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
準詐欺罪で逮捕
準詐欺罪で逮捕
準詐欺罪での逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
リフォーム業者をしているAは、仕事を通じて知り合った奈良県天理市に住む女性が認知症であることを知りました。
Aは、その女性の判断能力が低下していることに乗じて贈与契約書を書かせ、それを利用して約3千万円を自分の会社に送金させました。
後日、女性の家族が送金に気づいて不審に思い、奈良県天理警察署に相談したところ、Aの行為が発覚しました。
その後、Aは奈良県天理警察署に準詐欺罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたことを聞いたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
~準詐欺罪~
詐欺罪は、人をだまして財物や利益を得ることによって成立する犯罪です。
そのため、詐欺罪といえば人をだます犯罪、というイメージを抱いている方も多いでしょう。
しかし、今回のAは女性をだましているというわけではなく、女性が認知症であることに乗じて契約書を書かせ、お金を送金させているので、詐欺罪ではなく準詐欺罪での逮捕となりました。
刑法248条(準詐欺罪)
「未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。」
心神耗弱とは、簡単に言えば、判断能力が著しく低下していることを指します。
つまり、準詐欺罪の成立にはだますという行為は必要なく、相手の判断能力の著しい低下を利用して財物や利益を得ることによって準詐欺罪が成立するということになります。
今回の事例の被害女性のように、認知症を患っている場合なども心神耗弱であると判断されるでしょう。
~弁護活動~
準詐欺罪であっても罰則は詐欺罪と同じ「10年以下の懲役」が規定されています。
罰金刑の規定がないことから、略式手続による罰金刑となることはないので、起訴されてしまうと刑事裁判を受けることになってしまいます。
今回の事例の被害額は、3千万円と非常に高額になっていますので、一件だけであっても執行猶予が付かず実刑判決を受ける可能性もあります。
そのため、被害者への被害弁償を行うなど弁護士の弁護活動によって執行猶予判決を受ける可能性高めるようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っておりますので、事務所として刑事裁判の経験も豊富にあります。
全国13支部でさまざまな事件に対応してきた実績がありますので、安心して裁判をお任せいただくことができます。
また、今回の事例のように逮捕されている場合、身体解放に向けた活動も重要となってきます。
刑事事件に強い弁護士は、起訴前の段階から身体解放活動を行っていくことができますし、起訴前の解放が叶わなかったとしても起訴されればすぐに保釈に向けた活動を行っていき、最短での身体解放を目指していきます。
実刑が予想される事件こそ、刑事事件に強い弁護士への依頼をご検討ください。
また、準詐欺罪を含む刑事事件で刑事裁判を受け、結果が出た後であっても控訴審から対応することも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が初回無料での対応となる法律相談、お電話での受付で弁護士を派遣する初回接見サービスを行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて専門スタッフが24時間体制で受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
特に、ご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けた際には、すぐに弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
万引きは窃盗罪
万引きは窃盗罪
万引きでの窃盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住む主婦のA子はいつも訪れるスーパーマーケットで店員の目を盗んで、商品を自身のエコバッグに入れて万引きしていました。
一度発覚してしまったこともあったA子でしたが、そのときは誠心誠意謝って弁償することで、警察には通報されませんでした。
そのため、A子はばれても弁償して謝れば許してもらえる、と間違った認識を持ってしまっていました。
あるとき、いつものようにA子が商品をエコバッグに入れて万引きしようとしたところ、店員に呼び止められて奈良県奈良警察署に通報されてしまいました。
A子は駆け付けた奈良県奈良警察署の警察官に連行され、取調べを受けることになってしまいました。
逮捕はされず、ひとまず安心していたA子でしたが、しばらくして奈良県奈良警察署の警察官から連絡があり、「書類送検する。」と言われました。
書類送検という言葉に不安となり、今後どのようになってしまうのか不安になったA子は、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
万引き
レジ袋が有料化されたことなどから、最近ではエコバッグを持っての買い物が一般的に広がっています。
しかし、エコバッグの普及に伴ってそのエコバッグを利用した万引き事件も増えてきているようです。
万引き、というと子どものいたずらのような印象を受けてしまうかもしれませんが、みなさんご存知のように、万引きは立派な窃盗罪です。
窃盗罪
窃盗罪は刑法第235条に規定されています。
刑法第235条
「他人の財物を窃取した者は窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
万引きも窃盗罪になりますので、条文にあるように「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の範囲で刑罰が科される可能性があります。
書類送検
万引きによる窃盗罪を含む刑事事件は、警察での捜査が終わった後、検察へ送致されます。
なお、今回の事例のA子が一回目に万引き事件を起こしたときのように、店側への謝罪と賠償によって刑事事件化しない場合もありますし、警察に通報されて刑事事件化したとしても微罪処分など、警察段階で終了する事件もあります。
検察へ送致された場合は、検察官がその事件を不起訴にするのか、略式手続きによる罰金とするのか、または起訴して刑事裁判にするのかを判断します。
今回の事例のA子のように、逮捕や勾留といった身体拘束を伴わない、いわゆる在宅事件の場合、検察への送致は事件に関する書類のみが送られます。
このことから、在宅事件で検察へ事件が送致されることを一般的に書類送検と言います。
在宅事件の進行は見えにくい
在宅事件として進められている事件では、ある日突然書類送検されると伝えられるということも往々にしてあります。
検察官から連絡があり、自分が書類送検されていたとそこで初めて知った、というケースも見られます。
在宅捜査の場合、逮捕や勾留を伴って進められる刑事事件と違い、明確な時間制限があるわけではないため、事件の進捗が当事者であっても分かりづらくなってしまいます。
しかし、書類送検されてそのまま放置してしまえば、自分の知らないうちに処分の見込みが決まってしまっていたということになりかねません。
そのため、刑事事件を起こしてしまったら、書類送検される前にどのような処分が見込まれるのか、これからどうした弁護活動が可能なのか、すぐに弁護士に相談されることをおすすめします。
特に、万引きの被害店舗に被害弁償できていないという場合は、書類送検されてからでも遅くないので、弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が初回無料法律相談を行っています。
万引き事件を起こしてしまったという方、書類送検をされてしまったという方は遠慮なく弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談をご利用ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
執行猶予中の犯罪
執行猶予中の犯罪
執行猶予中の犯罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県桜井市に住むAは、2年前に詐欺事件を起こしてしまい、「懲役3年執行猶予5年」の有罪判決を受けていました。
その後は穏やかに暮らしていたAでしたが、あるとき出来心からコンビニエンスストアで万引きをしてしまいました。
Aの犯行は店員に発覚してしまい、通報され、奈良県桜井警察署の警察官が駆け付けました。
その後Aは、奈良県桜井警察署で取調べを受けることになりましたが、このままでは執行猶予が取り消されてしまい、刑務所に行かなければならないのかと不安になりました。
そこでAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
執行猶予中の再犯について
刑の全部の執行猶予は刑法第25条に規定されています。
刑の全部の執行猶予は、
「前に禁錮以上の刑に処せられたことのない者」
若しくは、
「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又は免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者」
が
「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」
の言渡しを受けたとき、
「情状により裁判確定の日から1年以上5年以下の期間その刑の執行を免除される」
というものです。
今回のAは、2年前に「懲役3年の言渡しを受けていますが、5年の期間その執行を猶予されている状態」、ということになります。
このような執行猶予中に再犯をしてしまうと、執行猶予は必ず取り消されてしまうのでしょうか。
刑の全部の執行猶予が取り消される場合
執行猶予中に罪を犯した場合に刑の全部の執行猶予が取り消される場合は
1.猶予の期間内にさらに罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき(刑法第26条第1号)
2.猶予の期間内にさらに罪を犯し、罰金に処せられたとき。(刑法第26条の2第1号)
が考えられます。
1については、必要的取消であり、必ず執行猶予が取り消されてしまいます。
2は裁量的取消であるとされており、裁判官の判断で取り消されてしまう可能性があります。
今回のAは、「懲役3年執行猶予5年」の執行猶予期間に「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」である窃盗罪を犯してしまいました。
例えば、今回の窃盗罪で「懲役2年」という言渡しを受けてしまい、執行猶予が取り消されると前回の懲役3年と合わせて5年間刑務所に行かなければならなくなるのです。
執行猶予が取り消されないために
執行猶予中に犯罪をしてしまった場合でも必ず執行猶予が取り消されて刑務所に行かなければならないわけではありません。
執行猶予が取り消されないための活動として、被害者の方と示談を締結するなどして不起訴処分を目指していく方法が考えられます。
もしも、起訴されてしまうという場合でも、検察官に意見書を提出するなどの活動によって懲役刑ではなく、罰金刑を求めていきます。
前述のように罰金刑であれば、執行猶予が必ず取り消されるというわけではなくなります。
これらの活動は刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士であれば、被害者との示談交渉、検察官との処分交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せいただくことができます。
そして、公判請求されてしまったとしても、まだ望みを捨ててはいけません。
再度の執行猶予
執行猶予中に犯罪をしてしまい、起訴されて公判請求となり、裁判を受けるという段階になっても、まだ執行猶予が取り消されるとは限りません。
執行猶予中にしてしまった犯罪についてもう一度執行猶予判決を受ける可能性が残されています。
執行猶予中の犯罪について執行猶予判決を受けることを再度の執行猶予といいます。
刑法第25条第2項には、
「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者」
が、
「1年以下の懲役又は禁錮の言渡し」
を受け、
「情状に特に酌量すべきものがあるとき」
は刑の全部の執行を猶予することができる
と規定しています。
(ただし、保護観察付執行猶予であった者は除く)
すなわち今回のAが起訴されて裁判となってしまった場合でも、「懲役1年以下」の言渡しであり、情状に酌量すべきものがあれば、再度の執行猶予を獲得できる可能性があるのです。
再度の執行猶予を獲得できれば、執行猶予が取り消される場合の1「猶予の期間内にさらに罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき」ではなくなるのです。
ただ、この再度の執行猶予獲得を目指していくには、情状面で有効なアピールをしていくなど適切な弁護活動が必要となりますので、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
このように、執行猶予中に罪を犯してしまっても、必ず執行猶予が取り消されてしまうというわけではありません。
執行猶予中に罪を犯してしまった場合でも、実刑を回避できることもありますので、一度刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間体制で無料法律相談、初回接見のご予約をお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
刑事事件はスピードが命、なのはなぜか
刑事事件はスピードが命、なのはなぜか
刑事事件の流れについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは、妻と大学生になる息子(22歳)と三人で暮らしていました。
あるとき、遊びに出ていた息子が帰って来ず心配していたところ、奈良県奈良警察署から連絡を受けました。
警察官から、息子さんを詐欺の疑いで逮捕しました、と聞かされたAは弁護士を探すことにしました。
すると、さまざまなところで「刑事事件はスピードが命」、「刑事事件はスピード勝負」といった内容を目にしました。
焦ったAは、刑事事件に強いという弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
刑事事件の流れ
刑事事件についてインターネットで検索したりすると「刑事事件はスピードが命」、「スピード勝負」といった言葉をよく目にします。
刑事事件でスピードが大切だと言われているのは、なぜなのでしょうか。
これは刑事事件の、特に身体拘束を受けている事件については、手続きや身体拘束の期間について明確に時間が決められていることが関係しています。
今回は警察に逮捕されてから起訴されるまでの事件の流れについて時系列順に弁護士ができることを交えてご紹介します。
逮捕~48時間
警察官に逮捕された場合、警察官は48時間以内に検察官に事件を送致しなければなりません。(刑事訴訟法第203条第1項)
※弁護士は
弁護士は検察官に送致せず、釈放するよう求めることができます。
検察官に送致せず釈放という可能性もあるのです。
送致~24時間
検察官は、警察から送致されてきた事件について、24時間以内に裁判所に対して身体拘束の継続である勾留を請求するかどうか判断し、請求しない場合は釈放しなければなりません。(刑事訴訟法第205条)
勾留が請求された場合には、裁判官が勾留を決定するかどうかを判断します。(刑事訴訟法第207条)
※弁護士は
検察官に対して勾留を請求しないように、裁判官に対して勾留請求を却下すように働きかけていくことができます。
勾留決定後
上記までの手続きで勾留が決定されてしまった場合、通常10日間身体拘束を受けることになり、最大でさらに10日間の延長が認められています。
勾留の満期になると、検察官は起訴しない場合、不起訴や処分保留で釈放しなくてはなりません。(刑事訴訟法第208条)
なお、起訴されてしまった場合には起訴後勾留となります。
※弁護士は
勾留決定に対して準抗告という不服申し立てを行うことができます。
準抗告が認容されると、釈放されることになります。
また、勾留期間中に示談等適切な弁護活動を行い、検察官と交渉していくことで不起訴処分を目指して活動していきます。
逮捕、勾留されている事件であっても最終的に不起訴処分を獲得することも十分に可能なのです。
これまで、逮捕から起訴までの簡単な流れを見てきましたが、身体拘束を受けているいわゆる身柄事件での逮捕されてから起訴までの期間は基本的には、最大でも23日間となっていることがわかります。
弁護士ができることも記載しましたが、勾留が決定をした後は勾留決定に対する準抗告(不服申し立て)はできますが、勾留を決定されないようにする活動はできなくなりますし、起訴されてしまった後は不起訴処分に向けた活動はできません。
このように刑事事件で最大限の弁護活動を行おうと思うならば、できるだけ早い期間から弁護士に依頼しなければなりません。
そのため、刑事事件ではスピードが命、スピード勝負だと言われているのです。
もちろん、少し時間が経ってしまっているからといって遅すぎるということはありません。
まずは一度、お問い合わせください。
今できることをし、少しでも早く対応していくことが後悔のない事件解決へとつながっていきます。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話を。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。