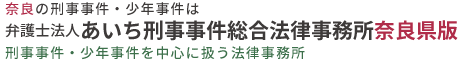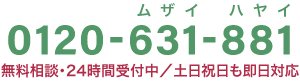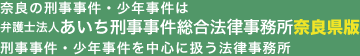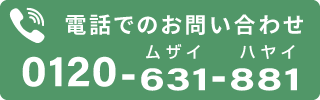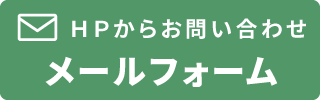大学4年生になる子供が万引き事件を起こし、警察署から呼び出しを受けた事例②

前回のコラムに引き続き、万引き事件を起こし、警察署から呼び出しを受けた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良市に住むAさんは今年の春4年生になる大学生です。
年末年始で浮かれていたAさんは気が大きくなり、ついお店の商品を万引きしてしまいました。
冬休みも空け、いつも通り大学で講義を受けていたAさんの下に、奈良県奈良警察署の警察官から電話がありました。
奈良県奈良警察署から出頭するように言われたAさんは、明日出頭しますと返答しました。
帰宅後、Aさんはすぐさま母親に万引きしてしまったこと、奈良県奈良警察署から呼び出しを受け明日出頭することを伝えました。
あまりのことに驚いたAさんの母親は警察署から呼び出しを受けた場合にどのようにすればいいのかインターネットで検索をし、すぐに弁護士に相談をすることに決めました。
(事例はフィクションです。)
窃盗罪と前科
前回のコラムで解説したように、万引きを行うと窃盗罪が成立する可能性があります。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。(刑法第235条)
窃盗罪で有罪になった場合には、罰金刑で済んだり執行猶予付き判決を獲得できた場合であっても、前科が付いてしまうことになります。
事例のAさんは今年の春に大学4年生になるようです。
大学4年生となると就職や進学など卒業後の進路を決定する大事な時期になります。
Aさんが窃盗罪で有罪になり、前科が付いてしまうと、就職活動などAさんの今後の進路に悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。
前科を避けたい
刑事事件では、不起訴処分という処分があります。
この処分は起訴しない処分のことをいい、不起訴処分を獲得することができれば刑罰は科されませんので、前科が付くことはありません。
ですので、前科が付くことを避ける場合には、不起訴処分に向けた弁護活動が重要になってきます。
不起訴処分に向けた弁護活動の一つとして、取調べ対策が挙げられます。
取調べでは、供述した内容を基に供述調書が作成されます。
供述調書は重要な証拠となり、作成後に内容を訂正することは容易ではありませんから、被疑者の意に反していたり、被疑者にとって不利な内容の供述調書が作成されることを防ぐことがとても重要になります。
例えば、今回の事例の被害店舗で万引きが多発していたり、近隣の店舗でも被害が相次いでいた場合には、やっていない万引き事件についてもAさんがやったと認めるように強要してくるかもしれません。
当然、やっていないわけですから、Aさんは否認をするかと思いますが、否認を続けることは体力的にも精神的にもしんどく、やっていないことも自分がやったのだと認めてしまう可能性があります。
繰り返しになりますが、一度不利な内容の供述調書が作成されてしまうと、後から訂正することは容易ではありません。
ですので、捜査官の誘導に乗らない、やっていないことを認めてしまわないことが重要です。
威圧的な取調べなどによって自白を強要されている場合には、弁護士から捜査機関へ抗議を行うことで取調べの環境を改善できる可能性があります。
現在、不当な取調べなどでお困りの方は、すぐに弁護士に相談をすることをおすすめします。
また、弁護士と取調べ対策を行い供述内容をあらかじめ整理しておくことで、心にゆとりをもった状態で取調べに臨める可能性がありますから、取調べを受ける前には弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
現在、不当な取調べを受けている方、これから取調べを受ける方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。