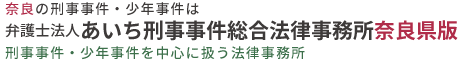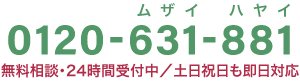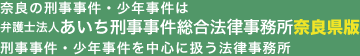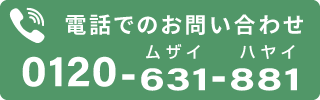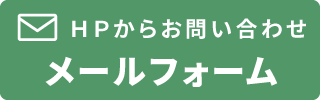Archive for the ‘財産犯’ Category
ATMからお金を持ち去り取調べ
ATMからお金を持ち去り取調べ
ATMからのお金の持ち去りについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県生駒郡斑鳩町に住む主婦のA子は、あるとき、銀行にお金をおろしに行きました。
するとA子の使おうとしたATMに誰かが取り忘れたお金が残っており、A子はそのお金を抜き取って持ち帰ってしまいました。
後日、奈良県西和警察署の警察官がA子の自宅を訪れ、「ATMからお金を持ち去った件で話が聞きたい」とA子は取調べを受けることになりました。
防犯カメラにもしっかりと持ち去る様子が映っており、どのように対処してよいか分からなくなったA子は刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
今回の事例では、A子はATMに残された現金を持ち去っています。
この場合に考えられる罪としては、窃盗や遺失物横領、占有離脱物横領が考えられます。
窃盗
第235条
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
遺失物等横領
第254条
「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」
窃盗か遺失物等横領か
前の利用客がATMに置き忘れたお金を持ち去ってしまった場合、基本的には窃盗罪となります。
物を持ち帰ったりした場合には、占有があるかどうかによって窃盗罪となるか遺失物横領罪若しくは占有離脱物横領罪となるか判断されます。
持ち主の占有があったかどうかの判断については、置き忘れた持ち主が気付いて戻ってきたか、その時間や離れた距離、警察署に被害を申告するまでの時間などさまざまな要素から判断されることになります。
しかし、ATMの場合、店舗が管理している場合も多く、店側の占有が認められれば、これも窃盗となるので、ATMのお金を持ち去ると窃盗罪となってしまう可能性は高くなります。
ただ、細かな状況によって変わってくるので、詳しくは専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
また、警察から罪名を言われているような場合でも、その後の捜査によって、検察官に事件が送られる際や起訴される際に罪名が変更されるということもありますので、注意が必要です。
窃盗と遺失物等横領の罰則を見てみると「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(窃盗)「2年以下の懲役又は10万円以下の罰金」(遺失物等横領)となっています。
比べてみると窃盗の方が重いことが分かりますが、これは、一概に遺失物等横領になったほうがよいというものではありません。
これは、罰金額の上限が関係してきます。
例えば、以前に遺失物等横領で10万円の罰金となって前科がある方が、再度置き引きをしてしまった場合、その置き引きが窃盗罪にあたるのであれば10万円より多額の罰金刑となる可能性がありますが、再度、遺失物等横領罪にあたるのであれば、より多額の罰金刑を科すことができないので、懲役刑となる可能性が高くなってしまいます。
もちろん、これは示談の有無やその他の活動のよっても変わってきますので、弁護士の無料法律相談に行くようにしましょう。
逮捕されてない事件ほど弁護士を
今回のA子は捜査され、取調べを受けていますが、逮捕されてはいません。
いわゆる在宅事件として、身体拘束を受けずに捜査されていくことになりますので、起訴されて裁判となるまでは国選弁護人は付かないことになります。
それでも不起訴や、処分の軽減を求めていくのであれば、示談交渉などの弁護活動を行っていく必要はあります。
特に重要となる示談交渉については、逆恨みなどをおそれて加害者本人と連絡を取りたくないという方もいますので、連絡先すら分からない状況も考えられます。
そのような状況であっても弁護士を選任することで、被害者の方も安心して示談交渉に応じてくれることもありますので、まずは、無料法律相談にお越し下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談では、今後の見通しや取調べのアドバイスなども行うことができます。
ご予約は0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
強盗強姦罪から強盗・強制性交等罪へ
強盗強姦罪から強盗・強制性交等罪へ
強盗・強制性交等罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住むAは仕事の帰り道に好みの女性を見つけ、性交したいと思い、その女性が人気のない公園に入ったところで女性に襲い掛かりました。
女性は抵抗しましたが、Aは女性を殴り、恐怖で逃げられなくしてから性交しました。
その後、性交が終わってから、Aは女性のハンドバッグに金目の物があると考え、女性のバッグを奪おうとしましたが、女性がなかなかバッグを離さなかったため、Aは女性に足蹴りをして、女性のバッグを奪い逃走しました。
後日、近くの防犯カメラの映像などからAの犯行が特定され、Aは奈良県奈良警察署に強盗・強制性交等の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
強盗・強制性交等
第241条
「強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第179条第2項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は7年以上の懲役に処する。」
第2項「前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」
第3項「第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。」
強盗・強制性交等は、平成29年の刑法改正により、強盗強姦罪から改正されました。
刑法第179条で強姦罪から強制性交等罪へと改正された、というだけでなくより現実的な状況に則すように改正されています。
大きく変わった点としては、以前の強盗強姦罪では強盗犯人が強姦をした場合に「無期又は7年以上の懲役」と規定していましたが、強姦の後に強盗の犯意を生じて強盗をした場合には、強盗強姦罪は成立せず、強姦罪と強盗罪の併合罪であるとされていました。
この場合は「5年以上30年以下の有期懲役」となるので、無期が規定されている強盗強姦罪とは大きな差違がありました。
そこで改正により、同一機会に強盗若しくはその未遂、強制性交等若しくはその未遂が行われていた場合にはその順番にかかわらず、改正前の強盗強姦罪と同じ、「無期又は7年以上の有期懲役」で処罰されることになりました。
これは、どちらが先に行われたか不明の場合や両方に同時に着手した場合も含まれます。
強盗・強制性交の強盗には236条の強盗、238条の事後強盗、239条の昏酔強盗が含まれ、強制性交等には準強制性交等が含まれます。
初回接見
ご家族が逮捕されたという連絡を受けた場合、どのようにすればよいか分からないことかと思います。
しかし、刑事事件では逮捕されてからの活動にはスピードが求められ、迅速な対応が早期の釈放、事件解決につながります。
その活動のはじめとして、初回接見サービスがあります。
初回接見サービスでは弁護士が身体拘束を受けているご本人の下へ向かい、取調べのアドバイスや今後の見通しをお伝えし、ご家族にご報告いたします。
取調べの相手はいわばプロとなりますので、何も知らないままに取調べを受けてしまうと知らないうちに不利な証拠を取られてしまうかもしれませんので、初回接見による弁護士のアドバイスは必要でしょう。
そして、その後の弁護活動をご依頼いただくことになれば、すぐに、検察官や裁判官への意見書など、さまざまな身体解放に向けた活動を行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
万引きでも裁判員裁判
万引きでも裁判員裁判
裁判員裁判について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県北葛城郡に住むAは近くのスーパーマーケットで食料品を万引きしました。
そのまま店の外に向かおうとしたAでしたが、ガードマンが前に立ちふさがったため、Aはそのガードマンを殴り倒し、そのまま逃走しました。
しかし後日、防犯カメラの映像などからAの犯行が特定され、Aは強盗致傷の疑いで奈良県西和警察署に逮捕されることになってしまいました。
Aの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
事後強盗
第238条
「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」
事後強盗罪は、刑法第238条に規定されています。
窃盗の犯人が、
1.財物を得てこれを取り返されることを防ぐため
2.逮捕を免れるため
3.罪跡を隠滅するため
上記いずれかの目的のために相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行、脅迫をくわえることで、事後強盗罪は成立します。
事後強盗罪の主体となるのは窃盗犯人であるため、既遂か未遂かは問いませんが少なくとも窃盗の実行行為に着手していることが必要です。
また、暴行、脅迫については窃盗の機会または機会継続中に行われることが必要です。
事後強盗罪で起訴されて有罪が確定した場合、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」に処されることになります。
また、その暴行によって被害者が負傷してしまうと強盗致傷となってしまうのです。
裁判員裁判
裁判員裁判は、抽選で選ばれた一般市民が「裁判員」となって、裁判官と一緒に刑事被告人が有罪であるか否か、有罪であるとしてどれくらいの刑を課すべきかを決める制度です。
裁判員裁判の対象となる事件については、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項に定められています。
1号 死刑又は無期の懲役、禁錮に当たる罪に係る事件
2号 法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件
強盗致傷となった場合の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」(刑法第240条)ですから今回の事例で被害者が負傷していれば、1号に該当し、裁判員裁判対象事件ということになります。
裁判員裁判は、国民がもつ常識や感覚を裁判に反映させるとともに、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることが目的とされています。
しかし、裁判のプロではない一般の方が参加するわけですから、先入観や偏見などによって、偏った事実認定をされたり、不当に重い量刑となるおそれがあるという弊害も指摘されています。
実際に、裁判員裁判で出された死刑判決が、高裁で無期懲役となった裁判例などもあるくらいです。
さらに、裁判員裁判では公判前整理手続きが必ず必要になるなど通常とは異なった流れで裁判が進んでいくことになりますので、刑事事件を専門に扱う弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
弁護士の見解を聞く重要性
万引きをしたつもりしかなく、窃盗のつもりでも今回のAのように逮捕を免れるために暴行をしてしまうと、強盗と同じ罰条で処断されることになります。
さらにその結果、相手が負傷してしまうと強盗致傷となり、裁判員裁判にまで発展してしまいます。
刑事事件では、自分の行いが思っている罪と違う罪に当たるということは珍しくありません。
自分の行為がどのような罪になるか分からない時には、刑事事件に強い弁護士に意見を聞くようにしましょう。
今後の見通しやどのような罪が成立しうるのか、専門知識と経験のある弁護士だからこそ詳しくお伝えできるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では裁判員裁判にも強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
値札の貼り替えが詐欺罪に
値札の貼り替えが詐欺罪に
値札の貼り替えについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県天理市に住むAは、ある日、デパートの洋服売り場で洋服に付いていた値札を、別の洋服に付いていた安い値札と付け替えて、実際の販売価格の半額以下の値段で洋服などを購入しました。
後日、良心の呵責から自首しようと考えましたが、このままでは前科が付いてしまうと思ったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
詐欺罪
第246条
第1項「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」
第2項「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」
詐欺罪は、人を騙して財物の交付を受けることによって成立する犯罪です。
1.人を騙すという欺罔行為
2.その欺罔行為によって相手方が錯誤に陥る
3.その錯誤に基づいて相手が財物、又は財産上の利益を交付する
4.それを受け取る
5.詐欺罪となる
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」と罰金刑が規定されていないため、起訴されていまうと無罪判決を獲得しなければ、実刑か執行猶予ということになってしまいます。
事件の内容によっても変わりますが、弁護士は不起訴処分を目指して、示談交渉などの活動を行っていきます。
値札の付け替えは詐欺罪か
お店の商品を盗めば窃盗罪となりますが、今回の事件でAは、実際の販売価格より安いとはいえ、代金を支払っています。
この場合は、窃盗ではなく詐欺罪となる可能性があります。
上記の例に沿って当てはめてみると
1.安い金額の値札に付け替えて、商品をレジの店員に渡すことが、詐欺罪における欺罔行為だとする
2.その値札を受け取った店員が錯誤に陥る
3.実際の販売価格よりも安い金額で洋服をAに交付する
4.それを受け取る
5.詐欺罪が成立する
Aのように、値札を付け替えて実際の販売価格よりも安い値段で商品を購入する他、他の見切り品に付いていた半額シールを、定価で販売している商品に付け替えて購入したり、不正にスタンプを押してポイントを貯めたポイントカードを店員に提示して、割引価格で商品を購入したりといった場合も、詐欺罪が適用される可能性が高いです。
警察未介入事件
今回の事例のように警察にまだ発覚していないような場合には、しっかりと被害者と示談交渉をすることで、被害届を出さない旨の条項を入れた示談書を締結すれば、刑事事件化することを防ぎ、前科を回避することができるでしょう。
間に第三者である弁護士をいれることで、無用な言い争い等は避けることができますし、早期に示談が結べる可能性もあります。
ただ、示談交渉の中でも、警察未介入事件での刑事事件化阻止に向けた示談交渉は難しいものとなります。
被害者は、事件を起こした加害者に対して刑事罰を望んでいる場合も多いからです。
そんな中で、被害の弁償などによって被害者や会社に納得してもらい、刑事事件化を阻止していくのは、示談交渉に強い弁護士でなければ難しいことだと言えるでしょう。
警察未介入のまま事件を収束することができれば、前科、前歴ともにつかないことになるので、詐欺事件を起こしてしまって前科や前歴、刑事事件化が不安である場合には、すぐに弁護士に相談し、示談交渉に取り掛かってもらうことも必要となってくるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、詐欺罪に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
奈良県天理市を含む奈良県天理警察署の管轄地域での弁護活動も行っております。
まずはご予約から、フリーダイヤル0120-631-881にてお待ちしておりますのでお気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
レンタカーの横領事件
レンタカーの横領事件
横領事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市在住のフリーターAさん(30歳)は、約1ヵ月前に自宅近くのレンタカー会社で乗用車一台をレンタルしました。
レンタルした際は、翌日に返却する契約をしていたのですが、Aさんは返却せず、レンタカー会社に無断でそのまま乗り続けていました。
そして昨日、このレンタカーを運転して奈良市内を走行中に、奈良県奈良警察署の警察官に職務質問を受けたAさんは、レンタカーの横領が発覚し、逮捕されてしまいました。
逮捕されたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士にAさんの初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
横領~刑法第252条第1項~
刑法第252条第1項に「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する」と横領罪が規定されています。
今回の事件では、Aさんはレンタカー会社の車を、契約期日を過ぎても返却せずにそのまま使用していたので、Aさんの行為は「横領罪」に当たる可能性が非常に高いでしょう。
しかし、もし契約時からAさんに、翌日にレンタカーを返却する意思がなかたった場合は、店員を騙してレンタカーを借りたことになるので、詐欺罪が成立する可能性もあります。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」と横領罪に比べると厳しいものです。
最終的にどのような法律が適用されるかは、実行行為だけでなく、警察等の捜査機関での取調べ内容によって決定するので、横領罪等の刑事事件で警察の警察の取調べを受けている方は、事前に、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
横領事件の弁護活動
今回のような横領事件では、逮捕された後に、勾留されることが少なくありません。
逮捕、勾留されている方は、弁護士以外から刑事手続きに関するアドバイスを受けることはできませんので、弁護士の助けがなければ、逮捕から勾留までの全てを一人で対処しなければなりません。
その様な事態を回避するために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用いただき、早期に弁護士の選任をご検討ください。
刑事事件専門の弁護士を選任することによって様々なメリットがございます。
①助言を受けることができる
一度逮捕されてしまうと、最大で23日間身柄を拘束されることになります。
その期間、捜査機関からの取調べを受けることになりますが、逮捕された方は、どのように取調べを受けて良いのか分からないはずです。
取調べで発言した内容は、後に裁判で取り消すことが非常に困難です。
ご自身の判断だけでは、不利な発言をしてしまう可能性が高くなります。
そこで、先に弁護士からどのように取調べを受けるかの助言をしてもらうことで、取調べ段階で、不利益になるような事態を避けることができるでしょう。
②弁護士の面会
逮捕から勾留決定までの間は、基本的にご家族の方でさえも面会ができません。
また、勾留中の場合、ご家族の方は面会できますが、面会時間に制限があり、立会人がいるため、お互いに伝えたいことを伝えきれない可能性があります。
また弁護士は逮捕から勾留が決定するまでの間でも面会ができ、弁護士は接見によって、逮捕された方の精神的負担を軽くするように努めます。
弁護士の面会は立会人なしで行われるため、逮捕された方は自分が思っていることを自由に話すことができます。
③被害者との交渉
検察官は、裁判で有罪であると証明できる場合でも、被疑者の情状や犯罪後の情況などを考慮して起訴する必要がないときは不起訴処分とします。
被害者との間に示談が成立していれば、検察官が不起訴処分とする可能性が非常に高まります。
そこで、弁護士は、代理人として被害者に対する謝罪や示談交渉を行います。
④不起訴処分となるように検察官へ働きかける
起訴して裁判を行うかどうかは、検察官が決定します。
そこで、弁護士は、検察官が起訴しない(不起訴処分とする)ように働きかけます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料相談、初回接見をおこなっております。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、奈良市の横領事件など、刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
窃盗事件での弁護活動
窃盗事件での弁護活動
窃盗事件での弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
奈良県大和高田市に住むAはコンビニを利用した際に、レジに財布が置いてあることに気が付きました。
前の客が忘れていったものでしたが、Aはその財布を無意識にカバンに入れて、そのまま持ち帰ってしまいました。
後日、高田警察署から連絡があり、Aは窃盗の疑いで取調べを受けることになりました。
(この事例はフィクションです)
今回の事例は、前の客がレジに置き忘れた財布を盗んでしまったという事件です。
このとき、財布の占有がどこにあったかによって窃盗罪か遺失物若しくは占有離脱物横領罪となるかが変わってきます。
これは、被害者がどのくらい離れていたか、どれくらいの時間が経っていたか、などで判断されることになります。
過去の裁判例では被害者がベンチを離れて2分、距離が200メートルほど離れたところでポシェットを忘れているのに気づいたが、すでに盗られていた、という事案で窃盗罪の成立が認められたものがあります。
今回の事例でも被害者の状況によっては罪名が変わる可能性はありますが窃盗罪で疑われているとします。
窃盗
刑法235条
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
窃取とは、不法領得の意思をもって他人の占有を侵害し、財物を自己の実力的支配内に移すことを指します。
そして、不法領得の意思とは、権利者を排除して他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従いこれを利用又は処分する意思のことをいい、分かりやすく表現すると、人の物を盗んで自分の物として、その物を使ったり、売って利益を得たりする意思ということです。
窃盗罪等の財産犯罪が成立するにはこの不法領得の意思が必要であり、遺棄、隠匿目的で財物奪取行為を行った時は窃盗罪にあたらないとされています。
今回のケースでは、Aにこの不法領得の意思がなかったことが認められれば、窃盗罪は成立しないことになります。
このような主張が認められるのかはもちろん、このような主張をしていくためには取調べでどのように対応していけばよいのかについては、弁護士の見解を聞くようにしましょう。
特に取調べの対応については重要です。
認めているのか否認しているのかで処分に影響が出ますし、あいまいな記憶で答えてしまうと、自分の意思とは違う調書ができてしまいます。
そこに署名をしてしまえば、裁判になった際にその調書は証拠となるのです。
示談交渉
窃盗罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と法定刑の幅が広く設定されています。
これは、被害金額や場所、方法などが事件ごとに全く異なってくるからです。
そのため、専門知識がなければ見通しを立てることも難しくなってしまいますので、専門家である弁護士にきちんと相談し、見通しを聞くようにしましょう。
そして、ほとんどの場合で有効な手段となるのが、被害を弁償し、謝罪の意思を伝える示談です。
被害届の取下げといったことまではできなくても、被害弁償をしていることによって不起訴となる可能性もあります。
ただ、個人での示談交渉ということになると被害弁償も受け取ってもらえないというケースもありますので、示談交渉の経験も豊富な刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
被害弁償を受け取ってもらえない場合にも供託という制度を利用したり、示談の経緯についてまとめて検察官との処分交渉を行うなど様々な活動を行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、窃盗罪に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。