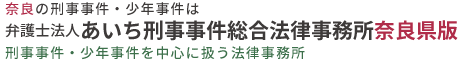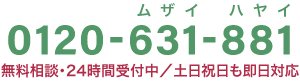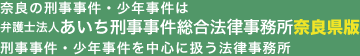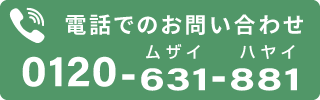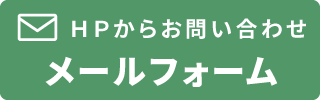Author Archive
痴漢事件の示談は弁護士へ
痴漢事件の示談は弁護士へ
痴漢事件の示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県香芝市に住むAは、自宅の最寄駅構内において、痴漢事件を起こし、奈良県香芝警察署に逮捕されてしまいました。
Aは、痴漢の事実を認め、翌日には、釈放されました。
Aは、被害者に謝罪して示談をしたいと思い、申し入れをしようとしたのですが、警察に取り次いでもらうことはできませんでした。
困ったAは、刑事事件に強い弁護士に相談し、示談を含む弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
示談を弁護士に依頼するメリット
今回の事例のAが起こした痴漢事件など、被害者のいる刑事事件では、被害者の方と示談しているかどうかは、最終的な処分に大きく影響します。
今回のAのような痴漢事件では、検察官が起訴不起訴の判断をする前に示談を締結することができれば、不起訴処分を獲得することができる可能性もあります。
しかし、示談をしたいと思っても、当事者やその家族だけでは、なかなか示談成立までこぎつけることは難しいと言えます。
まず、最初に示談交渉に入るために、被害者の方の連絡先を知ることが非常に難しくなります。
今回の痴漢事件のように、被害者の方と被疑者が知らない人同士の可能性が高い事件では、連絡先を知らなければ示談交渉を開始することすらできません。
被害者の方は、加害者やその家族に対して良い感情を持っていないことはもちろんですが、示談交渉をするために連絡先を教えたり、話をしなければならないという状況に恐怖を感じることが予想されます。
だからこそ、示談をしたいとお悩みの場合には、弁護士に相談することがおすすめされるのです。
弁護士という第三者を介し、個人情報は弁護士限りにとどめ、加害者とも直接のやり取りをしなくてもよいとなれば、被害者の方も話に応じてくれやすくなります。
さらに、刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験も豊富にありますので、示談の内容を含め、安心して示談交渉をお任せいただくことができます。
示談書の内容
刑事事件で示談締結が非常に重要であることは述べましたが、示談書の内容は具体的にどのようなものになるのでしょうか。
示談書の内容の基本的な部分について、加害者から被害者への謝罪や示談金の取り決めはもちろんですが、事件によっては以下の項目を記載したりします。
口外禁止
事件のことや示談のことを、みだりに第三者に言わない、という約束です。
被害者の方にとってはもちろんのこと、被疑者・被告人にとっても、刑事事件に関与したという情報や、それに関して示談を行ったという情報は、非常にデリケートな情報となりますから、示談に際してこうした約束事が設けられることが多いです。
接近禁止
示談の際の約束事として、今後被疑者・被告人が被害者の方へ近づかない、という約束を入れる場合もあります。
痴漢事件の場合、これに加えて、犯行現場となった駅や路線を被疑者・被告人が利用しないようにする、という約束をして示談するケースも見られます。
宥恕
宥恕とは、被害者が加害者を許すことを意味します。
示談締結に際してはこの宥恕文言を納得していただくかどうかは、処分にも影響する非常に大きな要素の一つです。
被害届が出ている場合はその取下げを条項に加えることもあります。
今回ご紹介したものは、あくまで代表的な内容です。
示談については事件の詳細な事情によっても変わってきますし、被害者の方、被疑者・被告人の要望等により、示談の内容は細かく異なってきます。
示談は金銭の授受のみではなく、こうした細かい約束事も非常に大切ですので、示談に悩んだら、まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
いじめではすまない恐喝罪
いじめではすまない恐喝罪
恐喝罪の少年事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市の高校に通っている18歳のAは、友人たち3人と、中学校の頃からVをからかっていました。
そしてそれは、高校に進学してからどんどんエスカレートしていき、Aとその友人たちは頻繁にVを脅してお金を巻き上げるようになっていきました。
ある日、Vが黙って家のお金を持ち出したことでAと友人の恐喝行為が発覚し、Vの両親は奈良県奈良警察署に通報しました。
Aとその友人はすぐに通報を受けた奈良県奈良警察署の警察官に、恐喝罪の容疑で逮捕されてしまいました。
高校3年間で、被害総額は200万円にもなっていました。
奈良県奈良警察署の警察官からAが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は、少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
少年の恐喝罪について
恐喝罪は、刑法249条1項に規定されており、「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」とされています。
上記の事例のAは、Vを脅して(=恐喝して)、Vのお金(=財物)を渡させていた(=交付させていた)ので、この恐喝罪に当たる行為をしていたことになります。
少年のいじめによる恐喝事件は、1994年に、いじめを受けて少なくとも110万円を恐喝された中学生が自殺したという事件がありました。
また、2000年には、名古屋市で中学生が約5000万円の恐喝事件を起こして逮捕され、注目を浴びました。
恐喝は、子どものいたずら、いじめという言葉でおさまるものではなく、立派な犯罪です。
もし継続的に行っており、被害額が膨らめば、被害弁償すら難しい金額になってしまいます。
いじめは刑事事件
いじめというと学校内での問題と捉えてしまいがちですが、学校内でのいじめであっても刑事事件となる可能性が十分にあります。
今回の事例のような恐喝罪やすぐに思いつくような暴行、傷害事件はもちろんのこと物を隠す行為は器物損壊罪となる可能性がありますし、何かを命令する行為は強要罪となる可能性があります。
このように、学校内で考えられるいじめについても刑事事件となってしまう可能性が高いといえるでしょう。
そのため、今回の事例のように逮捕されている場合はもちろん、逮捕されていない在宅事件であってもいじめが刑事事件になりそうという場合には、決して軽く考えるようなことはせず、少年事件に強い弁護士に弁護活動を依頼し、更生に向けた活動を行っていくようにしましょう。
少年の更生には専門の弁護士を
少年事件では、成人事件とは違い、少年の更生が最重要とされています。
この更生の度合いについては、家庭裁判所での最終的な処分にも大きく影響してきます。
少年の更生のためには、いじめや恐喝の被害者の方へ謝罪・賠償を行うのはもちろんのこと、少年自身の環境を調整することも重要になります。
少年自身の環境とは、交友関係や親子関係など少年を取り巻く環境のことをいいます。
たとえば今回の事例でいえば、一緒にいじめをしていた友人と連絡を取らないようにする、親子間のコミュニケーションを密にする、などが考えられます。
少年事件に強い弁護士は、こういった活動のサポートやアドバイスを適切に行い、少年一人一人に合わせたベストな方法での解決へ導いていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事・少年事件専門の弁護士事務所です。
少年事件、恐喝事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間体制で無料法律相談、初回接見のご予約を受け付けております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
器物損壊事件で逮捕
器物損壊事件で逮捕
器物損壊事件での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県大和高田市の会社に勤めていたAさんは、仕事が上手くいかず、会社内の人間関係にも悩んでいました。
このような状況でストレスに耐えかねたAさんは、会社に飾ってあった社長が所有する有名な陶芸家が製作したとされる時価200万円の壺に対しても怒りを感じるようになってしまいました。
「俺たちの稼いだ金でなんでこんなものを買っているのか」と疑問に思ったAさんはその壺を地面にたたきつけて、こなごなに破壊してしまったのです。
すぐに他の社員たちに取り押さえられたAさんは、器物損壊の容疑で、奈良県高田警察署の警察官に逮捕されることになってしまいました。
Aさんが逮捕されたと聞いたAさんの妻は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事案はフィクションです)
器物損壊
Aさんは刑法第261条に規定されている器物損壊罪で逮捕されました。
Aさんとしては、家族のためにも起訴されることは何としても避けたいと考えています。
Aさんが起訴を避けるためには、どのような方法があるのでしょうか。
器物損壊罪は親告罪ですので、適切な対応を取ることができれば、不起訴処分を獲得することが可能です。
親告罪とは
親告罪とは被害者の告訴がなければ起訴できない罪のことをいいます。
告訴とは、被害者その他告訴権を有する一定の者が捜査機関に対し犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示です(刑事訴訟法第230条)
そこで、今回の事例で言えば、被害者である社長に告訴を取り下げてもらうことができれば、Aさんは、起訴されることはなくなるのです。
そのため、親告罪において弁護士は、被害者に告訴を取り消してもらえるよう活動する必要があります。
具体的には、相手方に対して、賠償を行い、示談を締結することによって告訴を取り消してもらいます。
示談交渉
親告罪において、示談交渉が非常に有効であることはご説明しました。
では、示談とは弁護士がいなくてはできないことなのでしょうか。
実は、弁護士がいなくても示談をすることは可能です。
ただ、刑事事件における示談については、示談の交渉相手は被害者やその代理人ということになります。
処罰感情を持っている相手に対して、示談交渉をしていくことは非常に難しいといえるでしょう。
そのため、示談交渉が必要という場合には、刑事事件に強い弁護士を選任し、示談に向けた交渉を円滑に行なっていった方が良いでしょう。
特に親告罪では、示談が締結され、告訴の取り消しがあるかどうかで、その後の展開が大きく変わってきてしまいますので、後悔のない事件解決のためにも、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件では、親告罪以外の事件であっても示談交渉は非常に重要な弁護活動となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にあるので、安心してお任せいただくことが可能です。
示談交渉は、相手に合わせて行っていく必要がありますので、経験が非常に重要となります。
そのため、奈良県での示談交渉は、刑事事件を専門に扱い、事務所として刑事事件の経験が豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。
奈良県大和高田市の器物損壊事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
刑事事件に強い弁護士が逮捕されている方の下へ向かう初回接見、初回無料での対応となる法律相談を行っています。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
現場から逃亡してしまった
現場から逃亡してしまった
現場から逃亡してしまった場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良奈良市に住む会社員のAが、あるとき電車に乗っていると、たちまち満員電車となってしまいました。
そこで、目の前に好みの女性が来たAは、その女性の臀部を触ってしまいました。
女性はすぐに車両の緊急停止ボタンを押し、電車は次の駅で停車しました。
そして、ドアが開いた瞬間にAは、走って駅構内を駆け抜け、駅の外まで逃亡しました。
Aは無事に逃げ切り、一週間が経ちましたが、警察などからの連絡は一切ありません。
Aは不安で夜も眠れません。
(この事例はフィクションです。)
逃亡してしまうと逮捕されやすい?
今回のAは、痴漢行為をしてしまい、その現場から逃走しています。
逃亡というと刑法上に逃走罪が規定されていますが、この逃走罪は「裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者」に対する罪ですので、逮捕前の段階については逃走罪とはなりません。
では、刑事事件を起こしてしまった場合、逃亡した方が得をするのか、というとそうではありません。
逃亡してしまった場合、逮捕されてしまい身体拘束を受ける可能性が高くなってしまいます。
逮捕の要件
逮捕には、大きく分けて現行犯逮捕、緊急逮捕、通常逮捕があります。
今回の事例では、Aは現場から逃走し、一週間が経過していますので、逮捕されてしまうとすれば、通常逮捕になるでしょう。
そこで通常逮捕の要件についてみていきましょう。
逮捕の要件は、具体的に、逮捕の理由と逮捕の必要性があるか、ということです。
逮捕の理由
刑事訴訟法第199条1項には「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」場合に逮捕することができると規定されています。
この要件は逮捕の理由と呼ばれます。
逮捕の必要性
刑事訴訟法第199条2項では、裁判官が逮捕状を発するには『逮捕の必要性』がいるとされています。
この条文は抽象的ですが、刑事訴訟規則第143条の3に具体的に書かれています。
1 被疑者が逃亡するおそれ
2 被疑者が罪証を隠滅するおそれ
1に「逃亡するおそれ」とあることから、すでに現場から逃亡してしまっている場合は逮捕の必要性があると判断されてしまう可能性は高くなってしまうことがわかります。
すなわち、現場から逃亡してしまった場合は逮捕されてしまう可能性が高くなってしまうのです。
また、近年では至る所に防犯カメラが設置されているため、Aの犯行であることが特定されてしまう可能性は高いといえます。
今回の事例でも駅構内の防犯カメラには逃亡しているAの姿が映っていることでしょう。
逮捕を回避するために
一度、現場から逃亡してしまった場合、逮捕は避けられないのか、というとそうではありません。
逮捕の可能性を下げるためにできることの一つとして、自ら出頭することが挙げられます。
自首が成立すれば、逮捕の可能性はさらに低くなりますが、捜査機関にすでに事件が発覚している場合、自首は成立しません。
それでも自ら警察署に出頭し、罪を認めて反省していくことは、罪を逃れようと逃亡する行為とは真逆の行為ですので、逮捕の可能性を少しでも下げることはできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、自首あるいは出頭に同行することも可能です。
自首、出頭する際に弁護士が付いているということ自体も、逮捕の可能性を下げる要素の一つとなります。
これは、刑事事件に強い弁護士であれば、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがないことを的確にアピールしていくことができるからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
逃亡してしまい、不安な夜を過ごしている方はすぐにご連絡ください。
初回無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
執行猶予中の犯罪
執行猶予中の犯罪
執行猶予中の犯罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県桜井市に住むAは、2年前に詐欺事件を起こしてしまい、「懲役3年執行猶予5年」の有罪判決を受けていました。
その後は穏やかに暮らしていたAでしたが、あるとき出来心からコンビニエンスストアで万引きをしてしまいました。
Aの犯行は店員に発覚してしまい、通報され、奈良県桜井警察署の警察官が駆け付けました。
その後Aは、奈良県桜井警察署で取調べを受けることになりましたが、このままでは執行猶予が取り消されてしまい、刑務所に行かなければならないのかと不安になりました。
そこでAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
執行猶予中の再犯について
刑の全部の執行猶予は刑法第25条に規定されています。
刑の全部の執行猶予は、
「前に禁錮以上の刑に処せられたことのない者」
若しくは、
「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又は免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者」
が
「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」
の言渡しを受けたとき、
「情状により裁判確定の日から1年以上5年以下の期間その刑の執行を免除される」
というものです。
今回のAは、2年前に「懲役3年の言渡しを受けていますが、5年の期間その執行を猶予されている状態」、ということになります。
このような執行猶予中に再犯をしてしまうと、執行猶予は必ず取り消されてしまうのでしょうか。
刑の全部の執行猶予が取り消される場合
執行猶予中に罪を犯した場合に刑の全部の執行猶予が取り消される場合は
1.猶予の期間内にさらに罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき(刑法第26条第1号)
2.猶予の期間内にさらに罪を犯し、罰金に処せられたとき。(刑法第26条の2第1号)
が考えられます。
1については、必要的取消であり、必ず執行猶予が取り消されてしまいます。
2は裁量的取消であるとされており、裁判官の判断で取り消されてしまう可能性があります。
今回のAは、「懲役3年執行猶予5年」の執行猶予期間に「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」である窃盗罪を犯してしまいました。
例えば、今回の窃盗罪で「懲役2年」という言渡しを受けてしまい、執行猶予が取り消されると前回の懲役3年と合わせて5年間刑務所に行かなければならなくなるのです。
執行猶予が取り消されないために
執行猶予中に犯罪をしてしまった場合でも必ず執行猶予が取り消されて刑務所に行かなければならないわけではありません。
執行猶予が取り消されないための活動として、被害者の方と示談を締結するなどして不起訴処分を目指していく方法が考えられます。
もしも、起訴されてしまうという場合でも、検察官に意見書を提出するなどの活動によって懲役刑ではなく、罰金刑を求めていきます。
前述のように罰金刑であれば、執行猶予が必ず取り消されるというわけではなくなります。
これらの活動は刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士であれば、被害者との示談交渉、検察官との処分交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せいただくことができます。
そして、公判請求されてしまったとしても、まだ望みを捨ててはいけません。
再度の執行猶予
執行猶予中に犯罪をしてしまい、起訴されて公判請求となり、裁判を受けるという段階になっても、まだ執行猶予が取り消されるとは限りません。
執行猶予中にしてしまった犯罪についてもう一度執行猶予判決を受ける可能性が残されています。
執行猶予中の犯罪について執行猶予判決を受けることを再度の執行猶予といいます。
刑法第25条第2項には、
「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者」
が、
「1年以下の懲役又は禁錮の言渡し」
を受け、
「情状に特に酌量すべきものがあるとき」
は刑の全部の執行を猶予することができる
と規定しています。
(ただし、保護観察付執行猶予であった者は除く)
すなわち今回のAが起訴されて裁判となってしまった場合でも、「懲役1年以下」の言渡しであり、情状に酌量すべきものがあれば、再度の執行猶予を獲得できる可能性があるのです。
再度の執行猶予を獲得できれば、執行猶予が取り消される場合の1「猶予の期間内にさらに罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき」ではなくなるのです。
ただ、この再度の執行猶予獲得を目指していくには、情状面で有効なアピールをしていくなど適切な弁護活動が必要となりますので、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
このように、執行猶予中に罪を犯してしまっても、必ず執行猶予が取り消されてしまうというわけではありません。
執行猶予中に罪を犯してしまった場合でも、実刑を回避できることもありますので、一度刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所です。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間体制で無料法律相談、初回接見のご予約をお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
飲酒運転で逮捕
飲酒運転で逮捕
飲酒運転について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県大和高田市に住むAは、ある日の休日、朝までお酒を飲んでいました。
そして、翌日1時間ほど寝たAは仕事のために自動車を運転して会社に向かいました。
しかし、Aの身体には明らかにお酒が残っており、まともに運転することはできず、Aは民家の塀に自動車をぶつけてしまいました。
住人が出てきて奈良県高田警察署に通報したところ、駆け付けた警察官がAの不審な様子に気が付きました。
そこで呼気検査を要求されたAからは基準値を超えるアルコールが検出され、Aは酒気帯び運転の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
飲酒運転
飲酒運転とは、お酒を飲んだ状態で自動車等を運転することを指しますが、今回は、飲酒運転をしてしまった場合に適用されることのある法令のうち、代表的なものをご紹介します。
酒気帯び運転
まず、道路交通法に規定されている酒気帯び運転です。
道路交通法第65条第1項は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めています。
そして、この規定に違反して、車両等(軽車両を除く。)を運転した者が、身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあれば、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(道路交通法117条の2の2第3号)に処せられます。
これが、酒気帯び運転といわれるものです。
政令で定める程度、とは「血液1ミリリットルにつき0.3g又は呼気1リットルにつき0.15mg以上のアルコールを保有する場合」を指し、この数値を超えていた場合に酒気帯び運転となります。
そのため、警察官は酒を飲んでいる疑いがある者に、呼気検査等を実施するのです。
酒酔い運転
次に酒酔い運転が考えられます。
酒気帯び運転に対し、酒酔い運転は、身体に保有するアルコールの量、つまり呼気検査等の数値は関係ありません。
酒を飲み、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車を運転していた場合、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます。(道路交通法第117条の2第1号)
危険運転致死傷罪
これまで見てきた酒気帯び運転、酒酔い運転は、飲酒運転をして、飲酒検問で検挙されたり、今回の事例のように物損事故を起こしてしまったりした場合に適用される可能性のあるものです。
もしも、飲酒運転で人身事故を起こしてしまうと、もっと重い処罰を受けてしまう可能性があります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、「自動車運転処罰法」)にもアルコールに関する規定があります。
自動車運転処罰法第2条に規定されている危険運転致死傷罪では、第1号において「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」により人を負傷させた者は「15年以下の懲役」、死亡させた場合は「1年以上の有期懲役」が規定されています。
そして、自動車運転処罰法第3条には、準危険運転や3条危険運転と呼ばれる規定があります。
これは、運転開始時にアルコール又は薬物の影響により、走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、その後正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた場合「12年以下の懲役」人を死亡させた場合は「15年以下の懲役」が規定されています。
もちろん、飲酒運転で人身事故を起こしてしまった場合でも、必ず危険運転致死傷罪や準危険運転になるとはかぎりません。
酒気帯び運転と過失運転致傷となることもありますので、詳しくは刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
飲酒運転は人身事故を起こしてしまうと、非常に重い刑事罰が科されることになりますし、たとえ事故を起こしていなかったとしても決して軽くはない刑事罰が科されてしまいます。
飲酒運転に関する規定は、今回ご紹介したものだけでなく、飲酒検知を拒否することや、人身事故の後にアルコールを摂取したり、お酒を抜いてから出頭したりするなどアルコールの発覚を免れることについても罰則があります。
このように飲酒運転に関する罰則にはさまざまなものがありますので、飲酒運転でお困りの方やそのご家族はぜひ一度刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う事務所です。
フリーダイヤル0120-631-881にて初回接見、無料相談のご予約を24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
メールで脅迫して逮捕
メールで脅迫して逮捕
脅迫罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県生駒市に住む主婦のA子は旦那と6歳になる息子の3人で暮らしていました。
A子と旦那の家族とは、あまり仲が良くなく、小さな言い争いが頻繁に起こっていました。
特に旦那の姉であるVとは仲が悪く、Vにも息子と同い年の子どもがいることもあり、A子はVの家族には負けたくないと考えていました。
二人の息子が小学校に入学する年になったころ、A子の息子は有名私立の受験に失敗してしまいましたが、Vの息子はA子の息子が落ちた学校に合格しました。
そのことに嫉妬したA子は、Vに対して、「Vの息子さんはあの有名私立小学校に入学したらしいけど登校時の列に車で突っ込むから」というメールを送信しました。
怖くなったVは、すぐに奈良県生駒警察署に通報し、A子は逮捕されることになってしまいました。
A子が逮捕されたという連絡を受けたA子の旦那は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
脅迫罪の対象
脅迫罪は刑法第222条に規定されています。
刑法第222条
第1項「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」
そして、2項では、親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して脅迫した者も同様とすると規定されています。
親族の範囲については、民法第725条に規定されています。
1.6親等内の血族
2.配偶者
3.3親等内の姻族
つまり、害悪を加える対象が恋人や友人の場合は、脅迫罪は成立しませんが、今回の事例のように子どもに対して害悪を加える旨を告知した場合は脅迫罪が成立する可能性があるのです。
では、具体的にどのような行為が脅迫罪となってしまうのでしょうか。
脅迫罪における害悪の告知
脅迫罪で相手方に告知する害悪については、一般人が畏怖する程度のものであれば脅迫罪が成立し、実際に相手が畏怖したかどうか関係ありません。
そして、告知の方法についての制限はなく、相手方に知らせる手段を施し、相手方が知れば脅迫罪は成立します。
今回の事例のようにメールを送った場合だけでなく、言語、態度、動作で示したり、文書の掲示、郵送、第三者を介しての告知であっても成立するのです。
なお、脅迫の内容に「●●されたくなければ、●●しろ」等相手に義務のないことをするように指示する内容があれば、脅迫罪よりも重い罰則が規定されている刑法第223条の強要罪となってしまう可能性もあります。
脅迫罪の弁護活動
脅迫罪は、相手方に対して害悪の告知をすることになるので、被害者の連絡先や住所等を知っているケースが多くなります。
そのため、被害者との接触可能性が高いと判断されてしまい、身体拘束を受ける可能性は高くなってしまいます。
そのため、身体解放に向けては、被害者との接触をしない旨を誓約したり、ご家族等がしっかりと監視監督することを約束したりすることが大切になってきます。
こういったことを弁護士が検察官や裁判所にアピールしていくことで、身体解放の可能性が高まっていくのです。
また、脅迫罪の弁護活動においては、被害者と示談交渉をしていくことも大切になってきます。
今回のA子のように被害者が親族であったり、近所に住む人や以前からの顔見知りという場合には、示談交渉をしようにも、本人同士が顔を合わせて交渉すると感情的になってしまうこともあるでしょう。
そのため、弁護士を通して、しっかりと示談交渉していくことが必要となってきます。
脅迫罪は示談が成立することで不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
ただ、具体的な事件の見通しについては、被害者との関係や脅迫の内容等によっても変わってきますので、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う事務所です。
逮捕されてしまった際の身体解放活動、被害者との示談交渉をご希望の方は、ぜひ一度フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
素振りに当たった子どもが死亡
素振りに当たった子どもが死亡
過失致死罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良市山稜町に住む会社員のAは、草野球のチームに参加していました。
そこで活躍したいと考えていたAは、会社が終わってから自宅の家の前の路上で素振りをしていました。
あるとき、素振りをしているAの近くを近所に住む子どもが通りかかりました。
Aはそのことに気付かず、金属バットをフルスイングしてしまい、子どもの頭に当たってしまいました。
Aはすぐに応急処置をして救急車を呼び、子どもは病院に運ばれましたが、間もなく死亡してしまいました。
すると、Aの下へ奈良県奈良西警察署の警察官が来て、Aは重過失致死罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。
(この事例はフィクションです。)
故意と過失
刑法では、故意について刑法第38条に規定しています。
刑法第38条第1項
「罪を犯す意思がない行為は罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りではない。」
今回の事例のAは、子どもをわざと殴ったわけではないので、罪を犯す意思のある行為ではありません。
そのため、今回のAの行為は法律に特別の規定がない限り、罰せられることはありません。
ただ、今回の事例のように過失により人を死亡させてしまった場合は、法律に規定があり、過失致死罪や業務上過失致死罪、重過失致死罪となる可能性があります。
まずは、それぞれの条文を確認してみましょう。
過失致死罪
刑法第210条
「過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する」
業務上過失致死罪(前段)、重過失致死罪(後段)
刑法第211条
「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする」
業務上過失致死罪における業務とは、次のように判示されています。
「本条にいわゆる業務とは、本来人が社会生活上の地位に基づき反復、継続して行う行為であって、他人の生命、身体等に危害を加えるおそれあるものをいう」(最高裁 判例 昭和33年4月18日)
「本条にいう業務には、人の生命、身体の危険を防止することを義務内容とする業務も含まれる」(最高裁決定 昭和60年10月21日)
上記をみると、今回の事例のAの行為は業務であるとはいえないでしょう。
そこで、問題となるのは、過失があったのか、あったとすればその程度が条文上の「重大な過失」にあたるのか、ということです。
過失致死罪と重過失致死罪
過失致死罪と重過失致死罪では、懲役刑の規定があるかどうかという罰則に大きな違いがあります。
そのため、過失致死罪となるか重過失致死罪となるかは、非常に重要であるといえるでしょう。
過失致死罪と重過失致死罪の違いは、その過失の程度です。
過失とは、注意義務違反のことで、過失の要件については裁判所の決定があります。
「過失の要件は、結果の発生を予見するとことの可能性とその義務及び結果の発生を未然に防止することの可能性とその義務である」(最高裁決定 昭42年5.25)
過失の程度とは、つまり注意義務違反の程度ということになり、そこから過失致死罪となるか、重過失致死罪となるか判断されます。
そして、過失の程度については、状況によっても変わってきますので、過失犯として刑事事件になってしまった場合は刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
状況によっては過失がなかったと判断される可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
過失致死罪や重過失致死罪で、過失の有無や程度について争っていきたい方はもちろん、被害者の方へ適切な賠償がしたいという方にも対応可能です。
奈良の刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが無料法律相談、初回接見のご予約を24時間体制で受け付けております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
刑事事件はスピードが命、なのはなぜか
刑事事件はスピードが命、なのはなぜか
刑事事件の流れについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住む会社員のAは、妻と大学生になる息子(22歳)と三人で暮らしていました。
あるとき、遊びに出ていた息子が帰って来ず心配していたところ、奈良県奈良警察署から連絡を受けました。
警察官から、息子さんを詐欺の疑いで逮捕しました、と聞かされたAは弁護士を探すことにしました。
すると、さまざまなところで「刑事事件はスピードが命」、「刑事事件はスピード勝負」といった内容を目にしました。
焦ったAは、刑事事件に強いという弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
刑事事件の流れ
刑事事件についてインターネットで検索したりすると「刑事事件はスピードが命」、「スピード勝負」といった言葉をよく目にします。
刑事事件でスピードが大切だと言われているのは、なぜなのでしょうか。
これは刑事事件の、特に身体拘束を受けている事件については、手続きや身体拘束の期間について明確に時間が決められていることが関係しています。
今回は警察に逮捕されてから起訴されるまでの事件の流れについて時系列順に弁護士ができることを交えてご紹介します。
逮捕~48時間
警察官に逮捕された場合、警察官は48時間以内に検察官に事件を送致しなければなりません。(刑事訴訟法第203条第1項)
※弁護士は
弁護士は検察官に送致せず、釈放するよう求めることができます。
検察官に送致せず釈放という可能性もあるのです。
送致~24時間
検察官は、警察から送致されてきた事件について、24時間以内に裁判所に対して身体拘束の継続である勾留を請求するかどうか判断し、請求しない場合は釈放しなければなりません。(刑事訴訟法第205条)
勾留が請求された場合には、裁判官が勾留を決定するかどうかを判断します。(刑事訴訟法第207条)
※弁護士は
検察官に対して勾留を請求しないように、裁判官に対して勾留請求を却下すように働きかけていくことができます。
勾留決定後
上記までの手続きで勾留が決定されてしまった場合、通常10日間身体拘束を受けることになり、最大でさらに10日間の延長が認められています。
勾留の満期になると、検察官は起訴しない場合、不起訴や処分保留で釈放しなくてはなりません。(刑事訴訟法第208条)
なお、起訴されてしまった場合には起訴後勾留となります。
※弁護士は
勾留決定に対して準抗告という不服申し立てを行うことができます。
準抗告が認容されると、釈放されることになります。
また、勾留期間中に示談等適切な弁護活動を行い、検察官と交渉していくことで不起訴処分を目指して活動していきます。
逮捕、勾留されている事件であっても最終的に不起訴処分を獲得することも十分に可能なのです。
これまで、逮捕から起訴までの簡単な流れを見てきましたが、身体拘束を受けているいわゆる身柄事件での逮捕されてから起訴までの期間は基本的には、最大でも23日間となっていることがわかります。
弁護士ができることも記載しましたが、勾留が決定をした後は勾留決定に対する準抗告(不服申し立て)はできますが、勾留を決定されないようにする活動はできなくなりますし、起訴されてしまった後は不起訴処分に向けた活動はできません。
このように刑事事件で最大限の弁護活動を行おうと思うならば、できるだけ早い期間から弁護士に依頼しなければなりません。
そのため、刑事事件ではスピードが命、スピード勝負だと言われているのです。
もちろん、少し時間が経ってしまっているからといって遅すぎるということはありません。
まずは一度、お問い合わせください。
今できることをし、少しでも早く対応していくことが後悔のない事件解決へとつながっていきます。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話を。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
覚醒剤譲受事件の保釈
覚醒剤譲受事件の保釈
覚醒剤譲受事件の保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県天理市に住む無職のAさんは、自宅近くの路上において、売人から覚醒剤を3万円で譲り受けました。
すると、パトロールをしていた奈良県天理警察署の警察官に上記の行為を現認されてしまい、職務質問を受けることになりました。
薬物担当刑事による簡易検査の結果、覚醒剤であることを示す反応が検出され、Aさんは覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは勾留されることになり、国選弁護人が付きました。
勾留の満期日を迎えたAさんは覚醒剤取締法違反で起訴されてしまい、すぐに保釈の請求をしましたが、却下されてしまいました。
Aさんの家族は国選弁護人から刑事事件に強い弁護士に切り替えようと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
~覚醒剤譲受について~
覚醒剤取締法第41条の2第1項では、覚醒剤をみだりに譲り受けた者について「10年以下の懲役」が法定されています。
「譲り受けた」とは、相手方から、物についての法律上又は事実上の処分権限を与えられて、その所持の移転を受けることをいいます。
なお、取引について、有償、無償を問いませんので、事例のように買い受けたわけではなく、覚醒剤を無料で受け取った場合も覚醒剤取締法違反となります。
覚醒剤関連事件では、入手経路や余罪の捜査も必要になってきますので、身体拘束を受けた状態で事件が進行していく可能性は高いといえます。
~身柄解放活動(保釈)~
保釈とは、裁判所からの許可を受けたうえで、保釈保証金を裁判所に納めることで、釈放される制度です。
ただ、保釈は請求したからといって必ず保釈許可決定が出るとは限りません。
そのため、弁護士は法律で定める保釈の要件を満たしていることをしっかりとアピールしていく必要があります。
保釈の要件は法律に規定されていますが、実際の事例について裁判所が保釈の許可の判断をしていくうえで重要視する部分は事件や被告人によってさまざまです。
そのため、弁護士はそれを見極めたうえで保釈の請求をしていく必要があります。
例えば、今回のような薬物事件では、薬物依存に対する治療の必要性や、携帯電話を新しくするなどして売人等との関係を完全に断ち切ることを主張していくことも有効でしょう。
このほかにも、個々人に対応したアピールがありますので、保釈をご希望の際は、ぜひ刑事事件に強い弁護士にご依頼ください。
刑事事件の経験が豊富な弁護士であれば、最適のアピールをしていくことができるでしょう。
~起訴後でも私選弁護人への変更は可能~
さて、今回の事例のAさんには、当初国選弁護人が付いていました。
しかし、一度目の保釈請求が却下されたことにより、Aさんとご家族は私選弁護人への変更を希望しています。
起訴されてからであっても国選弁護人から私選弁護人に変更することは可能です。
国選弁護人のままで人を変更することは基本的にできませんので、国選弁護人が付いている方が弁護士を変更しようと思うと私選弁護人に変更する、ということになります。
私選弁護人への変更をご検討されている場合は、ぜひ刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご依頼ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士を派遣させる初回接見サービスを行っています。
拘置所への接見も可能ですので、起訴されてしまったという方も一度フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。
刑事事件はスピードが命と言われますが、遅すぎるということもありません。
後悔のない事件解決のためにも一度お電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。