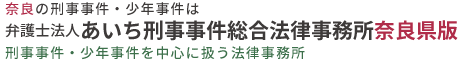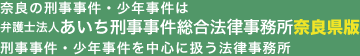殴り合いを強要
強要罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事件~
奈良県に住むAは、香芝市で従業員十数人の会社を経営していました。
あるとき、Aの前で従業員のうち二人が口論を始めました。
Aは、お互いに気持ちをぶつけあうことで仲も深まるだろうと「二人とも思う存分殴り合え。やらないなら二人ともクビだ。」と言い出しました。
その言葉に触発された二人は殴り合いの喧嘩を始めてしまい、二人は傷害を負うことになってしまいました。
この話を聞いた従業員の家族が激怒し、Aに対する被害届を奈良県香芝警察署に提出しました。
後日、奈良県香芝警察署から連絡があり、Aは取調べに呼ばれることとなってしまいました。
取調べ前にアドバイスをしてほしいと考えたAは。刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
強要罪
今回のAは刑法第223条の強要罪に当たる可能性が高いです。
強要罪は暴行、脅迫を用いて他人に義務のないことを強要することで成立します。
Aの「やらないなら二人ともクビだ。」という発言は、脅迫に当たると考えられます。
そして、この脅迫を用いて、従業員の二人に殴り合いというなんの義務もないことをさせているので、強要罪が成立する可能性は非常に高いでしょう。
強要罪の法定刑は「3年以下の懲役」と罰金刑の規定がない、比較的重い罪となっています。
間接正犯と教唆犯
間接正犯と教唆犯は、他人を利用して犯罪を実行させるという点では似ています。
しかし、間接正犯は、人を道具として犯罪を実行させていることから、原則的に実際に犯行を行った者は刑事責任を負わず、刑事責任を問われるのは利用者だけです。
その反面、教唆犯は、責任能力のある他人を教唆して、特定の犯罪の実行を決意させ、かつ実行させるもので、その刑事責任は、行為者と利用者の両方に科せられる、いわゆる共犯の一形態です。
では、強要罪が成立する場合に、その強要した行為が犯罪行為であった場合、強要した者にどのような刑事責任が及ぶのかを検討します。
①強要に至る脅迫が、相手方の意思決定の自由を失わせるものであるときは、実行された犯罪(今回の事例では傷害罪)の間接正犯と強要罪の刑責を負う可能性があります。
②強要に至る脅迫が、意思決定の自由を抑圧するに至らないときは、実行された犯罪の教唆犯と強要罪の刑責を負うでしょう。
今回の事件でAさんは、「やらないなら二人ともクビだ。」と言って従業員を脅迫しています。
この脅迫が、二人の従業員の意思決定にどの程度影響したのかによりますが、この程度の脅迫で、二人が意思決定の自由を失ったとは考えるのは難しいでしょう。
実際にこのような形態の間接正犯の成立を認めた判例は少なく、例えば殺傷能力の高い凶器を突き付けられて脅迫された場合や、実際に暴行されて、従わななければ更にひどい危害を加えられるかもしれないときなどのように、意思決定の自由を強度に抑圧する場合において、間接正犯が認められるものと解されています。
つまり今回の事件を考えると、Aに強要されて殴り合いをした二人の従業員は、傷害罪の刑責を免れることは難しく、お互いに傷害罪の刑責を負うことになってしまいます。
今回の事例のように、何らかの犯罪行為にあたることは容易に想像できるような場合でも、実際に誰にどのような刑罰が科される可能性があるのか、と言われると少し複雑になってきます。
特に警察が介入する前ですと、自分が何罪で疑われているのかも分からない状況となってしまいます。
このようなときには、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士は、あらゆる可能性を考慮したうえで、見通しをお伝えさせていただきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱っておりますので、その見通しはより正確なものとなるでしょう。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。