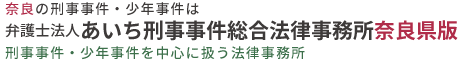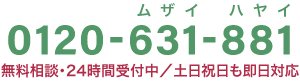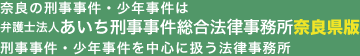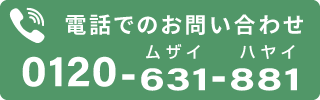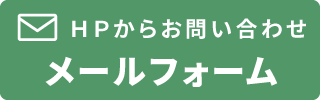Archive for the ‘刑事事件’ Category
不法投棄が刑事事件に発展
不法投棄で刑事事件に
不法投棄で問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【ケース】
奈良県香芝市在住のAは、香芝市内の会社に勤める会社員です。
Aは仕事の都合で香芝市内にある一人暮らし中のアパートから香芝市内の実家に戻ることになりました。
その際、一人暮らし中に使用していた洗濯機や冷蔵庫、テレビなどが不要になりました。
Aは急いで香芝市の粗大ゴミ回収の担当者に連絡をしましたが、回収に時間がかかると説明を受けました。
そこで、正規の手続きを行わずに自宅近くの裏山に、それらの粗大ゴミを捨てました。
数ヶ月経った後、香芝市内を管轄する香芝警察署の警察官がAの実家に来て、廃棄物処理法違反で任意同行するよう求められました。
≪ケースは全てフィクションです。≫
【不法投棄についての罪】
街中を歩いていると、不法投棄は犯罪です、といった看板やポスターなどを目にすることがあるかもしれません。
不法投棄は、個人や会社等が排出したゴミを正規の方法で処理しないことを指す一般的な言葉です。
このゴミは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃棄物処理法)により「廃棄物」と定められています。
このうち、事業活動で生じた一部の廃棄物等を産業廃棄物とし、産業廃棄物以外(個人が日常で排出するような廃棄物)は一般廃棄物と定義されています。
一般廃棄物をルールに従わずに捨てた場合、以下の規定に違反し、刑事罰が科せられます。
廃棄物処理法16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
14号 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
【不法投棄での弁護活動】
不法投棄は、前章で確認したとおり、廃棄物処理法に違反することとなり厳しい刑事罰が用意されています。
では、個人が一般廃棄物を不法投棄した場合にすぐに厳しい刑事罰が科せられるのかというと、必ずしもそうではありません。
具体的には、廃棄した物の性質やその量、頻度、理由などを総合的に検討したうえで、どの程度の刑事罰が科せられるか、決められます。
事件を起こしてしまった場合、在宅事件として捜査が進められる場合と、逮捕・勾留される場合があります。
いずれの場合も、引き当たり捜査と呼ばれる犯行現場の写真撮影などの手続きが終了するまでは、不法投棄した物は回収できません。
写真を撮り終え、証拠物の量などを図り終えたことを捜査機関に確認したのち、速やかに廃棄物処理業者を通じて処理を行い、その証明書等を作成することが望ましいです。
また、不法投棄した場所が私有地で行われた場合、土地所有者に対する謝罪や弁済が必要となる場合があります。
不法投棄が問題となる廃棄物処理法違反事件で土地所有者は直接の被害者ではありませんが、捜査に協力せざるを得なかったり一定期間その土地を使えなかったり、場合によっては被疑者特定の前に処理するため処理に時間や費用を使ったりしているという事例もあり、被疑者は民事上の請求義務がある場合が考えられます。
刑事手続きにおいても、捜査機関に対して「直接の被害者ではないものの、不法投棄した土地の所有者に謝罪し弁済している」ことを主張することは、検察官が終局処分を判断するうえで(被疑者にとって)有利な事情であると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
奈良県香芝市にて、粗大ゴミなどの不法投棄をしてしまい、出頭を命じられていたり家族が逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に御相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
五條市の飲食店で食逃げ 詐欺罪に問われますか?
五條市の飲食店で食逃げした方からの「詐欺罪に問われますか?」という質問について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
五條市の飲食店で食逃げした方からの相談
先日、私は五條市内の定食屋で食事をしました。
飲食代は2,000円ほどでしたが、勘定しようとしたところ、財布がない事に気付きました。
私は、店主が店奥の厨房に入った隙に店を飛び出して逃げてしまいました。
インターネットで調べると、食逃げは詐欺罪になるとありましたが、私は警察に逮捕されるのでしょうか?
(フィクションです。)
詐欺罪
刑法第246条に「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と、詐欺罪を規定されています。
詐欺罪は、被害者を騙し(欺罔行為)、騙された被害者(錯誤)が、被害者自身の意思に基づいて財物の交付を行う事によって成立します。
無銭飲食の場合、最初から無銭飲食する事を企て、お金を払う意思がないのに、飲食店で料理を注文すると詐欺罪が成立する可能性が大です。
それではAさんのように、食べ終わった後でお金がないことに気付いた場合は、どうでしょう。
後日、飲食代を支払う意志がないのに、店員を騙して、後日に支払う事を約束してお店を出た場合は、詐欺罪が成立する可能性がありますが、店員の隙をついて黙って逃げた場合は、欺罔行為がないので、詐欺罪が成立しない場合があります。
まずは弁護士に相談
刑事弁護活動に関わった方は、一日でも早く、刑事事件に強い弁護士に相談する事をお勧めします。
記憶が鮮明なうちに、事件の内容を弁護士に相談する事によって、より的確なアドバイスを受ける事ができ、必要に応じて、迅速的確な、弁護活動をスタートする事ができるからです。
五條市で、詐欺事件に強い弁護士をお探しの方、詐欺罪で警察の取調べを受けている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881
にて24時間、年中無休で受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
【解決事例】天理市の路上における痴漢事件で不起訴を獲得
【解決事例】天理市の路上における痴漢事件で不起訴を獲得
天理市の路上における痴漢事件で不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
Aさんは、最寄りの駅から歩いて自宅に帰宅途中である、天理市の路上で、女性のお尻を触った痴漢事件で奈良県天理警察署で取調べを受けました。
犯行時、酒に酔っていたAさんは、帰宅途中に偶然見かけた女性に興味を持ち、女性を追い抜き際にお尻を触って逃げたのですが、追いかけてきた女性に捕まってしまい、その場で110番通報されました。
当初から素直に犯行を認めていたAさんは、逮捕こそ免れましたが、被害女性の許しを得ることはできていませんでした。
そこで弁護士が被害者との示談交渉をおこなったところ、被害者との示談を締結することができ、Aさんは不起訴処分となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
天理市の痴漢事件
天理市内で痴漢事件を起こせば、奈良県の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)違反となります。
奈良県の迷惑防止条例では、公共の場所や乗物において、他人を著しくし羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに他人の身体に触れる卑わいな行為を禁止しています。
これに違反すると、起訴されて有罪が確定した場合「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
痴漢事件の量刑
痴漢事件を起こして警察の捜査を受けた方の刑事処分は、初犯であれば略式起訴による罰金刑となる可能性が高いでしょうが、2回目、3回目となれば正式に起訴されて刑事裁判によって裁かれる可能性が高くなります。
最初の刑事裁判で、いきなり実刑判決が言い渡されることは極めて珍しいケースではありますが、短期間における再犯の場合や、一人の被害者に対して長期間にわたって繰り返し犯行に及んでいる等悪質な場合は、執行猶予が付かず実刑判決が言い渡される可能性があるので注意が必要です。
不起訴を目指すなら示談が必要不可欠
奈良県の痴漢事件で不起訴を目指すのであれば、被害者との示談が必要不可欠となります。
示談がなくても嫌疑不十分等を理由に不起訴になるケースもありますが、Aさんのような路上における痴漢事件で、犯行直後に被害者に捕まってしまったような犯人性が明白な事件では、被害者との示談がなければ不起訴は難しいでしょう。
実際に今回の刑事手続きにおいて、Aさんは担当検察官が「示談がなければ略式起訴による罰金刑で手続きを進める。」と言われていました。
このコラムをご覧の方で、奈良県の痴漢事件でお困りの方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)
にて承っております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
奈良県香芝市でタクシーの運転手とトラブル 運転手と示談
奈良県香芝市でタクシーの運転手とトラブル 運転手と示談
奈良県香芝市でタクシーの運転手とトラブルで、運転手と示談した弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
タクシーの運転手とトラブル・奈良香芝警察署に逮捕
会社員のAさんは、酒を飲んでの帰宅途中に利用したタクシーの運転手に対して暴行を加えた上に、タクシーを損壊させたとして、奈良県香芝警察署に逮捕されました。
Aさんは、タクシー料金が思ったよりも高かったことが理由で犯行に及んだようですが、逮捕されて酔いが覚めたAさんは、早急に運転手と示談して事件を円満解決したいと考えています。
(フィクションです)
タクシーの運転手と利用客との間のトラブルはよくある話ですが、口論で終了すれば当事者間のトラブルで済み、刑事事件にまで発展する可能性はありませんが、Aさんのように、運転手に暴行を加えたり、タクシーを破壊した場合には、刑事事件化する可能性が高くなります。
特に、乗客が酒に酔った状態の場合には、自制が効かず些細なことで暴行に及んでしまうことがあり、事件となるケースが多いので、お酒に酔ってタクシーを利用する際は注意が必要です。
暴行罪と器物損壊罪
暴行で逮捕され、起訴後に有罪判決を受けると「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」が科せられることになります。(刑法第208条)
また、器物損壊の場合には「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」が科せられることになります。(刑法第261条)
双方とも、初犯の場合や被害者と示談が成立している場合には、不起訴処分となる可能性が高くなります。
ただし、前科・前歴がある場合や犯行が悪質で反省が見られない場合には、その限りではないので注意が必要です。
示談交渉
タクシーの運転手を相手にこういった事件を起こしてしまった場合には、運転手との示談交渉が効果的と言われています。
弁護士を通じて被害者に、被害弁償を行い示談することで刑事罰が軽減される可能性があるのです。
刑事手続きが進んでいる中で、当事者同士が示談交渉を行うことは困難ですので、刑事事件で被害者と示談交渉を検討されている方は、示談交渉に強い弁護士に被害者との示談交渉を依頼することをお勧めします。
奈良県香芝市の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、奈良県香芝市の刑事事件に対応している刑事事件専門の法律事務所です。
タクシーの運転手との示談交渉をご希望の方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881
にて、24時間・年中無休で承っております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
【解決事例】電車内の痴漢事件 示談できずに略式起訴(罰金)
【解決事例】電車内の痴漢事件 示談できずに略式起訴(罰金)
電車内の痴漢事件で、被害者と示談ができずに略式起訴(罰金)となった解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
Aさん(60歳代、無職)は、奈良市内を走行中の電車内で女子高生に痴漢したところ目撃者に捕まり、その後、通報で駆け付けた奈良県奈良西警察署の警察官に、痴漢の容疑で逮捕されました。
痴漢の事実を認めていたAさんは逮捕翌日には釈放されましたが、不起訴を求めて、弁護人を選任しました。
選任された弁護士が、被害者の母親と示談交渉をおこなったのですが、処罰感情が強かったことから示談することができませんでした。
その結果、Aさんは略式起訴されて罰金刑となってしまいました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
電車内の痴漢事件
奈良県内の走行中の電車内で痴漢事件を起こせば、奈良県の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)違反となります。
奈良県の迷惑防止条例では、公共の場所や乗物において、他人を著しくしゆう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、みだりに他人の身体に触れる卑わいな行為(痴漢行為)を禁止しており、これに違反して痴漢をすれば、起訴(略式起訴を含む)されて有罪が確定した場合「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
不起訴を目指すなら示談が必要不可欠
痴漢事件で不起訴を目指すのであれば、被害者との示談が必要不可欠となります。
示談がなくても嫌疑不十分等を理由に不起訴になるケースもありますが、Aさんのように痴漢の事実を認めている場合は、被害者との示談がなければ不起訴は難しいでしょう。
ちなみに初犯であればAさんのように略式起訴による罰金刑となる場合がほとんどですが、再犯の場合は正式に起訴(公判請求)される可能性が出てきます。
略式起訴とは
略式起訴とは、簡易裁判所が、その管轄事件につき、検察官の請求のより、公判手続を経ないで、主として検察官の提出した証拠を審査して、一定額以下の罰金または科料を科す簡易裁判手続のことです。
略式起訴の手続きは、書類上の審査だけで、罰金を納付すれば全ての刑事手続きが終了するというメリットがあります。
犯罪事実に争いがある場合は、略式命令の告知を受けた日から14日以内に正式裁判の請求をすることができます。
このコラムをご覧の方で、奈良県の痴漢事件でお困りの方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)
にて承っております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
【刑法一部改正】『拘禁刑』が創設と『侮辱罪』の厳罰化
【刑法一部改正】『拘禁刑』が創設と『侮辱罪』の厳罰化
13日の参議院本会議で、『拘禁刑』の創設と、『侮辱罪』の厳罰化が可決、成立し、刑法が一部改正されます。
本日のコラムでは、この刑法一部改正について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
拘禁刑の創設
懲役刑と禁錮刑が廃止
現在の刑法では第9条に「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料(付加刑として没収)」と、刑罰が定められていますが、この中の「懲役刑」と「禁錮刑」が、今回の改正で一本化されて『拘禁刑』となります。
「懲役刑」とは、刑事施設に拘置され、その中で刑務作業を強いられる刑罰です。
また「禁錮刑」とは、刑事施設に拘置されるという点では懲役刑と同じですが、懲役刑で強いられる刑務作業は希望者のみで強制はされません。
禁錮刑は、一部の過失犯や、内乱罪などの政治犯などに規定されています。
今回の刑法一部改正によって、この懲役刑と禁錮刑が廃止されることになりました。
拘禁刑が創設
懲役刑と禁錮刑にかわって新たに創設されるのが『拘禁刑』です。
拘禁刑とは、懲役刑と禁錮刑を一本化したもので、一部改正刑法が施行されると、受刑者の年齢や特性に合わせて、刑務作業と更生に向けた指導を柔軟に組み合わせることができるようになります。
侮辱罪の厳罰化
刑法第231条(侮辱罪)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
と、侮辱罪を規定しています。
侮辱罪には現在、拘留又は科料の法定刑が定められていますが、改正刑法が施行されると、法定刑は1年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金と厳罰化され、公訴時効は1年から3年になります。
刑事事件に関するご相談は
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件でお困りの方からのご相談を年中無休、24時間体制で受け付けております。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
夫婦喧嘩の末に娘に暴行 母親が逮捕
夫婦喧嘩の末に娘に暴行 母親が逮捕
夫婦喧嘩の末に娘に暴行した母親が逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件概要(6月11日配信のABCニュースを基に作成しています。)
奈良県生駒警察署は、夫婦喧嘩の末に、2歳の娘を足蹴りしたとして、暴行罪の容疑で母親を逮捕したと発表しました。
報道によりますと、6月11日未明、生駒市にある集合住宅の一室から「子どもの泣き声と、『警察を呼んで』という男性の声が聞こえた」と警察に通報があり、奈良県生駒警察署の警察官が現場に駆け付けたところ、集合住宅の一室に住んでいる夫婦がつかみ合いの喧嘩をした際に、喧嘩の腹いせに、母親が2歳の娘を蹴って転倒させていたことが判明したとのことです。
幸いにも2歳の娘に怪我はなく、暴行の容疑で逮捕された母親は取調べにおいて「けんかの怒りを娘に向けてしまい、衝動的に蹴ってしまった」と容疑を認めているということです。
暴行罪
人に対して暴行すれば暴行罪となります。
昔は、今回の事件のような家庭内の軽い暴行事件について警察が介入することは滅多にありませんでしたが、最近は、こういった家庭内の事件についても、警察は積極的に介入する傾向にあります。
特に今回の事件のような、幼い子供に対する暴行事件は、虐待事件に発展する可能性があることから警察は強制力(逮捕)をもって積極的に事件化しているように思います。
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と比較的軽いものですが、こういった刑事罰が科せられる以上に、警察が介入して事件化されることで、テレビや新聞、インターネット等のニュースで事件が報道されたり、子供が児童相談所に保護されたりといったかたちで被る不利益の方が大きくなるでしょう。
暴行罪の弁護活動
他人に対しての暴行事件であれば、被害者との示談交渉が主な弁護活動となりますが、今回のような自身の娘に対する暴行事件の場合は、示談交渉というのは叶いません。
そのため、少しでも軽い処分を求めるのであれば、本人の反省の意思を高めと、再発防止策を講じるしかありません。
こういった事件を二度と起こさないために何ができて、実際に何をするかが、どういった刑事罰が科されるかに影響するでしょう。
弁護士はそういった取り組みを提案することができますので、是非ご相談ください。
家庭内の暴行事件に強い弁護士
このコラムをご覧の方で、家庭内の暴行事件に強い弁護士を必要とされている方がいらっしゃいましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士の無料法律相談を
フリーダイヤル 0120-631-881
にて24時間、年中無休で承っております。
なお、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕や勾留等で身体拘束されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意しています。
初回接見サービスについては こちら をご覧ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
【解決事例】奈良県香芝市の公然わいせつ事件 目撃者との示談で不起訴を獲得
【解決事例】奈良県香芝市の公然わいせつ事件 目撃者との示談で不起訴を獲得
奈良県香芝市の公然わいせつ事件で、目撃者との示談によって不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
同僚と酒を呑んで酔払っていたAさんは、帰宅途中の奈良県香芝市の路上において、通行人の女性に陰部を露出する公然わいせつ事件を起こしました。
目撃者の通報で駆け付けた警察官に検挙されたAさんは、後日、警察署に呼び出されて取調べを受けることになりましたが、Aさんは、公務員であることから、不起訴になることを強く望んでいました。
(実際に起こった事件を基に、事件の発生地等一部変更を加えています。)
路上における公然わいせつ事件
陰部を露出する露出行為は「公然わいせつ罪」となります。
公然わいせつ罪は、公然とわいせつな行為をすることによって成立する犯罪で、刑法第174条に規定されています。
その法定刑は「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
公然わいせつ罪でいう「公然」とは、不特定又は多数の人が認識する可能性のある状態を意味し、実際に、不特定又は多数の人が認識することまでは必要とされません。
ここで注意が必要なのは、認識する人たちが特定された人たちであっても公然わいせつ罪が成立することです。
例えば、ネットで集った同じ性的嗜好を持つ人達が複数で、ホテルの一室で性行為に及ぶ場合や、いわゆるストリップ劇場等で性器を露出する行為であっても、違法性は阻却されず、公然わいせつ罪に該当する可能性があります。
目撃者との示談
公然わいせつ罪は、社会的法益である性秩序を保護法益としている法律なので、法律的には、刑事手続き上の被害者は存在しないとされています。
しかし、Aさんの起こしたような公然わいせつ事件では、目撃者が実質的に被害を被っています。
ですからこの目撃者と示談することによって、後の刑事罰が軽減される可能性があるのです。
実際に今回の弁護活動においても、弁護士は、警察から開示された被害者に対して、Aさんの謝罪の意思を伝えると共に示談交渉を行いました。
その結果、目撃者との示談を締結することができたのです。
不起訴処分の獲得
警察の捜査が続く一報で、Aさんに対する警察の取調べが行われ、その後は、検察庁に書類送検されました。
弁護士は、目撃者と示談している旨を担当の検察官に報告すると共に、Aさんの刑事処分について交渉を行いました。
その結果、Aさんが深く反省していることや、目撃者との示談が成立していることが高く評価されて不起訴処分を獲得することができました。
弁護活動を振り返って
公然わいせつ事件には様々なかたちがあります。
Aさんのように見知らぬ人に性器を見せつけるような事件もあれば、特定の複数人の中でわいせつ行為を行うような、実質的な被害を被っている人がいない事件もあります。
同じ公然わいせつ罪ですが、弁護活動の内容が異なってきますので、このコラムをご覧の方で、公然わいせつ罪について不安のある方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)
にて承っております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
人気アニメの缶バッジを無断で販売目的所持 著作権法違反で逮捕
人気アニメの缶バッジを無断で販売目的所持 著作権法違反で逮捕
人気アニメの缶バッジを無断で販売目的所持、著作権法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要(5月24日に配信された朝日新聞DIGITALから抜粋)
人気アニメのキャラクターの缶バッジを無断で製造し、販売目的で所持したとして、24日、奈良県警に二人の男が著作権法違反で逮捕されました。
逮捕された男らは、数年前から人気アニメのキャラクターの缶バッジを合計約2600個制作し、奈良市内の商業施設等で販売したり、販売目的で所持した容疑がもたれていますが、逮捕事実を認めているようです。
今回の事件は、昨年8月、奈良県警に情報提供のメールがありそこから捜査が開始されたようです。
著作権を有するメーカー等に無断でこういった商品を製造、販売、販売目的等で所持すれば著作権法違反となります。
今回の事件では、アニメの著作権を有する東宝など計19社の侵害したとされています。
著作権法違反
アニメだけでなく、本や音楽、映像、コンピュータープログラム、この世に存在するありとあらゆるものには、それを作った人などに権利があります。
その権利が著作権です。
そして著作権を有する人の許可なくして、複製したり、使用することによって、著作権を侵害すれば、著作権法違反になるのです。
著作権法違反の罰則は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金となり、場合によっては、懲役と罰金の両方を科される事もあります。
また、侵害者が法人の場合には、罰則が強化され、3億円以下の罰金となることもあります。
著作権法違反で逮捕されたら
ご家族、ご友人が著作権法違反で奈良県警に逮捕された場合、一刻も早く逮捕された方のもとに弁護士を派遣した方がよいでしょう。
奈良県内の刑事事件を扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意しています。
初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
にて承っております。
なお著作権法違反で警察等に逮捕されてしまった方に弁護士を派遣する初回接見サービスについては、⇒⇒こちらをクリック
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
奈良公園のシカを死なせると…文化財保護法違反について解説
奈良のシカに対する文化財保護法違反
奈良のシカに対する文化財保護法違反ついて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
奈良県奈良市に住むAさんは、奈良公園で国の天然記念物に指定されている「奈良のシカ」に刃物をたたきつけて死なせたとして、奈良県奈良警察署に文化財保護法違反の疑いで逮捕されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
奈良のシカ
「奈良のシカ」は古来、春日大社の「神鹿(しんろく)」として大切にされ、1957年に国の天然記念物に指定されました。
その対象エリアは奈良公園内のほか、2005年の市町村合併前の旧奈良市全域です。
天然記念物は、文化財保護法に規定があります。
文化財保護法
第2条「この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。」
第4号「貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で我が国にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)」
第109条
「文部科学大臣は、記念物のうち重要なものを史跡、名勝又は天然記念物(以下「史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。」
第196条
「史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、毀損し、又は衰亡するに至らしめた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。」
「奈良のシカ」は国の天然記念物に指定されていますので、「奈良のシカ」を傷つけた場合にも、文化財保護法違反となります。
お城やお寺への落書きなどは文化財保護法違反としてイメージしやすいかと思いますが、天然記念物に指定されている生物に対する行為も文化財保護法違反の可能性があるのです。
他の動物で言えば、オオサンショウウオを捕獲、飼育していた人が文化財保護法違反で検挙されたという例もありますので、動植物を傷つけてはいけないのはもちろんのこと、捕獲等にも注意が必要です。
~少しでも早い身柄解放を目指すためには~
今回の事例のAは文化財保護法違反で逮捕されています。
刑事事件で逮捕されてしまった場合、どのくらいの間身体拘束を受けることになるのでしょうか。
逮捕され、勾留が決定しまった場合、起訴されるまでの捜査段階で最長23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
会社に勤務していたり、学校に通うなどしている場合であっても、逮捕・勾留中は外に出ることができないので、その間は、欠勤・欠席を続けることになります。
無断欠勤・無断欠席が続いてしまうと、会社をクビになったり、学校を留年するなどの不利益を受けることになりますし、たとえ家族等から連絡を取ってもらったとしても23日間も休むのは不自然になってしまうでしょう。
そのため、逮捕されてしまった場合は、できるだけ早く身体拘束から解放され、外に出ることが重要です。
特に逮捕直後においては、勾留を阻止する活動が重要となってきます。
逮捕されてしまったケースにおいて、絶対に勾留が決定するというわけではありません。
勾留は検察官が請求し、裁判官が決定することになります。
そのため、弁護士は検察官、裁判官に対して働きかけを行うことで、勾留が決定しないように活動していくことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。