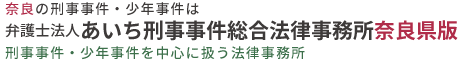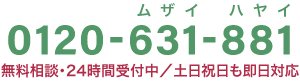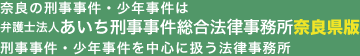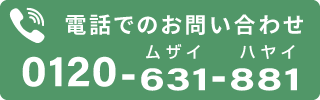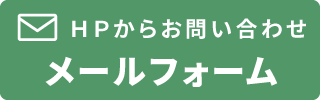Author Archive
盗撮事件が会社に発覚
盗撮事件が会社に発覚
盗撮事件の社会的制裁について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
奈良県に住むAは、あるとき、通勤で使用している電車に乗ろうとした際にミニスカートをはいた女性を発見しました。
エスカレーターに乗っているときに後ろから撮影すれば、盗撮できると考えたAは女性の後ろからスマートフォンで下着を撮影しました。
しかし、女性は振り返り、盗撮行為に気が付きました。
会社や家族にバレてしまってはまずいと考えたAはその場で謝罪し、後日改めて謝罪をするということで連絡先を交換しました。
なんとか示談をして、警察への通報を避けたいと考えたAは刑事事件に強い弁護士が行う無料法律相談へ行き、示談交渉を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
刑事事件の社会的制裁
刑事事件が発生し、逮捕されたり、報道されたりすることで会社や学校に知られてしまうと会社から解雇されたり、学校から退学処分を受けたりする場合があります。
また事件が報道されてしまうと、社会から厳しい非難を浴びることになり、場合によっては転居する必要があるかもしれません。
こうした刑事罰以外に受けることになる社会的な不利益を一般に社会的制裁といいます。
社会的制裁は、逮捕・勾留などの刑事処分よりも、後の人生に大きく影響してしまう可能性があります。
もしも何か刑事事件を起こしてしまい、社会的制裁についてもご不安ということがあれば弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士ならば、刑事罰等の事件に対する見通しはもちろんのこと、様々な社会的制裁に対する対応策についてもご相談可能です。
社会的制裁に対する活動
そもそも、会社や学校から解雇処分や退学処分を受けることになるのは、事件のことを会社や学校に知られ、何らかの処分が必要だと判断されるからです。
そこで、まず第一に考えうる社会的制裁の回避策は、「事件のことを学校や会社に秘密にすること」です。
事件のことを知られなければ、解雇されたり、退学させられたりといった社会的制裁を受けることはないと言ってよいでしょう。
では、事件のことを秘密にするにはどうすればよいでしょうか。
その方法の一つが、とにかく事件を早く穏やかに解決することです。
今回の事例のAのように警察が介入する前に被害者に謝罪する機会があれば、被害者との示談交渉によって警察が介入する前に事件を終了させるようにしましょう。
このような迅速な示談によって、事件化を阻止し、警察の捜査を免れることができるかもしれません。
そして、逮捕・勾留されているとすれば、早期釈放を実現し、一日でも早く会社や学校に復帰することを目指します。
何日も会社や学校を休んでしまうと、会社や学校が事件を知るリスクが高まってしまうからです。
またマスメディアによる報道も事件が周囲の人に知られる大きなきっかけとなります。
そのため、出来るだけ早く対応し、警察に事件を公表させない・マスコミに事件を報道させないよう働きかけていくことも重要です。
そして仮に、事件のことが会社や学校に知られてしまっているという場合でも打つ手がないわけではありません。
弁護士は懲戒処分や学校の処分に関してもできる限りの交渉を行っていき、懲戒解雇や退学などの重い処分が下らないように活動していきます。
実際の事件でどのような対応をしていくかは具体的な事件内容によって異なってきます。
ただ、いずれの事件についても早めの対処が後悔のない事件解決へとつながっていきますので、刑事事件を起こしてしまったというときはすぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談へ行くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
夜行バスで準強制わいせつ
夜行バスで準強制わいせつ
夜行バスでの準強制わいせつについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
奈良県に住む会社員のAは東京に行くのに奈良駅発着の夜行バスを利用することにしました。
Aは一人で利用していたため、帰りのバスで若い女性と席が隣になりました。
深夜、眠っていたAでしたが、たまたま目を覚ましてしまいました。
ふと、隣の女性を見てみると完全に熟睡しており、今なら触ってもばれないのではないかと思ったAは女性の胸を触ってしまいました。
女性に気付かれなかったことをいいことに今度は強く胸を揉んでしまったところ、女性は目を覚ましました。
女性はその場でバスの運転手に報告し、運転手は警察に報告しました。
奈良駅に着くと奈良県奈良警察署の警察官が待ち構えており、Aは準強制わいせつの疑いで逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は刑事時事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
準強制わいせつ
準強制わいせつは刑法第178条第1項に規定されており、心神喪失又は抗拒不能に乗じたり、心神喪失や抗拒不能にさせたりしてわいせつな行為をした者について強制わいせつと同じ「6月以上10年以下の懲役」の罰則を規定しています。
心神喪失とは、基本的に精神の障害によって正常な判断力を喪失している状態をいい、今回の事例のような熟睡状態や泥酔、高度の精神病や精神薄弱を上げることができます。
そして抗拒不能とは、心神喪失以外で心理的、物理的に抵抗することができなかったり、極めて困難な状態をいいます。
抗拒不能の具体例としては医師が治療と称してわいせつ好意を行った場合などですが、心神喪失との区別は必ずしも明確ではありません。
今回のようにバスや電車内で眠っている人に対してわいせつ行為を行った場合、状況によっては痴漢行為として各都道府県に規定されている迷惑行為防止条例違反となる可能もありますが、今回の事例のように準強制わいせつとなる可能性もあります。
詳細については専門家である弁護士の見解が必要であると言えるでしょう。
被害者との示談交渉
刑事事件を起こしてしまったときに被害者がいた場合の重要な弁護活動として示談交渉が挙げられます。
わいせつ系の事件は特に被害者の処罰感情は処分にも大きく影響してきます。
今回の事例のような準強制わいせつ事件であっても被害者と処罰を求めないという内容を含めた示談を締結することができれば、身体拘束からも解放され、不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
しかし、特にわいせつ系の事件で今回の事例のように顔見知りではない、知らない相手が被害者となってしまった場合については被害者と示談交渉を始めること自体が難しくなります。
被害者のことを全く知らない場合、連絡先等は基本的に警察や検察など捜査機関から教えてもらうことになります。
ただ、捜査機関から示談を希望していると聞かされても加害者本人やその家族に連絡先を教えることは、恐怖心もあることから、ほとんどありません。
そんなときは刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にありますし、弁護士を間に立てることで、被害者も加害者本人やその家族に直接連絡先を知られてしまうわけではなくなるので、安心して示談交渉をすることができます。
さらに、弁護士は示談を締結したことをもって検察官と処分の交渉も行っていくことができますので、弁護士に依頼したほうが不起訴処分を獲得できる可能性は上がります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
傷害罪で警察から呼び出し
傷害罪で警察から呼び出し
警察からの呼び出しについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
奈良県山陵町に住む会社員のAは、同僚と口論になり、ついつい殴って怪我を負わせてしまいました。
友人が奈良県奈良西警察署に被害届を提出したことから、Aは、呼出しを受けることになりました。
Aは警察に出頭したほうがよいか迷ったので、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
傷害罪
刑法第204条
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
今回のAは警察からの呼び出しを受けていますが、もしも警察からの呼び出しに応じない場合はどうなってしまうのでしょうか。
逮捕
逮捕には、現行犯逮捕、緊急逮捕、通常逮捕の3種類が存在します。
今回の事例では、被害者である同僚は後日に警察への届け出を行っているため、逮捕される場合には通常逮捕であることが予想されます。
※今回の傷害事件で通常逮捕される場合の流れ(一例)
①事件発生⇒②被害者が警察に届け出る(被害届を提出)⇒③警察が事件を捜査⇒④警察が犯人を割り出す⇒⑤警察が裁判官に逮捕状を請求⇒⑥裁判官が逮捕状を発付⇒⑦警察が犯人を逮捕
逮捕の必要性
警察が犯人を割り出せば、そこで犯人を逮捕する必要があるかどうかが判断されます。
これを法律用語で逮捕の必要性といいますが
●逃亡するおそれ
●罪証を隠滅するおそれ
の何れかがあれば、逮捕の必要性が認められます。
つまり警察が割り出した犯人に、逃亡するおそれがあったり、証拠隠滅の可能性が認められた場合は逮捕されるリスクが非常に高くなるのです。
そしてこの罪証を隠滅するおそれについては、被害者との接触可能性も含まれることになります。
これは、被害者の証言等も重要な証拠となってくるからです。
そのため、今回の事例のように被害者が近い存在であり、接触する可能性が高くなると逮捕の可能性は高くなってしまうことになるのです。
ただ、逆にこれらの必要性が認められなければ逮捕される可能性が低くなり、その後は身体拘束を受けることなく警察の呼出しに応じて取調べを受けることとなる、いわゆる在宅事件として事件は進行していきます。
警察の呼出しに応じないと
今回の事例のAのように傷害事件を起こして、警察の呼出しに応じなかった場合、逮捕のリスクが生じてしまいます。
警察が犯人を呼び出す場合、不拘束で取調べることを前提に犯人を呼び出すことがほとんどですが、この呼出しに応じないとなれば、警察は逃走するおそれがあると判断する可能性が高いです。
そうなった場合、警察は「呼び出しましたが出頭しません。」ということを疎明して、裁判官に逮捕状を請求し、最終的には逮捕されることとなってしまいます。
そのため、基本的には警察から呼び出しを受けた場合には日程の調整等はするにしても応じたほうがよいと言えるでしょう。
ただ、状況によっては呼び出しに応じたらそのまま逮捕されるということも考えられますので、逮捕の可能性などに関しては一度弁護士の見解を聞くようにしましょう。
傷害事件やその他の刑事事件を起こして警察から呼出しを受けている方、警察の呼出しに応じて出頭しようか迷っている方は、刑事事件専門の弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件を専門に扱っている経験豊富な弁護士が、皆様が警察に逮捕されるリスクを解説いたします。
もちろん、弁護活動をご依頼いただけば、逮捕されないように、また、逮捕されてもできるだけ早く身体解放されるように活動していきます。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
通貨偽造事件で裁判員裁判
通貨偽造事件で裁判員裁判
通貨偽造事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
奈良県天理市に住む大学生のAは、どうしてもお金が必要になってしまい、何とかなるかもしれないと自宅のカラープリンターで偽1万円札を作成しました。
思いのほかうまくできたので試してみようと自宅近くのスーパーで使用しました。
しかし、偽札であることは判明してしまい、Aは通貨偽造・同行使の罪で奈良県天理警察署に逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士の初回接見サービスを利用することにしました。
弁護士からの報告を受けたAの両親は、起訴されてしまうと裁判員裁判になると聞かされそのまま刑事事件専門弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
通貨偽造
偽造した偽一万円札を使用すると、通貨偽造・同行使の罪にあたります。
通貨偽造については、刑法第148条に定められており、行使つまり使用する目的で、貨幣、紙幣又は銀行券を偽造、又は変造することです。
通貨偽造の対象となるのは、日本銀行において製造、発行されている紙幣、硬貨の他、政府の認許によって特定の銀行が発行する紙幣の代用物としての証券(銀行券)です。
また、これら貨幣、紙幣又は銀行券は、日本国において法律による強制通用力があるものでなければならず、古銭や廃貨のように強制通用力を失っているものは対象となりません。
通貨偽造における「偽造」とは、通貨の発行権を持たない者が、真貨と誤信させるような外観の物を作成することをいい、その程度は、一般人が誤信する程度で足ります。
また「変造」とは、真貨を用いて他の通貨と誤信させる外観の物を作成することをいいます。
例えば、1枚の千円札を2枚に見えるように加工したりするなどです。
変造にあたるとされる程度については偽造と同じく、一般人が誤信する程度で足りるとされています。
そして「行使」についてですが、これは直接流通に置くこと、とされています。
両替したり、保険金として提供したり、公衆電話や自動販売機等で使用することも行使に含まれます。
通貨偽造で起訴されると
通貨偽造(同行使)の罪は、通貨に対する公共の信用と、取引の安全といった社会的法益を保護法益としている傍ら、国家の通貨発行権という国家法益に対する罪としても捉えられています。
そのため法定刑は私文書偽造や公文書偽造よりも重く、「無期又は3年以上の懲役」と非常に厳しく設定されています。
「無期又は3年以上の懲役」という法定刑が規定されていますので、通貨偽造で起訴されてしまった場合は、裁判員裁判によって裁判が行われることになります。
裁判員裁判は、国民がもつ常識や感覚を裁判に反映させるとともに、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることを目的として、一般の方も裁判に参加するという制度です。
裁判員裁判となってしまうと、裁判の期間が通常よりも長くなってしまいますし、手続きも複雑になります。
また、法律の専門家ではない方に対して主張していくことになりますので、分かりやすくなるように工夫する必要があるでしょう。
このように、裁判員裁判は通常の刑事裁判とは違ってきますので、裁判員裁判の経験もある刑事事件専門の事務所に弁護活動を依頼したほうがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っており、通貨偽造・同行使のような裁判員裁判対象事件も扱っています。
奈良県で起こした刑事事件でお困りの方、通貨偽造・同行使の罪でお困りの方、裁判員裁判に強い弁護士をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
飲食店経営者の監禁事件
飲食店経営者の監禁事件
監禁事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
奈良県奈良市で飲食店を経営するAは、常連客の一人がここ3カ月間ツケで飲食していることに悩んでいました。
あるとき、これ以上はツケにできないと思ったAは飲食代を請求しましたが、支払いを拒まれてしまいました。
我慢の限界が来たAはこの常連客を翌朝まで閉店後の店に監禁し、これまでの飲食代をまとめて払うように迫りました。
後日、常連客が奈良県奈良警察署に監禁の被害届を出したとAに報告に来ました。
このままでは逮捕されてしまうかもしれないと思ったAは、刑事事件専門弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
監禁罪
監禁とは、人の行動の自由を場所的に拘束することです。
刑法第220条には「逮捕及び監禁」として監禁罪が定められています。
法定刑は「3月以上7年以下の懲役」が規定されており、罰金刑のない厳しいものとなっています。
監禁罪は、不法に人を監禁する事で成立しますが、「不法に」とは、具体的にどのような行為を言うのでしょうか。
監禁の方法
監禁と聞くと縛って身動きができない状態など暴行脅迫を用いての方法を想像するかと思いますが、必ずしもそうではありません。
学説的には、その手段、方法を制限しておらず、有形的方法であるのと無形的方法であるのとを問わないのです。
暴行、脅迫を用いる方法は当然のこと、お風呂に入っていた人の服を隠すなど人の羞恥心を利用する方法や虫や動物などその人の苦手なものを配置して動けなくさせるなど恐怖心を利用する方法、偽計によって被害者を錯誤に陥らせる方法などによっても、監禁罪が成立する可能性があります。
また、不作為による監禁事件も存在します。
例えば、被害者がオートロック式のドアから誤って倉庫内に入り、室内に閉じ込められたのを知りながら、倉庫の管理人がドアを開けなかったような場合です。
この管理者は何もしていませんが、このように何もしなかったことが不作為による監禁罪に問われる可能性もあるのです。
示談交渉
監禁罪の法定刑は罰金刑の規定がない厳しいものとなっています。
罰金刑が規定されていないということは、略式手続きによる罰金もないので、起訴されてしまうと正式裁判が開かれることになり、無罪判決を獲得しなければ、執行猶予を付けられるかどうかの問題になってきます。
このように厳しい法定刑が規定されている場合でも、しっかりと被害者と示談を締結し、検察官と交渉をしていくことで不起訴処分が獲得できる可能性もあります。
示談交渉は、処分が決定されるうえで非常に重要な要素の一つとなりますが、一般的に加害者本人からの示談交渉は受け入れてもらえないことが多いです。
これは、被害者が加害者とはもう関わりたくない、許せないなど理由はさまざまですが、弁護士が付くことにより示談締結の可能性は高くなるといえるでしょう。
それは、弁護士が間にたつことになれば、被害者は加害者本人とは直接やりとりをすることなく、示談交渉をすることができるからです。
さらに、法的知識の豊富な弁護士により被害者の方にもしっかりとした説明をすることができます。
また、もしも示談を締結できなかった場合についても弁護士は示談の経過などから起訴しないようにと検察官と交渉していくことによって不起訴処分を目指していきます。
不起訴処分を目指せるかどうかなど、処分の見通しに関しては一度、専門家である弁護士に相談に行きましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には刑事事件に強い弁護士が多数在籍しています。
刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せください。
まずはフリーダイヤル0120-631-881にて無料法律相談、初回接見のご予約をお取りください。
ご予約のお電話は24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
公然わいせつ事件の弁護活動
公然わいせつ事件の弁護活動
公然わいせつ事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
奈良県生駒市に住む会社員のAは、仕事のストレスから性欲が溜まり、露出がしたくなり、人通りの少ない路上で機会をうかがっていました。
すると女性が一人で歩いているのを発見し、その女性の前に飛び出して、下半身を露出しました。
後日、犯行場所を通った際に警察官から職務質問を受けたAは、女性が奈良県生駒警察署に届け出たことにより、公然わいせつ事件として捜査していることを知りました。
警察に逮捕されてしまうのではないかと不安になったAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
公然わいせつ事件
公然わいせつ罪は、刑法第174条に定められており、公然とわいせつな行為をした者に対して「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」の罰則を規定しています。
公然わいせつ罪は、社会的法益である性秩序を保護法益とした法律で、強制わいせつ罪や強制性交等罪などの性犯罪事件のように、個人の性的自由を保護法益とするものではないので、法律的に被害者は存在しないことになります。
法定刑をみればわかるように、公然わいせつ罪は、強制わいせつ罪や強制性交等罪のように重大な犯罪ではありませんが、性犯罪(わいせつ事件)として区分され、強制わいせつ罪、強制性交等罪のような重要犯罪に発展するおそれもあることから、警察の捜査は積極的に行われています。
公然わいせつで逮捕されるか
法定刑を見るとそれほど重い犯罪ではない公然わいせつ罪ですが、現行犯の場合は逮捕されてしまうことも珍しくありません。
また、今回の事例のように公然わいせつ事件として警察が捜査を開始し、犯人として割り出された後に逮捕されてしまうこともあります。
特に連続して犯行に及んでいたり、罪証隠滅、逃走等のおそれがあったりすると、警察に逮捕されてしまう可能性は高くなるでしょう。
ただ、公然わいせつ事件は身体拘束を受けずに事件が進んでいく在宅事件となるケースも多く、犯人として割り出された時点で警察署に呼び出されて取調べを受けたり、現行犯逮捕されても検察官へ送致されずに、その日のうちや翌日に釈放されたりすることも予想されます。
在宅事件では警察の捜査が終了すれば検察官に送致されることになり、その後検察官が起訴するか否かを決定するのですが、初犯の場合は、略式罰金で正式裁判とはならない可能性が高いでしょう。
しかし、略式罰金でも刑事罰を受けることにはなるので、前科は付いてしまうことになります。
前科を避けたい場合には、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
弁護活動
前述のように、法律的には、公然わいせつ罪に被害者は存在しませんが、今回の事例のように女性に見せつけたような場合には、見せつけられた女性は実質的な被害者ということになります。
弁護士はこの実質的な被害者に謝罪、弁済等をし、その後、検察官に処分の交渉をしていくことで不起訴処分を目指して活動していきます。
処分の見通しに関しては専門的な法律知識が必要になってきますので、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
公然わいせつ事件やその他の刑事事件で警察に逮捕されるか不安のある方、前科を避けたいという方は刑事事件に特化した「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
在宅事件の場合は無料法律相談にお越しいただき、ご家族が身体拘束を受けている場合は初回接見をご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
殺人事件の自首に付き添う弁護士
殺人事件の自首に付き添う弁護士
殺人事件の自首について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
奈良県大和高田市に住む会社員のAは、介護のために実父と同居していました。
しかし、介護の疲れなどから精神的に弱ってしまい、楽になりたいと実父の首を絞めて殺してしまいました。
警察へ自首するかどうか悩んだAは、まず、刑事事件に強い弁護士に相談に行くことにしました。
相談後、弁護活動を依頼することに決め、弁護士が付き添って奈良県高田警察署に自首に行くことにしました。
弁護士は自首により、逮捕されることになったAに対する弁護活動を開始しました。
(この事例はフィクションです)
殺人事件
殺人罪は非常に重たい罪です。
殺人罪で起訴されて有罪が確定すれば、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」が科せられます。
殺人罪は故意犯ですので、成立には殺人の故意(殺意)が必要です。
殺人の故意(殺意)がない場合は、殺人罪は成立せず、死亡という結果があったとしても、過失致死罪や、傷害致死罪等にとどまる可能性があります。
殺人の故意(殺意)は、確定的である必要はなく、未必の故意、条件付きの故意、あるいは包括的な故意であってもよいとされています。
殺人罪で起訴されてしまった場合、裁判員裁判となり通常であれば、執行猶予が付かない実刑判決が予想されます。
しかし、言い渡される刑が減軽され、執行猶予となる可能性がある3年以下の懲役の言い渡しであれば、殺人罪であっても執行猶予となる可能性があります。
今回の事例のAについては介護疲れからの犯行ということもあり、事情によっては情状酌量の可能性はありますし、自首したことによる減軽の可能性があります。
自首
自首は、刑法第42条に規定されており、犯人が捜査機関に対し、自発的に自己の犯罪事実を申告し、その処分を求める事をいいます。
捜査機関が犯罪事実を認知していても、被疑者を割り出していない段階で出頭すれば自首となりますが、すでに被疑者が割り出されている状況では、自首として扱われない事があります。
自首は、基本的に犯人自らが警察等の捜査機関に出頭し、申告する事で成立しますが、直ちに捜査機関の支配下に入る状態で、電話や第三者を介する方法で申告しても、自首と認められる事があります。
刑事訴訟法上、自首は捜査の端緒に過ぎませんが、刑法上は、刑の任意的な軽減事由となります。
ただ、自首による刑の減軽については、必ずされるわけではないので、自首が成立するのか、自首することにメリットがあるのかなどについては専門家である弁護士の見解を聞いたほうがよいでしょう。
裁判員裁判
裁判員裁判の対象となる事件については、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項に定められています。
1号 死刑又は無期の懲役、禁錮に当たる罪に係る事件
2号 法定合議事件であって故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件
今回の事例の殺人罪は死刑も規定されていますので、裁判員裁判対象事件となります。
裁判員裁判は、国民がもつ常識や感覚を裁判に反映させるとともに、司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上を図ることを目的としています。
しかし、裁判のプロではない一般の方が参加するわけですから、先入観や偏見などによって、偏った事実認定をされたり、不当に重い量刑となるおそれがあるという弊害も指摘されています。
実際に、裁判員裁判で出された死刑判決が、高裁で無期懲役となった裁判例などもあったりします。
さらに、裁判員裁判では公判前整理手続きが必ず必要になるなど通常とは異なった流れで裁判が進んでいくことになりますので、刑事事件を専門に扱う弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
殺人事件、裁判員裁判対象事件に強い弁護士をお探しの方、自首に付き添う弁護士をお探しの方は、刑事事件に強い弁護士が多数所属する、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
体罰が刑事事件化
体罰が刑事事件化
体罰での刑事事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事件~
奈良県桜井市の公立中学で教師をしているAは、部活動の指導中に熱くなってしまい、生徒の顔を拳で殴ってしまいました。
生徒が家に帰り、親に事情を話すと、殴った理由にも納得ができず、許せないと思った保護者が奈良県桜井警察署に傷害事件として通報しました。
その後、Aの自宅に警察官が訪れることになり、Aは傷害の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが連れていかれる様子を見ていたAの妻でしたが、何か対処をしなければと刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
体罰が刑事事件化
昔は、家庭内や学校内で体罰が行われることは、ある種当たり前であったと言えるかもしれません。
しかし、そういった風潮が招いてしまった悲惨な事件を教訓として、現代では体罰に対する対応も厳しくなりつつあります。
今回の事例のような学校での体罰については、新聞やテレビのニュース等でも、報じられることがよくあり、警察が介入して刑事事件化することも珍しくなくなりました。
もちろん、学校で起こる体罰事件すべてが、刑事事件に発展するわけではありませんが、刑事事件化した場合に対応することも必要となってくるでしょう。
また最近では、学校だけでなく家庭内での、親が子供に対して行うしつけでさえ、暴行、傷害、場合によっては殺人未遂として刑事事件に発展することもあります。
なお、体罰事件で適用されることの多い暴行罪は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」傷害罪は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」がそれぞれ規定されています。
刑事事件化されると
被害者である生徒や、生徒の親が警察に被害を訴えれば、警察はその訴えに基づいて捜査を開始します。
教師と生徒の間で起こった事件であれば、被害者が重傷を負っている等よほどの理由がない限りは、教師が逮捕される可能性は高くはありませんが、ないとは言えません。
しかし、この様な、体罰による暴行、傷害事件では、被害者と示談していれば、前科の有無などもかかわってきますが、不起訴処分を得ることも充分に考えられます。
ただ、被害者感情が強く示談できなかった場合や、被害者の傷害の程度が重かった場合、事件に至る経過が相当と認められなかった場合は、罰金等の刑事罰が科せられる事もありますので、こういった見通しに関しては専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
また、刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験も豊富であり、安心してお任せいただくことができます。
特に今回の事例のように被害者が生徒であれば、未成年ということになりますので、その示談交渉の相手方は保護者ということになり、示談交渉が困難になって行くことも予想されますので、専門家に任せるようにしましょう。
公務員の刑事事件
今回のAのような公務員が刑事事件を起こしてしまった場合、刑事処罰とは別に、地方公務員法等の特別法に定められた規定によって、懲戒免職などの処分を受ける可能性があります。
地方公務員法では、様々な基準を設け、分限や懲戒の処分対象を明記しています。
そしてその中に、刑事事件を起こした場合の処分についても定められているのです。
場合によっては、刑事事件の処罰としては不起訴に終わっても、勤務先で懲戒免職など厳しく処分される事もあります。
刑事事件に強い弁護士であれば、そういった懲戒の処分に関する見通しについてもきちんと立てることができますので、今後の見通しを聞くためにもまずは無料法律相談へお越しください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
ペットの殺害事件
ペットの殺人事件
ペットの殺人事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事件~
奈良県生駒市に住むAは、隣人と犬の鳴き声や散歩のときに糞を始末しないなどのマナーについてたびたびトラブルになっていました。
ついに我慢できなくなってしまったAは犬を殺してしまおうと決意しました。
Aは夜中に大量の農薬を混ぜたドッグフードを用意し、犬に食べさせました。
翌日、犬は死んでおり、それを見つけた隣人は様子がおかしいと感じ、奈良県生駒警察署に通報しました。
使用された農薬や隣人宅に設置されている防犯カメラの映像などからAの犯行であることが特定され、Aは器物損壊の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
その後、報告を受けたAの妻は被害者との示談交渉を含めた弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
今回の事件は器物損壊についてです。
まずは条文を見てみましょう。
刑法第261条 器物損壊
「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」
今回注目していただきたいのは「傷害した者」の部分です。
器物損壊の客体については他人の物であるとされていますが、この他人の物には動物が客体となることも予想されているので、傷害という文言が使用されているのです。
つまり、今回の事例のように他人の飼い犬などのペットを殺害すれば、器物損壊罪が適用されることになります。
法律でいう「物」とは、財物と同義で、広く財産権の目的となり得る一切の物ですので、動産、不動産はもちろんのこと、動物や植物も含まれることになるのです。
親告罪
器物損壊は親告罪であると規定されています。
親告罪とは、検察官は、被害者等の告訴権者の告訴がなければ、公訴を提起することができません。
公訴を提起できないとはつまり起訴することができないということです。
つまり、親告罪では、告訴されてしまったとしても示談を締結するなどして告訴を取り下げることができれば、起訴されることはないのです。
示談ができなかった場合、犯行に及んだ動機や、損壊した物の価値、謝罪、弁済の有無にもよりますが、初犯であれば、略式罰金になる場合が多いです。
しかし、略式罰金といっても罰金刑を受けることになるので、前科は付くことになってしまいますし、もしも再犯であれば、正式起訴されて刑事裁判となる可能性もあります。
そのため、器物損壊事件を起こしてしまった場合は刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士ならば示談交渉の経験も豊富にありますので、示談を締結できる可能性も高くなります。
弁護士による身体解放
今回の事例のAも逮捕されることになってしまいましたが、隣人トラブルから起こった器物損壊事件では、被害者との接触可能性が高いなどの事情から逮捕されてしまう可能性も低くありません。
さらには、身体拘束が継続される勾留が決定されてしまう可能性もあります。
勾留期間は10日~20日ですが、弁護士の活動によって、勾留を阻止したり、勾留期間を短くして釈放を早めることができるかもしれません。
勾留は検察官が請求し、裁判官が決定しますので、弁護士はそれぞれのタイミングで意見書を提出するなど、勾留が決定されないように活動していきます。
また勾留が決定してしまった場合にも不服申し立てや、延長された場合にはその期間の短縮なども行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では器物損壊、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。
法律相談に関しては初回無料でのご案内となりますので、お悩みの方は一度お電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。
色情盗で住居侵入窃盗
色情盗で住居侵入窃盗
住居侵入窃盗について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事件~
奈良県大和郡山市に住む会社員のAは、自宅近くのワンルームマンションに住む女性に好意を持つようになりました。
たまたま部屋番号を確認することができたAはその女性の部屋のベランダから、干してある下着を盗む色情盗を繰り返していました。
近くの防犯カメラなどの映像からAの犯行であることが特定され、Aは奈良県郡山警察署に逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
色情盗
色情盗とは、たとえば下着泥棒などのことで「窃盗罪」に当たる行為ですが、財産目的というよりもわいせつな目的があるような場合のことを指します。
今回の事例のAのように、マンションのベランダに干してあった下着等を盗んだ場合、窃盗罪だけでなく、刑法第130条の住居侵入罪にも問われる可能性があります。
マンションの敷地やベランダに不法に侵入して下着を盗み、住居侵入と窃盗が成立することになると、この二つの罪は牽連犯として扱われます。
牽連犯とは、数個の犯罪が、手段と結果の関係にある場合をいいます。
牽連犯の科刑
刑法第54条第1項後段には、「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるとき」について規定されており、この規定が牽連犯です。
この牽連犯については刑を科する上で一罪として扱われ、数個の犯罪のうち、最も重い罪の法定刑によって処断されます。
今回の事例の色情盗の場合をみてみると、住居侵入という手段によって窃盗の結果をもたらしています。
住居侵入の法定刑は「3年以下の懲役又は10年以下の罰金」、窃盗の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています。
この場合、窃盗罪の方が、住居侵入罪よりも重いことになりますので、起訴されて有罪が確定すれば、窃盗罪の法定刑内で刑事罰を受けることとなります。
ただし今回のAのように色情盗を繰り返していた場合には、話が変わってきます。
この場合は2回以上事件を起こしているとして、併合罪で処理されることになります。
併合罪の科刑
併合罪は牽連犯とは違い、単純に2つの罪を犯してしまった場合をいいます。
この併合罪については刑法第45条から第53条までに規定されており、その処理の仕方などが記されています。
併合罪となる場合の有期の懲役又は禁錮に関しては、それぞれの罪の刑の長期を合計したものを超えない範囲で、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものとなります。
つまり、色情盗を繰り返し行っていた場合は15年以下の懲役の範囲で懲役刑が科されることになります。
そして罰金については多額が合計されることになりますので、色情盗を繰り返してしまっていた場合には「15年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の範囲で処断刑がかされることになります。
法定刑は刑法の条文に記載されているため、だれでも読むことはできます。
しかし、実際の事件は複雑化することもありますし、余罪があったりして、実際にどのような法定刑の範囲で処断されるかは専門の知識がなければ分かりにくいです。
さらに、実際の見通しということになると事件当時の細かな状況なども関係してくるので、事件の見通しについて知りたい場合は法律の専門家である弁護士の見解を聞く必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
住居侵入窃盗、色情盗の繰り返しなどでお困りの方やそのご家族の方がおられましたら、フリーダイヤル0120-631-881までお電話いただき、無料法律相談、初回接見のご予約をお取りください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、犯罪行為による刑事事件・少年事件の弁護活動を中心に扱う法律事務所です。
奈良県をはじめ近畿地方の刑事事件・少年事件について多数の解決実績がございます。また奈良県の刑事事件・少年事件に精通した弁護士が、一から、専門知識と経験に基づいて親身に対応いたします。
当事務所では、刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。無料相談のご予約は365日24時間お電話にて受け付けています。奈良県の刑事事件・少年事件で少しでもお困りの方は、いつでもご相談ください。